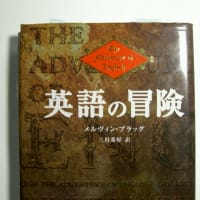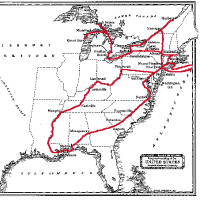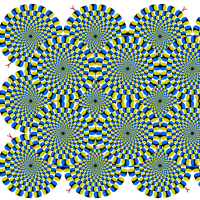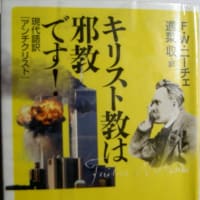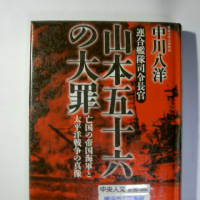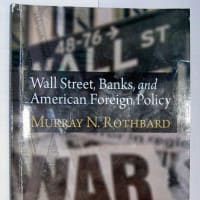ホルバイン作「墓の中の死せるキリスト」
地獄の呵責が三百年も続けば、どんな民族でも、その魂に決定的な刻印を受けざるを得ない。しかしその経験が何か積極的な精神を生むか否かはまたおのずから別の問題だ。屈辱は骨の髄まで奴隷的な、矮小な人間を生むこともあるだろう。ロシアでは、この苦悩の経験から、あの特徴ある巨大な反逆児が生まれ、黙示録的人間が生まれた。「地下室の住人」や「永遠の夫」は虐げられ踏みつけられた「奴隷」の反逆を典型的な形で具現している。徹底的に虐げられた敗北の人の魂の中からでなければ、あのような反逆は生まれない。魂の深部で淡々と燃える恐ろしい怨嗟、忿恚、羨嫉、嫉妬。上べには諂いの笑いを浮かべながら魂の底で殺人を犯すのだ。
謂われなくしてあまりにも残酷な暴行、拷問、折檻を受けた敗者の恨みは、頑固な、恐るべきひねくれとなって内攻する。しかもこの怨恨だけが、一切を剥奪されてしまった赤裸の魂の、最後に残った一点なのである。怨恨は外にむかって爆発せず - 爆発したくとも外面への途は固く閉ざされているのだ - 深く深く内面へこもって行く。ひと思いに恨みを返し仇をうってしまえば胸もせいせいするだろうに、そうする代わりに、誰も知らないようなうす暗い部屋の片隅にひっそりと身を隠して、そこから四六時中じっと相手をみつめている。そしてまた、そうしていることが当人にとっては死ぬほど苦しいと同時に、その裏では、身顫いが出るほど劇しい快楽でもあるのだ。こんな非合理的な、根深い反逆はロシア的人間だけのものである。
しかしながら「奴隷」の体験は、こういう執拗なひねくれ者だけを生みだしたのではなかった。それは同時にあの特徴あるロシア黙示録的人間をも生んだ。一見するとまるで相反するように見えるけれど、神への反逆と神への帰順とはここでは同じ一つの根から出た二本の幹である。ロシア的反逆とロシア的信仰とは双生児だ。イヴァンとミーチャが兄弟なら、スメルジャコフもまた同じ血をひいている。三百年の奴隷生活、その深い絶望と苦悩のどん底から、救済への希救が、神への熱い祈りとなって湧き上がる。
ロシアが形式的に基督教を受け入れたのは基督教会の東西分裂以前の古い昔であるが、それが本当にロシア人の血となり肉となったのは韃靼時代を通過してからであることは注目に値する。あまりに平穏無事な日々をおくっている人は自己の存在の危機を自覚しない。ところが、ひとたび、思いもかけぬ悲境に投げ込まれる時、彼は愕然として存在の危機を自覚し、魂の救いを憶いはじめる。韃靼人支配下のロシア人もそうだった。深い憂愁と絶望の淵から、大いなる「汝」にむかって呻吟とも祈りともつかぬ悲痛な叫び声を捧げるボードレールのように、彼らは生まれてはじめて心の底から、真剣に神を憶い、神を喚んだ。
わが陥りし幽暗の深淵の底より
われ汝の憐みを乞い求む、「汝」わが愛する唯一のものよ。
世界は陰鬱に、見はるかす地平は鉛にとざされ、
恐怖と冒瀆は夜の闇に漂う。
自分で苦難の十字架を背負ってみて、はじめて基督の十字架の意義もわかった。自分で本当に苦しみ悩む身になった今にして、彼らは「苦しみ悩む人」基督に対する狂おしいばかりの愛に目ざめた。
・・ 以上、「ロシア的人間」井筒俊彦著 中公文庫 から。
かくして、ロシア人は過酷な奴隷時代を経て、魂の救いを求め宗教に目覚めた。
韃靼人(モンゴル)に侵略される前のキーエフ公国時代の日本はといえば平安時代。
文化の中心は京都に限られ、宮廷を中心にして、これをめぐる貴族たちの文化が当時の日本文化の全部であった。
平安文化の特徴は、「古今集」にみられるように四季の歌と恋歌が半分以上を占めているように、繊細で、女性的で、優美閑雅、感傷的である。
とにかく男は涙にくれて、泣いて長袖を濡らしている。女々しい。
思想において、情熱において、意気において、宗教的あこがれ、霊性的おののきにおいて、学ぶべきものはなにもない(鈴木大拙、「日本的霊性」)。
救いがいらないということは幸せなことだったが・・