[書籍紹介]

広告代理店の制作部に勤める高城(たかぎ)祐二は、
学生時代、演劇を志すも、先輩の助言で、
「観る」立場に位置を定めていた。
24歳の時、ある新作芝居を観に行って、
連れの女性にすっぽかされ、
売り切れの切符を求めて劇場前に来ていた
17歳の新条奈美と一緒に観劇する。
その後、妙な経緯で、奈美の父親の工藤に引き合わされ、
東京に出て来る奈美の、かりそめの兄の立場に立たされる。
奈美は私生児で、
工藤は認知していない父親だった。
短大を受けずに演劇学校を受験した奈美は
上京して、女優を目指すのだという。
目標は吉田日出子。
物語は、二人が出会った芝居が上演されるたびに
二人が交流し、
祐二は会社で順調に出世していくが、
奈美は女優として芽が出ない。
そして決断する時が迫る・・・
佐々木譲という作家は、
警察小説の人だと思い込んでいたが、
こんな青春小説を書いていたとは。
「鉄騎兵、跳んだ」で「オール讀物新人賞」を受賞して、
作家デビューしたのが1979年で、
本作の刊行が1984年だから、
ごく初期の作品ということになる。
「笑う警官」や「警官の血」、
直木賞受賞作「廃墟に乞う」などを書く
遥か前のことだ。
24歳の青年と17歳の少女との、4年間の
みずみずしい交わりを、ある芝居を背景に展開する。
吉田日出子の名前は出て来るものの、
その芝居の題名は本編では書かず、
あとがきでその名を明かしているのは、
自由劇場の「上海バンスキング」。

1979年1月、六本木自由劇場にて初演、
翌年の1980年3月、再演し、
1981年5月、銀座の博品館劇場に進出、
1983年3月には、博品館劇場をはじめとする各劇場においても上演された。
本作は4つの章に分かれているが、
上記上演時期と一致している時系列。
「上海バンスキング」は、
その後も全国公演など、
小劇場演劇としては記録的なロングランとなり、
当時の劇評家たちに絶賛された。
作者は斎藤憐で、
岸田國士戯曲賞を受賞、
演出は串田和美、
主演は吉田日出子、
昭和初期の日中戦争時の上海を舞台に、
時代に翻弄されたミュージシャンたちを描いた音楽劇で、
登場するバンドは、
プロのミュージシャンではなく、
劇団員によって編成されたものだった。

1984年と1988年の2度にわたって映画化されている。

バンスキングの“バンス" とは、
英語のadvance borrowing (前借り)を省略した日本語。
私は1990年のシアターコクーンでの再演を観ている。
立ち見だった。

吉田日出子の名前は、
昭和42年(1967年)の
NHKのステレオドラマ「叙事詩 曼荼羅」で知った。
ギリシャ悲劇をリオのカーニバルを舞台に映像化し、
1959年度のアカデミー賞外国語映画賞を受賞した
マルセル・カミユ監督の映画「黒いオルフェ」を

青森のねぶた祭りを舞台に翻案した
寺山修司の脚本。
吉田日出子は主人公のチサを演じ、
声だけで、こんなに豊かな感情表現が出来るのかと
驚愕した覚えがある。
「叙事詩 曼荼羅」は、
今、私のパソコンで聴くことが出来る。
ついでに声だけで驚かされたのは、
市原悦子で、
昭和60年代の連続ラジオドラマを聞いて、
その声の演技の素晴らしさに、
この人はどういう人だろうと興味が湧いた。
その後の市原悦子の活躍はご存知のとおり。
題名の意味は、
吉田日出子を含む劇団のバンドと共に、
上海へ向かうクルージングのこと。
祐二と奈美は、参加できず、
横浜港でその船を見送るところで物語は終わる。











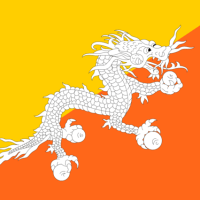









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます