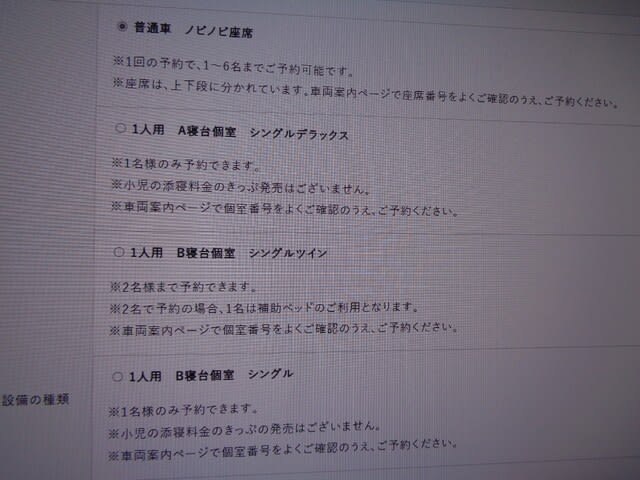[書籍紹介]

惣菜と珈琲のお店「△」を営むヒロは、
一つ上の晴太、中学三年生の蒼と
三人で暮らしている。
ヒロが惣菜を作り、
晴太がコーヒーを淹れ、
蒼は元気に学校へ出かける。
店はオフィス街と住宅街の中間にあり、
買っていくのは若い社会人か忙しい主婦。
惣菜や弁当の販売だけでなく、
店内で食事も出来る。
常連も着き、
三人で食べていくだけの売上はあるようだ。
三人の関係は何だろうと思って読んでいると、
ある時点で「晴太は兄です」とヒロは言う。
どうやら兄弟らしい。
では、両親はどうしたのか。
なぜ兄弟だけで暮らしているのか。
そうしているうちに、
蒼の父親という人物のことが書かれ、
三人は血のつながりがないことが分かる。
三人は擬似家族を作っていたのだ。
そして、それぞれの置かれた環境が描かれ、
三人とも、
「お前は要らない」と見捨てられた者たちだと判明する。
そして、ある日、
蒼は中学卒業とともに家を出たいと言い始める。
全寮制の専門学校に行きたいという。
これまでの穏やかな日々を続けていきたいヒロは、
激しく動揺する。
そして、蒼が行方不明になり、
数日後、帰って来た。
その行先は・・・
というわけで、
町の片隅に住む、
惣菜店を営む3人の物語。
さわやかな話のようだが、
実は背景にかなり重い問題を抱えている。
蒼の旅立ちは、
三人の関係を根底から揺るがす。
それは蒼の成長の結果で仕方ないことだった。
蒼が見るはずの未来を、
私たちの手で見えなくしてしまっているんじゃないかとか、
本来形になるはずのない『家族』を、
私たちが無理やり作って
蒼に押し付けているんじゃないかとか。
屈託なく笑う蒼の顔を免罪符に、
これが幸せだと決め込もうとしていた。
きっとふたりともかわかっていたのだ。
父に捨てられ母とも引き離された蒼には、
晴太だけが、
そして同じく父も母もいない晴太にとって、
蒼だけが家族だということを。
入れて、と思った。
私もそこに入れて。
うらやましいとかあこがれるとか、
そんな感情を飛び越えて、
私もそこに入れてねしいと思った。
三人の関係が次第に分かって来る経過は、
なかなか巧みだ。
ヒロが学校で浮いた存在だったというのも、
出自が分かった時、納得する。
次作の「さいわいわ住むと人のいう」と同様、
最初の方を読んだだけで、
筆者の才能が伺える。
やがて直木賞の候補になるだろう。
惣菜店兼食堂の話なので、
料理が頻繁に出て来て、
食欲をそそる。
刑事の花井や日村など常連も魅力的。
最後の方で、
ヒロの名前の由来が分かり、
母親と再会する場面は、
祖母の存在も合わせ、
読ませる。
母親がヒロに手放した理由を話そうとすると、
祖母は止める。
「言い訳はしない。
これ以上見苦しい母親になったらいけない」
「おれたちはここまでだよ」との晴太の言葉が悲しい。
題名の由来は、次の言葉に集約される。
「たとえそのつぎ目が不格好でも、
つながっていられればそれでいいと思っていた。」
第11回ポプラ社小説新人賞受賞作。
選考員満場一致だったという。
本屋大賞の対象になってもよかったと思うが
ノミネートさえされなかった。
筆者菰野江名は、現役の裁判所書記官だという。