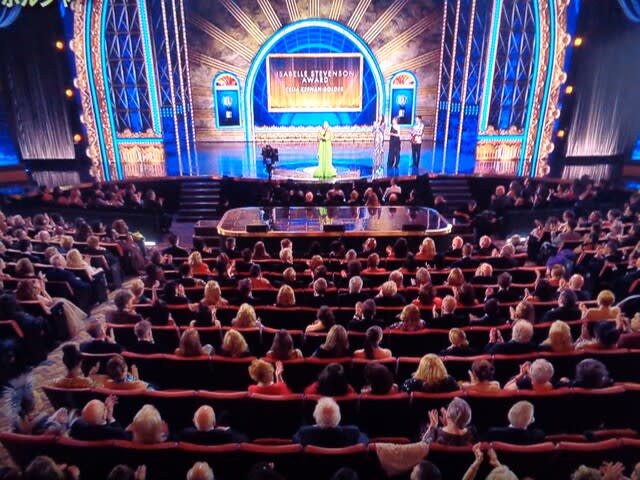[書籍紹介]

衝撃的な題名。
廃寺同様、神社も廃されることがあるのか。
著者の嶋田奈穂子さんは、
滋賀大学非常勤講師。
人間文化学、地域研究の専門家。
インドで調査旅行をしている時、
同行していた恩師が亡くなり、
その死を看取った経験が
神社の看取りに重なっている。
「なぜあそこに神社があるのか」という設問に対して、
日本中の神社を訪問して、その意味を探る。
衝撃的な事実を知った。
日本に神社は7万8千602あり、
コンビニの数より多い、
とはよく言われるが、
その78602の数字は、
神社本庁が把握している、法人格を持つ神社の総数であって、
法人格を持たない、
地域に根ざした神社の数は入っていないということだ。
それらの神社を数に入れたら、
その総数は驚異的なものになるに違いない。

本書の中で、滋賀県守山市の野洲川流域の神社を調べる下りがある。
ある神社を調べようとして、
滋賀県神社庁の発行した「滋賀県神社誌」を見ると、
掲載されていない。
つまり、法人格を持っていないのだ。
恩師の「ゼンリンに載っているだろう」という助言に従って、
「ゼンリン住宅地図」に当たってみる。
これは、調査員が実際に町を歩いて作った地図だ。
その結果、野洲川流域の神社数は380社。
神社誌の掲載数は110社なので、
その3倍の数の神社が存在する。
更にその現場に行ってみると、
更地になった神社や、地図に載っていないものもあり、
結局、野洲川流域では378の神社が存在した。
地図の調査員も、その場所が何か分からなかったらしい。
著者はそれらの場所を「聖地」と呼ぶ。
本書の副題に「変わりゆく聖地のゆくえ」とあるのがそれだ。
その「聖地」が何らかの理由で消えていく過程を追う。

「看取られる神社」とは、
それらの名もない社の終末を描いたものだ。
その原因は主に人口減少、過疎化だ。
神社は古代から集落の中心にあった。
しかし、人口減少社会に入り、
集落が消滅すると神社はどうなるのか?
住民がその土地を離れる時、
神社も終末を迎える。
誰が、どうやって神社を閉ざすのか。
そのプロセスを追う。
村落で最後の住民になった人が村を離れる時、
それが行われる。
ご神体の像を近くの寺に移したり、
地元の博物館に遺贈したりして、
最後は神社の建物を解体、焼却する。
それが、集落の最後の一人となった住民の仕事なのだ。

「毎日少しずつ壊してね、
最後の柱を倒した時、
主人は泣き崩れて、しばらく立てなかった」
まさに、人を看取るのと同じである。
神社を廃する行為は、
誰かを看取ることと重なっていく。
始末を終えた村人は「これで安心して死ねる」とつぶやく。
そして、跡地は更地になり、
そこに神社があった痕跡も残らない。
神社としてあった土地を自然に還すことで
初めて神社を閉じることになる。

明治末期、神社整理が行われた時、
日本各地には、
大小さまざまな神社、寺、社、祠が数多くあり、
それぞれ住民の信仰を集めていた。
明治政府は、西洋化の過程で
一つの村には一つの神社を置く措置が取られ、
多くの神社が合祀(ごうし)された。
明治41年~42年の頃の話だ。
政府は、小さな神社や祠(ほこら)を、
強引に合祀することで消滅させた。
それに対して、住民は密かにそれらの「聖地」を守り続けた。
外的圧力は、聖地の目に見える部分を廃止することはできたが、
住民の精神までを変えることはできなかったのだ。

神社について調べてみると、
それが日本人の精神的根幹をなしていることが分かる。
よく日本人は無宗教だというが、
日本人の心の中には神社がある。
キリスト教やイスラム教のように、
開祖や教義がなくとも、
日本人は宗教的民族だ。
まさに日本は「神の国」なのだ。