「なにげない」 と 「さりげない」 は音も意味も似ていて、違いが分かりにくいですよね。
私は、意識しているかどうかで使い分けています。
「なにげない」 は、無意識とか、ほぼ何も考えていない様子。
「つい」「うっかり」 言ってしまった 「なにげない ひと言」 で相手を傷つけてしまったり、
その反対に、狙ったわけでもないのに、「なにげない ひと言」 が仲間に大うけすることも。
「さりげない」 は、意識している事を、わざとらしくなく自然に行なう様子。
配慮のある 「さりげない ひと言」 は、優しい心遣いとして、相手の心に届くことでしょう。
では次の場面では、どちらの言葉が合うとお思いになりますか?
1 「ふと立ち止まって、〇〇げなく空を見上げたら、 がキレイだった」
がキレイだった」
2 「泣いてしまった私に、友人が〇〇げなくハンカチを差し出してくれた」
3 「〇〇げなく を置いたら、コーヒーがこぼれて
を置いたら、コーヒーがこぼれて  を汚してしまった」
を汚してしまった」
4 「デートのときに、彼が〇〇げなくエスコートしてくれました 」
」
1と3が 「なにげなく」、2と4が 「さりげなく」 というイメージでしょうか。
「なにげなく」 は自分で感じ、「さりげなく」 は他人が感じてくれるようですね。
さて、いつの頃からか頻繁に耳にするようになった 「なにげに」 という言葉。
「なにげない」 から派生したのであろうと想像はつきますが、
「なにげに美味しい」 は、「なんとなく美味しい」 のか 「意外と美味しい」 のか、
はたまた 「可もなく不可もなく」 という程度なのか、いまひとつピンと来ないのです。
さらに私を悩ませるのが、「さりげに」
「さりげに見送った」 というのは、涙も心の動揺も隠して、淡々と見送ったのか、
万歳三唱(いつの時代でしょ ) など大騒ぎをせず、静かに見送ったのか、
) など大騒ぎをせず、静かに見送ったのか、
柱の陰から、明子お姉さんのように見つめていたのか?(お分かりの方は同世代です )
)
言葉は生きていますから、時代と共に変化も進化も退化もします。
「なにげございません」 「さりげございません」 という方向に進まなかったのは結構ですが、
仲間内ならともかく、オフィシャルな場面で使うのには、「さりげない配慮」 が必要かと。
「なにげなく言った言葉」 が、相手に伝わらないどころか、誤解されては困りますものね。
お読みくださいまして、ありがとうございます。
さりげなくクリックしていただけますと嬉しいです

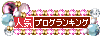
私は、意識しているかどうかで使い分けています。
「なにげない」 は、無意識とか、ほぼ何も考えていない様子。
「つい」「うっかり」 言ってしまった 「なにげない ひと言」 で相手を傷つけてしまったり、
その反対に、狙ったわけでもないのに、「なにげない ひと言」 が仲間に大うけすることも。
「さりげない」 は、意識している事を、わざとらしくなく自然に行なう様子。
配慮のある 「さりげない ひと言」 は、優しい心遣いとして、相手の心に届くことでしょう。
では次の場面では、どちらの言葉が合うとお思いになりますか?
1 「ふと立ち止まって、〇〇げなく空を見上げたら、
 がキレイだった」
がキレイだった」2 「泣いてしまった私に、友人が〇〇げなくハンカチを差し出してくれた」
3 「〇〇げなく
 を置いたら、コーヒーがこぼれて
を置いたら、コーヒーがこぼれて  を汚してしまった」
を汚してしまった」4 「デートのときに、彼が〇〇げなくエスコートしてくれました
 」
」1と3が 「なにげなく」、2と4が 「さりげなく」 というイメージでしょうか。
「なにげなく」 は自分で感じ、「さりげなく」 は他人が感じてくれるようですね。
さて、いつの頃からか頻繁に耳にするようになった 「なにげに」 という言葉。
「なにげない」 から派生したのであろうと想像はつきますが、
「なにげに美味しい」 は、「なんとなく美味しい」 のか 「意外と美味しい」 のか、
はたまた 「可もなく不可もなく」 という程度なのか、いまひとつピンと来ないのです。
さらに私を悩ませるのが、「さりげに」

「さりげに見送った」 というのは、涙も心の動揺も隠して、淡々と見送ったのか、
万歳三唱(いつの時代でしょ
 ) など大騒ぎをせず、静かに見送ったのか、
) など大騒ぎをせず、静かに見送ったのか、柱の陰から、明子お姉さんのように見つめていたのか?(お分かりの方は同世代です
 )
)言葉は生きていますから、時代と共に変化も進化も退化もします。
「なにげございません」 「さりげございません」 という方向に進まなかったのは結構ですが、
仲間内ならともかく、オフィシャルな場面で使うのには、「さりげない配慮」 が必要かと。
「なにげなく言った言葉」 が、相手に伝わらないどころか、誤解されては困りますものね。
お読みくださいまして、ありがとうございます。
さりげなくクリックしていただけますと嬉しいです














 タイム。 甘酸っぱいケーキの美味しさといったら
タイム。 甘酸っぱいケーキの美味しさといったら 







 から葉書サイズの鏡を取り出して、メイクスタート
から葉書サイズの鏡を取り出して、メイクスタート 








 CM もありましたっけ。
CM もありましたっけ。






