台北故宮博物館に訪れた時、実物の汝窯青磁の美しさに魅了され、その際色々調べた覚えがあります。温潤の色合いが印象的でした。
北宋の時代(960年 - 1127年)に現在の河南省に作られた汝窯は、内戦があったため、わずか二十年で滅びてしまいました。そのせいで、製造工程は残されず、現代に残されている本物は、わずか60点。北京故宮博物館や台北故宮博物館を中心に所蔵されています。
最近、中国に出張した主人が汝窯青磁風の茶器セットを買ってきてくれました。いわゆるレプリカですね。
レプリカとはいえ、汝窯青磁のいくつかの特徴がしっかり再現できています。

趣深い青。半透明の釉薬、器壁が薄く、一見玉のようにも見えます。ちなみに、博物館にある本物の逸品に使う釉薬は、宝石の瑪瑙(めのう)の粉末が混ぜてあるらしいです。

茶杯は、花びら五枚の形。茶杯の縁側や内側の模様で見られるように、淡い灰色を帯びた黄色で施しています。ほかに、茶壺の注ぎ口などもその工夫を語るような作りとなっています。

茶器の底に特徴があります。底部に、3-6個まで足のような支えがあります。「芝麻鋲」と言われるものです。

茶こしセットは蓮の葉をイメージした作り。
蓮の花や菊の花の形にした茶杯や酒付きは、古代の文人の間で人気でした。手に花の形をした杯を持つと、まるで花そのものを持っているようと言われています。なんて優雅の発想だろう。
あれっ、しかし、宋の時代のお茶と言えば、まだ固形茶と粉茶しかない時代です。あの時代に、このような形の茶壺もないはず。やはり、あくまでも汝窯青磁風にした現代の茶器ですね(苦笑)。
汝窯青磁のことをもっと知りたいならば、「宋汝窯(song4 ru3 yao2)」と調べてみるといいです。

どのお茶が合うかな。とこれから色々試していくのが楽しみです。
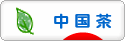 にほんブログ村
にほんブログ村



















