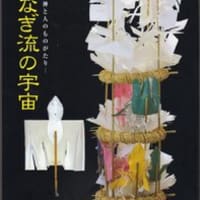釣竿に取り付けられた釣糸のことを「テグス」という。
一般的には、「道糸」と「鉤素(ハリス)」がある。どちらもテグスであることに違いはない。たとえば、ヤマメ釣りにおける道糸が0,8号であれば、ハリスは0,6号となる。道糸は、竿から伸びた糸であり、その先にハリスが結び付けられ、その先端に鉤が付く。すなわち道糸は、釣糸全体を遠くへ飛ばす役割と、一定の強度を確保するためのものであり、ハリスは魚の眼に見えにくくするためになるべく細い糸を使うものである。が、私たちは、そんな面倒なことはしない。「通し」と言って、竿先から鉤まで一本の糸を使う。「0,6号の通し」といえば、竿から鉤を経て魚に至る釣糸のすべてが0,6号のテグスで仕掛けられているのである。なんとなれば、大きな魚がかかった時や、水中の岩に引っ掛かったり、木の枝に絡まったりしたときに切れるのが、この道糸とハリスの結び目なのである。釣り逃がした大魚も惜しいが、その後、鉤とハリスを咥えたまま生きていかねばならぬ魚の一生を思うと気の毒でたまらぬ気がするのである。数年前のことだが、25センチほどのヤマメを釣り上げたら、そのヤマメはルアーを喉の奥まで呑み込んだまま生きていた。3~4センチもある魚の形をしたプラスチックを体内に持ちながら、なお餌を追って来たのである。これなどは、釣り師の釣技の未熟と無神経が責められるべき残酷なる事例であろう。
テグスとは、天蚕(てんさん)と呼ばれる野生の蚕の仲間の楠蚕(くすさん)の幼虫から採った糸のことである。クスサンの幼虫は7~10センチほどもある芋虫で、体色は青く、白い毛が密集して生えていることから白髪太郎などと呼ばれる。楠や銀杏の木に付く。その繭は茶色で網目は粗い。このクスサンの幼虫の体内から繊維を酢に漬けながら引き出すと、糸が採れる。これが天蚕糸〈てぐす〉である。同じく天蚕の仲間である山繭(やままゆ)の緑色の繭から採れる糸が古来絹糸として珍重されたことと比べると、やや位が低いきらいがあるが、釣糸としての歴史も見落としてはならない。釣糸がナイロン糸になり、丈夫になった今も、テグスという名称だけは厳然と残っているのである。

私は現在、0,6号のナイロンテグスを使うが、夏から秋口へかけては0,5号に変える。釣師に責められて用心深くなっているヤマメは、わずか0,1ミリの差を見分けるのである。長年の釣友、渓声君は、いよいよとなったら0、175号という極細のテグスを使うというが、その糸は私どもの眼には見えないほど細い。そして糸は細いほど良く釣れるが、切れやすいという二律背反の業を負う。大物を釣り逃した後、切れて風になびく糸を呆然と見ながら、釣り師は未練がましいため息を一つ吐くのである。
「テグス」の語源を調べると、弓を引くときに手が汗で滑らないようにするために「薬煉(くすね)」という薬を塗り付け、万全の態勢で敵の襲来に備えたことにちなむ、とある。それも語源の一つではあろうが、弓弦そのものや弓の握りの部分などに巻く糸などに天蚕糸が使われていたことを考慮の内に入れるべきであろう。釣聖・太公望は、鉤の付いていない糸を垂れ続け、それにより周の国の大臣と面識を得て軍師として推挙され、殷王朝を滅ぼして周王朝を樹立した。「国」を釣った釣糸は、天蚕糸だったのではなかろうか。
私どもは、今、窓辺で天蚕を飼い、山繭を育てているから、その繭を見るたびに、古い時代の釣糸のことを思うのである。



![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/6e/f9/fc9850d8b3c82e8fb632dd0e58544ae8.jpg)
![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/13/ac/8c71d06187180435b05ed1c03dc39f9b.jpg)
![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/7c/a0/7c84411b10e13d7c7864db0847dc41a3.jpg)
![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/26/ff/2cd96bde95f3683b56e1066fd0f39808.jpg)
![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4d/1c/76b0b83d26669d5899ed89a064100174.jpg)
![変異するとき/予告・武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:15>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2a/07/efa184aee8271918ffcc80f4ee249500.jpg)
![紅蓮の炎に映し出されるものは/田口雅己「八百屋お七」[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:14>]アートスペース繭コレクションから④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4e/19/7e04bc2df5ec82a537852c6b8ca6c477.jpg)
![雨の歌を聴きながら/田島征三「雨の森の一日」[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:13>]アートスペース繭コレクションから③](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/38/d0/6ce5e0ef312e53248f7a96bb6436247f.jpg)