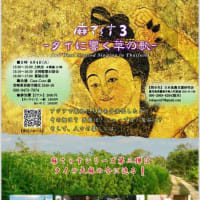阿蘇外輪山から久住高原へと通じる道の脇に、広大な草原があり、その一角に萩の群生地を見つけた。
車を停めて、その小道を歩いてみる。
道は、たちまち草藪に覆われ、私もその草の原の中に没してしまう。
萩の花が満開である。
甘い蜜の香りが、野に満ちている。
行き行きて 倒れ伏すとも 萩の原
芭蕉とともに「奥の細道」を旅した曾良の句である。
芭蕉忍者説は、松尾芭蕉の出身が伊賀藤堂藩の武士であったこと、奥の細道への旅が、藤堂藩の水運を利用したものであったことなどにより、根強い支持者があるが、私は芭蕉は忍者ではなく、その弟子として奥の細道の旅を企画し、先導し、旅の全体をコーディネートした河合曾良こそが忍者であったと解釈している。芭蕉の句は、一句一句が旅の感動にもとづく芸術表現であるが、曾良の句は、平凡で何のとりえもない。曾良の日記をみると、彼は句作に励んだり土地の文人と交わったりするよりも、神社仏閣を訪ね、地勢を記録し、その土地の人情風俗を観察している。これこそが、徳川政権下で安定期に向かった時代の「忍者」の役割にもっとも近いではないか。その土地(藩)に不穏な情勢や幕府の政策に合致しない実態などがあれば、容赦なく改革に乗り出し、藩の入れ替えや取り潰しなどを行ったのが、この時代の国家政策であった。忍者は、「戦闘」を任務とした時代を終えて「諜報」を主たる活動としたのである。
それでも、苦楽を共にした旅が終わりに近づき、師と別れる時になれば、率直な心情が発露され、掲句のごとき絶唱が生まれたのである。
――師よ、これでお別れです。わたしは任務により別の道を行きますが、行く先で倒れるようなことがあれば、そこは萩の花の咲き乱れる野であってほしいものです。
これに対し、芭蕉は
今日よりは 書付け消さん 笠の露
の句を残す。芭蕉の笠には、『乾坤無住同行二人』と書かれ、曾良との旅を続けてきたのだが、これからは一人、草の露でこの同行二人の文字も消すことになるだろうとの詠嘆。
ここまでは研究されつくしており、私も別の機会に書いたことがある。
「曾良忍者説を補強する」
というのは、ここからである。
萩の花咲く草原に立ち、花の香に埋もれていて、私は突然浪漫主義者としての心象よりも「曾良は忍者であった」いう連想のほうが強くはたらいた。
曾良は芭蕉と別れる時、芭蕉の死を予測していた。すなわち、大阪での芭蕉の茸中毒死である。これは茸中毒ではなく毒殺である、という説も根強い。任務を終えた、または曾良の忍者としての仕事を知り尽くした芭蕉は「消された」のである。その根拠はいくつかあげられるが、要約すれば曾良が向かったのは彼の故郷の伊勢長島であり、その後彼は武士の身分に復帰している。任務を完遂したことの報酬であろう。
さて、「研究」や「学説」となればここからの入念な調査・研究・考証が必要だが、私はそのつもりはないので言及はここまでにして曾良のその後のことを少し書いておこう。曾良は、最晩年を壱岐で過ごし、没する。彼の数奇な人生の果ては、朝鮮半島を望む国境の島であった。ここにも曾良の生涯を象徴する何かが秘められているような気がするが、それは文学的推理の範疇なので立ち入らない。
壱岐で曾良の墓を訪ねた時、強い西風が吹き、水仙の花が風に揺れていた。
玄海の 風は東へ 曾良の墓
私は俳句を詠む習慣はないが、その時はこんな感懐が湧いた。
風は、遠い伊勢長島方面へも吹き行くだろうと思ったのである。





![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/35/8c/9dce2c42453d0e3d2de364e09f67c529.jpg)


![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/33/0643f5c268a5eef814a7199587b7f10a.jpg)
![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4d/1c/76b0b83d26669d5899ed89a064100174.jpg)
![変異するとき/予告・武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:15>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2a/07/efa184aee8271918ffcc80f4ee249500.jpg)
![紅蓮の炎に映し出されるものは/田口雅己「八百屋お七」[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:14>]アートスペース繭コレクションから④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4e/19/7e04bc2df5ec82a537852c6b8ca6c477.jpg)