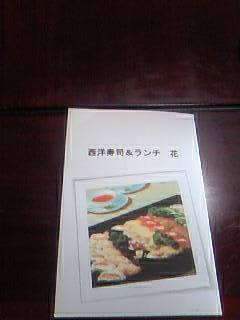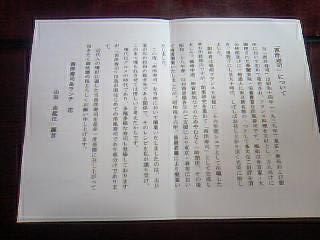加工・業務用国産野菜の利用拡大セミナーに出席してきました。
場所は三田共用会議所というところで、重厚な建物、厚い絨毯の廊下でした。
それはともかく・・・
平成19年ごろからの加工・業務用に国産の野菜を使っていこうという動きを、農林水産省のホームページや、他のイベントで追ってきました。
利用拡大セミナーは初めての参加でしたが、生産者、流通業者、実需者の順に発表がされていました。

生産者側の動きとしてJAグリーン近江とJAとぴあ浜松の二つのJAの発表がありましたが、JAの戦略によって、この分野の取組がどのように進むのかということがよくわかる事例でした。
倉敷地方卸売市場の卸売事業者である倉敷青果荷受組合は、卸売市場で初めてISO22000の認証を取得する、カット野菜工場をつくるなど、利用拡大について取組を推進するなどしている事例でした。4定(定時・定量・定品質・定価格)に加えて、低価格が必要という話が印象的でした。
(株)ロック・フィールドの発表もありましたが、加工・業務用に関しては、多くの利害関係者を抱えているからでしょうか、レタスの葉一枚一枚の検品の写真はありましたが、近年の事業の取組の説明に終始していました。
ロイヤルホスト(株)も事業の取組について説明されていましたが、消費の経年変化がわかる興味深い内容でした。
ちょうど、弊社が農商工連携人材育成事業に取り組んでいるときと、この加工・業務用野菜の取組が重なるのですが、その後公務員として農業の6次産業化に取り組むに至って、「対象」と「内容」に共通項が多い取り組みが、政策をどこの・だれが作るかによって、名称も支援施策も変わってくることに居心地の悪さを感じています。
共通項に目を向け、重複する分野のなかで、本当に必要な政策は何かに注目すれば、業界や業種の壁が低くなり、無駄のない資源配分につながっていく気がします。
すでに、省庁横断的にと考え、少人数で目的を達成するために政策を組んでおられることを知らないわけではありませんが。