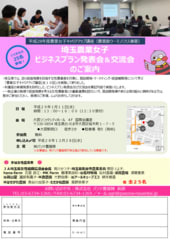奥富康雄さんが亡くなりました。
「早すぎる」ということばでは表しきれない、とても惜しい方でした。
「さといもコロッケ」「ごぼうのぴくるす」
少し変わっているけど、どこにでもありそうな商品。
けれども、この二つの商品には、これまでにない発想と思慮により生まれました。
産地の価値を地域に還元し、一度消えた産地を復活させる。
それを、農商工連携・6次産業化という手法を使って。
農業者自らがそれを主導するという、革新的な取組だったと思います。
私が知っているのは、この農業革新者としての、奥富康雄さんです。
1 さといもコロッケの取組
はじめて奥富さんに会ったのは2010年7月でした。
弊社が平成22年度農商工連携等人材育成事業(地域版)全国商工会連合会(経済産業省事業)の採択を受け、カリキュラムを精査するなかで、埼玉県川越農林振興センターにご紹介頂きました。
当時、奥富さんが代表をしていた「さやま里芋増産倶楽部」は、「さといもの親芋を活用したコロッケ」により、より若い世代に里芋の美味しさを知ってほしい、そして狭山市が高品質なさといもの産地だということを地域の方に知ってほしいという考え方から、前年より農商工連携に取組んでいました。
採択された研修プログラムは、「農商工連携のサプライチェーンのキーポイントである、①生産者、②流通、③加工、それぞれにおける課題を整理する」という組立でした。
企画の意図としては農業者と加工業者が直接つながることによるリスクを認識し、さらに、それを踏まえたWin-Winの関係をどう築くかということでした。
「さやま里芋増産倶楽部」は、前年にコロッケの商品化ができたものの、加工業者との直接の関係はできたものの、直接つながったことにより、いくつもの課題を抱えることになりました。
①加工業者の依頼に応じて農業者自らが加工業者の稼働日に合わせて数量を揃え直接納品すること。
②加工業者の供給先が限定されており、それが狭山市にはないこと。
など。
当初の目的を達成するために、新たな加工業者、新たなサプライチェーンを構築しようとしているところでした。
弊社の研修の意図した農商工連携におけるサプライチェーンに関する問題を、現在進行形で解決しようとしているところでした。
研修の意図を説明し、ご快諾頂き、10月9日の実習の日を迎えました。
実習は、畑での掘り取りから、調整作業、さといも親芋活用の説明という組立でしたが、あいにくの雨天でしたから、圃場見学と、事前に掘り取って頂いていた株を調整作業することと、前半部分を切り替えました。
雨天の中の圃場見学でしたが、積極的な質問が重ねられました。
大きなさといもの株から、実際にほぐして、小芋、孫芋、そして親芋に触ってみることは、受講された方には初めての体験で、また、奥富さんの説明とも相まって、充実した時間になりました。
さやま里芋増産倶楽部の取組は、大きな農業法人の経営者をはじめとする当日参加された方々から、大きなエールを贈られました。
その後、親芋をコロッケにする試みは、出荷にはJAの協力、新たな加工業者の生産から販路に至る協力、地域の卸売業者の協力、狭山市内の精肉店などの協力を得て、狭山市内で買えるもの、学校給食で供給できるもの、そして、さらに幅広い皆さんに楽しんでもらえるものになりました。
さといもコロッケは、エキナカで増えているそば店「そばいち」の看板メニュー「狭山のさといもコロッケそば」で食べることができます。
※そばいち
この取組は、平成24年度地産地消優良活動表彰において関東農政局長賞を受賞しました。
※新商品「さといもコロッケ」の開発を通じた地域活性化
※さといもコロッケの開発を通じた青年農業者育成活動
また、この活動を支援した埼玉県農林部川越農林振興センターは、平成23年度普及活動全国コンクールにおいて農林水産大臣賞を受賞しました。
※(社)全国農業改良普及支援協会プレスリリース
※埼玉県Webページ
いまでも、出色なこの農商工連携の取組は多くのメディアを賑わせています。
2 ごぼうのぴくるすの取組
かつて(40年ほど前)狭山市を含む入間郡域は「入間ごぼう」の産地として有名でした。品質の良さから全国的なブランドになりましが、連作障害等で作付面積が減少したことから、「幻の入間ごぼう」と言われていました。
「入間ごぼう」復活プロジェクトの提案があったのは、私が2012年8月から3年8か月ほど任期付職員として埼玉県農林部で仕事をさせて頂いた、初年度の半分が過ぎた頃でした。
※任期付職員の経緯
生産適地であり、さといも→ごぼう→さといもの輪作を試したところ、成績がよく、鮮度の高さで差別化が可能な商品なので、産地化すれば収益力の高い生産物になり地域の農業に貢献するものになるとのことでした。
具体的には、
①品種は「サラダごぼう」という、サラダなどの用途に合う品種。
②販売形態は、一定のサイズで。
③収穫機を使い収穫を機械化したい(のちに収穫機を導入)。
④産地として復興するために生産者を増やしたい。
⑤そのときに、規格外や調整の切り落とし部分にも価格が付くようにしたい。
⑥④と⑤のために、加工品を考えたい。
これで「入間ごぼう」の産地を復活させたいとのことでした。
食のトレンドを勘案し、ごぼうでピクルスができないかと検討をはじめました。
輸入ピクルスの統計を見るとB to Cの商品が増えていること、流行をつかんで品揃えする店舗でごぼうをはじめとする国産素材でのピクルスの販売が目立つようになってきたこと、加工度を上げずに幅広く流通する商品であり素材感を残すことが可能であることなどが、ピクルスとした理由です。
農業の6次産業化の支援ということで、川越農林振興センターの普及指導員の方などとともに、既存商品の調査、商品試作に取り組み始めました。
「もとのごぼうの風味を生かす」というのが、商品開発にあたってのもっとも重要な優先順位でした。
さらに、試作品がどのような素材と組み合わせれば、ごぼうの美味しさが引き立つのかという開発プロジェクトでの試食を重ねました。
また、地域の方に試食をしてもらったところ、男性にはあまり好まれない反応があったりと、一進一退を繰り返しました。
一年ほどで商品の方向性が決まり、加工業者の方がプロジェクトに加わりました。
試作品は、形状を変え、調味を変えの何度も検討を重ねました。
素材との組み合わせによる検討をいくつもの視点で検討しました。
「もとのごぼうの風味を生かす」ということから軸足を外さずに、商品の検討が続きました。
そして、2014年10月に「ごぼうのぴくるす」と「ごぼうのもろみ漬け」が発売されました。
※プレスリリース
当初は、サプライチェーンを組み立てるのに、加工業者の方に負担をかけることになりましたが、地域のJAの協力により、卸問屋が入り、供給の流れが整理されました。
鮮度の高さで差別化が可能な農産物であったことが、これを可能にしました。
その後、「JAいるま野狭山野菜部会サラダごぼう部会」ができ、耕作面積も生産者も増加しました。
※埼玉県知事の「とことん訪問」記録
農業者自らが、地域の農業生産の将来像を明確に抱き、仕組みを作る。その仕組みの一つとして、農商工連携型の6次産業化に取り組む。
あくまでも、6次産業化は手段で、重要なのは地域の農業という軸足のしっかりした取組でした。
自らの地域に軸足をおいた「儲かる農業」のビジネスモデルを作り続けた農業革新者でした。
活躍の舞台は限りなく広がっていたのに。
残念で、無念で、さびしくて、胸が痛くなります。