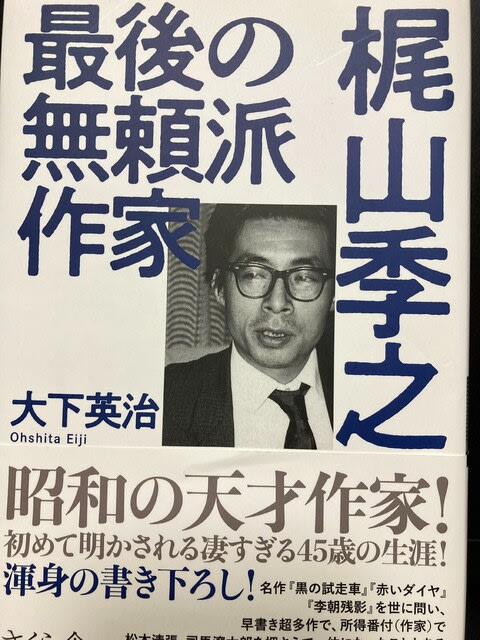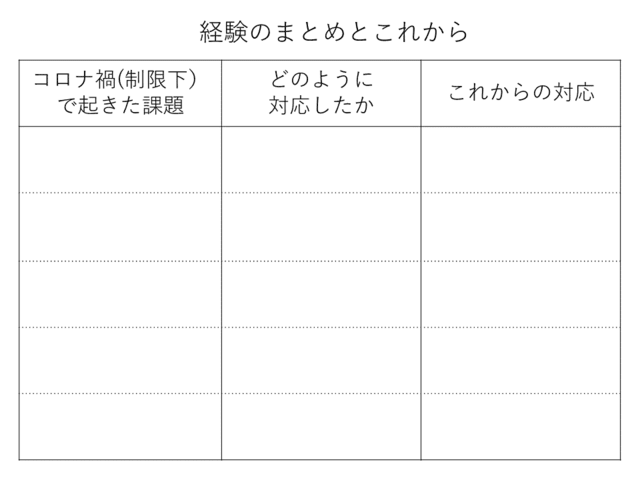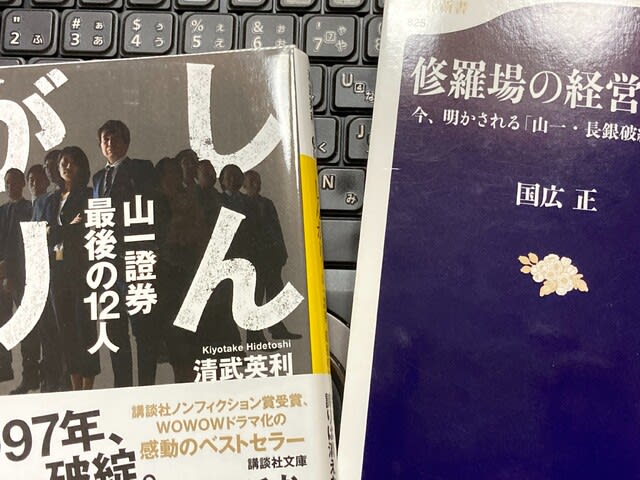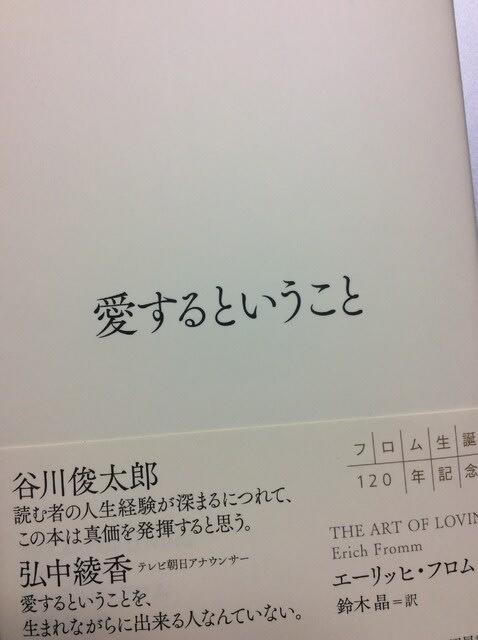フオーリーブスや郷ひろみの話題が教室の中であふれていたあのころ、斜に構えていた私が、「白馬に乗った王子様が迎えに来るシンデレラストーリー」に全く興味がなかったと言えばうそになるかもしれない。
新しい音楽を知ることができる音楽番組を見ることは楽しいこと。
ある日の音楽番組。NANANAのパフォーマンスを見て驚いた。さわやかなのに、ゴリゴリに歌って踊っている。
YouTubeチャンネルで、ichibanを見た。インスタレーション作品のよう、美しいアートだ。
グループ名が「King & Prince」、デビュー曲が「シンデレラガール」、ファンが「Tiara」。
白馬に乗った王子様が迎えに来るシンデレラストーリー、そのものの彼らは、それを体現し、やがて、現代のあり方、そして、少し先の未来を見つめて、自分たちの次に向けて努力していった。
「かっこいいというものは、こういうことじゃないか」、「かっこいい」ことをビジネスにする彼らが、追及して自ら新しい姿を作っていった。そして彼らの言う「おとな」が、伸びしろのすごさに驚嘆しながら、最大のパフォーマンスを引き出していったことに疑う余地はない。
さて、彼らを抱える組織はどうだろうか。特徴は3つある。①リーダー企業であること、②収益モデルができていること、③成功体験を維持していることである。
①リーダー企業である。
全方位の競争戦略を持ち、芸能のすべての分野が領域で、すべてのメディアが領域市場。
かかえる人材の年代は幅広く、ターゲットはフルカバレッジ。
売り手としての圧倒的な強みを持つ。
②収益モデルができている。
ファンクラブによる顧客の囲い込み、成長ストーリー、CDデビューというステップアップストーリーの提供等により、組織だけでなく、それぞれのグループのブランドロイヤリティを高める仕組みができている。
③成功体験を維持している。
NHKで20年以上自社タレントのみの番組を維持するなど、業界のトップ企業としてゆるがない体制を続けている。
競争と選抜と組み合わせについての暗黙知があり、CDデビュー後は本人たちが努力を怠らなければ売れる仕組みがあった。
収益力の高いときに、次の投資をはじめる。
社内ベンチャーを育て新しい成長のたねを探す。
両利きの経営。
チーズが無くならないように、鼻を利かせる。
列挙に暇がないこれらの考え方は、それを実行に移す難しさを示している。
成功体験に甘んじている組織のなんと多いことか・・・
さて、「King & Prince」はどうだろうか。
最大利潤を享受し、過去の成功体験を追随している組織が違和感をもった時、これまでの組織が思う常識を打ち崩しかねない動きと感じた時、組織は変化への強烈な拒否反応を起こす。それが少しの動きであろうとも。
「かっこいい」を追求する彼らは共通のベクトルで強いチームを作り出し、組織の標準から逸脱し、先に進み続けるエネルギーは、経営陣の違和感を増大させ続けてきたことだろう。自分たちが持っている価値観を覆されることは、言葉にも出さないが怖いことだ。
そうなったとき、組織は、「不在化~なかったことにする」を選択する。
この収益モデルは崩れない。タレントは彼らだけではない。
ただ、本当のことは分からない。
能力の高い彼らは、別のステージに立っても輝き続けるだろう。ただ、「おとな」たちを含んだ最適解を探し続けたチームが、さらなる成長のステージを見せてくれるという、視聴者の願望を実現してくれる・・・という希望は消え失せようとしている。
チームごと買い取ってくれる強力な投資家が現れないのかと考えたりもする。
業界の外側にいるきらびやかな世界には届かない、世間の片隅から考えたこと。
すこし言葉に出してみた。