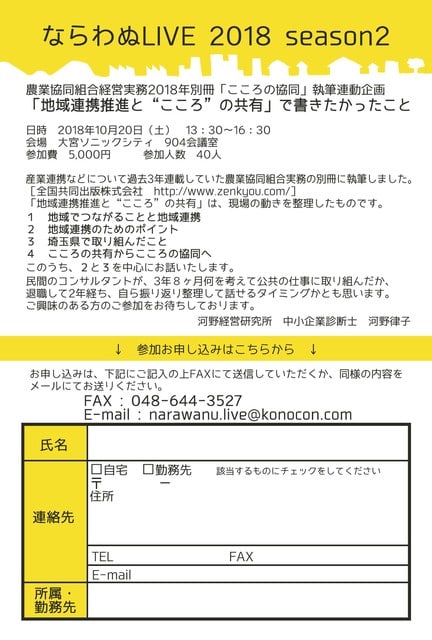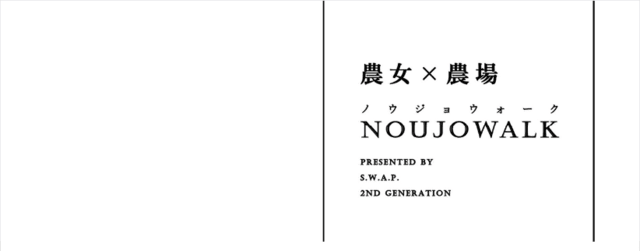その1で、「ドメイン」「マーケティング」「オペレーション」それぞれにポイントがあるとしましたが、今回は「オペレーション」について考えてみます。
タイトルを、「講座やセミナーを組み立てること」としましたが、この「組み立てること」は、サービスの提供の場で完成するものですが、事前の「オペレーション」にあたる部分で、目標とする品質を目指して準備しておくことが大切になります。
いくつかの場面を想定して、考えてみましょう。
■ 体験教室の場合
① タイムスケジュールを立てる
体験してもらいたい内容に直接にかかる時間、準備や片づけなど間接的にかかる時間、属人的な理由で時間が前後する場合があるのでその時間を見込む。
② 教材・手順書を作る
体験してもらいたい内容の、教材・手順書を作る。再現性が求められるときは、過程の写真などを入れ込み、状態の変化が分かるようにする。
また、衛生的な管理が必要でメモなどを取らずに理解してもらいたい場合は、口頭での説明の内容を書面に書いておくようにする。
理解をしてもらいたい内容が多い場合は、全ての内容について書き込まず、事前にメモを取ってもらいやすい教材を用意する。
③ 原材料等の準備をする
全体の時間の配分の中で、原材料等の計量等から取り組んだ方が良い場合と、計量小分けしていなければその後の対応に手間取る場合があるが、体験教室のコンセプトとしてどちらの方法がふさわしいかという検討と、衛生的な面等での検討をして、準備をしておく。
原材料等に特徴がある場合、特徴と言っても、農業生産物であれば作り手の想いや、購入したものであっても他との差別化できるものであれば、②の教材・手順書に記載するようにする。
④ 体験する場の管理について
調理室、加工室の場合、危険なものの取り扱いや、衛生手順の徹底が必要になる。
屋外の場合、圃場内などでは、危険予知行動が必要になる。
これらの必要事項のレクチャーの時間をタイムスケジュールに読み込むとともに、分かりやすい掲示、ラミネートしたもので基本事項の徹底等を行える準備をしておく。
⑤ 協力体制
複数で運営するとき、サポートを頼む方がいる場合、①~④まで事前に理解しておいてもらう。
加えて、仕事をしてもらう場所や位置取りについて、事前の打ち合わせを入念にする。
といったことが、ポイントになりますが、内容や時期などにより検討しなければならないことが増えてきます。
■ 講座やセミナーの講師の場合
① テーマと内容の整理をする
参加される方や依頼される方から「期待されている情報や特技」と、それについて話したい内容の整理をする。
中心となる大項目を立て、中項目、小項目と順に組み立てていく方法、主要構成要素を、洗い出し、ストーリを組み立てていく方法、その他自分にとってやりやすい方法で講座の全体構成を考える。
実習・演習が組み込まれる場合には、「期待されている情報や技術」と、時間等の制約条件のなかで、何が出来るのかアウトラインを考える。
② タイムスケジュールを立てる
講座の構成要素の時間配分を考え、「期待されている情報や特技」を効果的に提供できるかどうか考える。
①で考えた内容を取捨選択し、時間配分を考える。
③ スライドショーのコンセプトを考える(使う場合)
PowerPointで原稿をつくり、プロジェクターやモニターで映すということが、一般的になっているが、スライドショーについては、いくつもの考え方があり、期待されている情報や特技の提供方法として最もふさわしいものとするように基本コンセプトを考える。
・スライドで、提供する情報全てを整理しページごとに情報を書き込み伝える。
・ビジュアルを重視し、写真を中心として、具体的な現場情報を伝えるものとする。
・スライドを、板書(黒板・ホワイトボードでの重点記述)の代わりと考え、具体例の写真を加えるなどする。
等
さらに、教材として配布するかどうか、配布するなら全部なのか一部なのかも検討する。
④ 教材を作る
先ず前提として、配布資料が必要かどうか、そのボリュームはどのくらいが必要かということを検討する。
また、スライドショーのコンセプトによって、配布できる教材の内容も変わる。
教材は、最終的な、サービスの品質に関わってくるが、講師の差別化のための要素となる。
話す場面以外に、演習や実習、グループワークを組み込む場合があるが、テーマと内容につなげていくための、枠組みとその説明がきちんとしておかないと、参加された方が躊躇してしまい、グループワークの場合、ただの交流会になってしまう。(それを目的にする場合は別)
⑤ シナリオ、ノート、書き込みを用意する
講座やセミナーの場合、原稿を棒読みしては納得感が得にくいが、何をどのように説明するかを組み立てるためには、シナリオを作ってみる事も大切。スライドのノートを作るのも同じ効果。
話をするのが得意な方なら、ポイントを書き込んでおくことも有効。
といったことがポイントとなりますが、内容の習熟度、プレゼンテーションの得意不得意によって、変わってきます。
リテールサポートの研修講師をしていた時の方が、今よりも、参加者の方との関係性の結び方が上手で、さらに、研修の講師としてはいい気になっていたと思います。
ただ、その時怖かったのが、自分の経営の知識の未熟さでした。具体策や手法は話せるものの、それによって得られる利得が小売店経営全般にどのように生かせるのか、その肝心なところが整理して話せない自分のふがいなさでした。
それは、大学の専攻が食品化学分野だったため、まさか、そんな仕事に就くとも思わず、経営学の体系的な知識を得ていなかったからです。販売士の資格を2級まで取り、日経を3紙読み、事務所の経済雑誌や商業関係の雑誌を読み漁りましたが、不安は消えませんでした。
中小企業診断士の資格を取ったのは、そのためで、さらに、父と経営学の論議を戦わすことになるとは、考えてみもしないことでした。
分野は様々ですが、経験則で語れることには限界が来ます。
自分が、「講座やセミナー」を組み立てるときには何が必要か考えて、不足する要素、必要となる要素の吸収を貪欲に進めることが大切だと思います。
・・・・・
午前中に常磐線に乗ると必ず進行方向左側の席に座っていました。
なぜかというと、晴れている日は、右側の席は他の路線に比較して非常にまぶしく、大好きな沿線の景色を見続けられないからです。
先日、雨模様のため、右側に座りました。霞ケ浦を見ることができました。
少し、位置を変えると見えるものがあります。