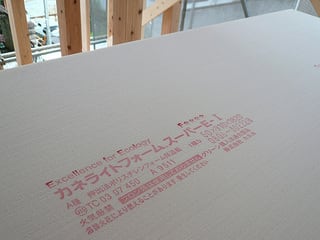窓が付いてきました。
本当に、工事が進むのが早いです。
外壁の構造用合板が、だいたい貼り終わったようです。
窓が付くところが分かります。

現場に立ち寄ります。
天気が良くて気持ちいい朝です。
今日は、Mさんは居ません。他の現場の残工事に行っているとのこと。

こちら側も、ほぼ、外壁の合板は貼り終えているようです。
サッシの取り付けをしています。

不安定な足場の上での作業、器用なもんです。
これは、サッシの外側に付く、防犯用のシャッターの枠です。
「おはようございま~す!」と、中に入ります。
1階の床下地の作業中です。

水平な床を作るための、地味ながら、手間のかかる作業です。
丁寧な仕事です。

105mm角の大引きに90mm角の大引きを架け渡し、910ピッチの碁盤の目状に組んだ剛床仕様です。
根太は架けずに、この上に、直接、構造用合板の24mm厚を釘で止めて、床下地とします。
根太が無いので、「根太レス」工法などと呼ぶこともあります。
最近は、この工法が多いそうです。
根太を組んで床を貼るより、剛性の高い床になります。
材料も少なくて済みます。
ただ、床面の水平をだすのに、「逃げ」がありません。
根太があれば、多少の不陸を、大引きと、床下地の間の、根太で微調節することができるのですが、その調節のための根太がありません。
土台を敷く段階で、シビアに水平を出しておく必要があります。
レーザー測定器が復旧してきたので可能な工法なのかも知れません。
「お疲れさまです!」と、2階へハシゴを登ってあがります。
2階の方が、明るくて気持ちいいですね。

1階担当よりも、2階で作業するほうが、気分が良さそうです。
彼は、アルミサッシを取り付けるための、下地枠を切り出しています。
整頓されて、綺麗な現場です。
わたしの経験では、仕事が丁寧かどうか、現場がうまく動いているかどうかは、現場が綺麗かどうかで、ある程度分かります。
とっちらかっている現場は、たいてい、仕事もとっちらかったり、時間に迫られて混乱していたりします。
化粧梁(仕上げ後も露出する梁)と束は、日焼け、汚れのないように、きちんと養生されています。

居間と食堂は、斜めの天井になります。
台所から南側を見ると窓。

この窓の向こうは、テラスになります。
居間、食堂の窓です。

想定通り、気持ちのいい窓になりそうです。
隣のキャベツ畑が、未来永劫、キャベツ畑ならいいののに、と思います。
「今日も一日、よろしくおねがいします!」と言って、現場をあとに、会社へ向かいます。
明日は、久々、朝から現場で定例です。