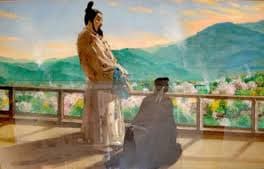倫理の起源62

ところで先に、ソクラテスが若いころ自然哲学に関心をもって熱心に研究したが、自分はそれに不向きなことを知って、人間学的な方面に研究の矛先を変えたといういきさつについて記した。ソクラテス以前の哲学は宇宙万物の謎を解くことを主目的としていたが、ソクラテスは大きく舵を切って、「善とはなにか」「正義とは何か」「よく生きるとはどういうことか」という方向に哲学船の方向を変えたのである。これは哲学の主たるテーマを人間学的・倫理学的なものに求めるのと同じである。
プラトンの弟子・アリストテレスは、このソクラテスの視線変更を再び軌道修正し、哲学(学問)は両方を含んだ総合的な視野を持たなくてはならないと考えた。だから彼の考察領域は、自然学、政治学、倫理学、論理学、詩学、魂の学などあらゆる分野に及んでいる。彼は、ソクラテスの遺志を受け継いだプラトンのような魂の学への激しい情熱に比して、もっと冷静さと客観性と中庸とを重んじたのだろう。そのためにその手つきは、いかにも冷ややかで、賢くて、諸学の博物学とでも形容したくなるような雰囲気を具えている。しかしそのようにしてこそ、宇宙の問題も人間の問題も統一的に理解できるというのが、アリストテレスの密かな理念だったに違いない。そうしてこの理念こそは、今日、学問とか科学とか呼ばれている営みの基本精神を形成している(はずだった)。
さて近代科学がやってきた。それは観察と実験と現実整合性を最重要視する自然学から始まった。そうしてガリレイ、ケプラー、ニュートン、ラボアジェ、ダーウィンら超天才を生み、大成功をおさめた。やがて西洋の人々は、この大成功の果実である「普遍妥当的な法則の確立」をそのまま、あるいは若干の方法的変更を加えさえすれば、人間社会の現象や魂の問題にも適用できるのではないかと考えた。
むろんこのスライド方式によっていくつかの成果は得られたであろう。しかしその際、見落とされていたことが一つある。それは、人間社会の現象や魂の問題を扱うのに、それを扱う主体自身の存立そのものが疑われることがなかったという点である。言い換えると、学問としての客観性が保証されるために、学問主体は、彼が扱う対象からあくまで神のように超越していなければならず、したがって彼自身が人間的・倫理的な問題、つまり生の不安や生活上の迷いなどに囚われていてはならないという条件が暗黙の裡に要請された。
これは自然を対象とする場合にはそれで構わない。重力の法則や天体の法則は、ガリレイやニュートンのある日の気分や彼らの生死に関係なく成り立つからである。しかし人間が人間自身の事象を扱う場合には、この問題を等閑視することは許されない。というのは、ある主体が人間世界を観察しようとするとき、彼はまさに人間世界のただなかに、その一員として参加しつつそうするので、彼自身の精神を形づくっている具体的な文化や歴史や時代の諸傾向から無縁に学問の営みを続けることは不可能だからである。これは要するに、人間世界を対象とする諸学問は、価値の問題から自由に中立的に成立することなどありえないということを意味する。彼の駆使する「学問的言語」は、そもそもの初めからある価値観に支配されているのである。それを排除しうるなどと幻想しないほうがいい。
そのことはまた、どんな人文諸科学といえども、人間学的・倫理学的関心をその方法論のうちにあらかじめ含むべきことを要求する。つまり、ソクラテスが大きく舵を切ったあの方向性を、現代の人文諸科学は見習うべきなのである。
だが現状はどうだろうか。
前期ヴィトゲンシュタインは「語りえぬものごとについては沈黙せねばならぬ」とダンディな見栄を切ったが、この語りえぬものごととは、人間学的・倫理学的な問題のことである。これを聴いた多くの人たちは、新しい哲学(学問)のご託宣を得たように感じて、論理実証主義や分析哲学や記号論理学などの道を切り開こうとした。だが彼らの志向性そのものが深層のレベルで一つの価値意識に拘束されていたのであり、その価値意識とは、「我々は、倫理のことなど無視して、人間社会の事象を純粋に、数学的に、システマティックに学問すべきなのだ!」という選択意志である。
しかし繰り返すが、どんなに細分化された現代の個別諸科学といえども、それが人間世界そのものを対象としている限り、倫理的問題と切り離されて自立的に存立することはあり得ない。そのような脱倫理の体裁を保っている学問や理論は、まさにその脱倫理性のゆえに、必ず人間の現実から乖離した空虚な、あるいは人間の幸福に資さない有害な姿をさらすのである。
たとえば経済学という学問がある。まさしく人間社会の活動そのものを扱う学問だが、現在、この学問の主流を占めている「新古典派」は、経済活動に参加するすべての人間は、利益追求という合理的な目的に従って行動するはずだという前提から出発する。この前提は、人間の意志や行動には不確定な要素が含まれるという当然の認識を無視している。また、社会は個人意志の算術的総合ではなく、まさにそれらが合成されることによって、それ自体が独自の構造と力学を持った生き物のようになるという視点も欠落している。いずれにしてもこの前提が脱倫理的であることは明らかだろう。脱倫理的であることを担保することによって、この学派は、理論的学問の純粋性追求の地歩を獲得できたと錯覚するのである。
次に、この合理的経済人の経済的目的を最大限に達成するためには、市場の自由を最大限保証しなければならないと、この学派は考える。よってどんな社会状態になろうと、国家などの公共体の市場への介入は極力排除しなくてはならない。そうすれば、需要と供給とは自動的に均衡状態に達するので、価格は安定する。モノやサービスの供給量が決定されれば需要はそれに見合うようについてくる。前者が過剰になったり後者が過小になることは単なる一時的な現象だから、長い間には完全雇用が実現するはずだ。ゆえに非自発的な失業はあり得ない……。
しかしこのようなオートマチックな考え方は、実態とまったく合わない。企業の倒産や投資の停滞、非自発的な失業は、デフレーション、すなわち供給が過剰となってモノが売れない場合にはいくらでも見られるし、インフレーション、すなわち通貨の量が膨張するときには、バブル経済で返済不能な債務が増大し、物価の上昇に賃金の上昇が追いつかず多くの人の生活は困窮する。
こうした景気の変動現象と、それが引き起こす国民の貧困化に対して、新古典派経済学はあえてそっぽを向こうとするのである。それもそのはず、彼らにしてみれば、経済学とは「純粋な」理論学問であって、低所得者の生活の困窮やそれによる社会秩序の混乱を解決しようという社会倫理的な動機など端から持っていないからである。現実と理論とが乖離しているときには、現実のほうが間違っているのだ!
しかし、ケインズはそうではない。彼の経済学は、企業が大規模に倒産もせず、失業者が増大せず、国民がそこそこ豊かな生活を送れるようにするには、どういう考え方をすればよいかを絶えず念頭に置いている。景気の極端な変動を抑制するには、市場の自由にゆだねたのではだめで、状況に応じて国家の適切な介入が必要である。失業者が増大したり深刻な不景気が出現したり貧富の格差が極端に開いたりした時には、一国の総需要を拡大するような方策を取るべきで、そのためには、政府が積極的に財政出動を行って、民間企業に息を吹き込むのでなくてはならない。じっさい世界恐慌の時代に、アメリカは彼のこの主張に基づいた大規模な公共事業によって多くの雇用を創出したのだった。
ケインズはある状況の下で一定の法則性が成り立ったとしても、それは絶対的ではなく、別の状況下では、前提を変えなくてはならないという柔軟な態度をいつも貫いた。彼は常に、経済活動というものが特定の条件の下で行われるという現場性を重視した。ある法則を抽出するためには、多数の経済学的要素の関係を複合的に組み合わせて仮定しなくてはならない。そのことが、後から見ると彼の理論が単純な法則性に収斂せず、難解に感じられる一つの理由である。そうして、こうした柔軟な態度こそ、人間生活の現実をよく見ていた証拠なのである。
つまりケインズの「経済学」には、その学的追究のモチベーションのうちに、もともと人間学的・倫理学的な観点が盛り込まれているのである。一見、欲望追求という脱倫理的な力学のみで動いているように見える経済の世界も、単純な法則や原理に依存した「純粋理論」によって解析することはできない。どういう立場の人間が、どういう条件の下で、どういう期待を抱いて自己投企するか、経済の動きには、そうした不確定な要因がもともとはたらいている。ケインズはそのことをまず深く承認する。
しかし不確定ということは、未来が全く予測不可能だということではない。その活動因子は、私たちがよく知っている生きた人間である。ゆえに、こういう場合にはこの立場の人間はこのような行動をとるということは、ある程度までは予測可能なはずである。だから経済学は、社会心理学的な要素を不可欠とする。そうして同時に、事態が深刻となった時には、どのような解決策を講ずるべきかというモチベーションを具えていなくてはならない。
ではその対策を講ずる主体はだれか。それは、マルクスが思い描いたように、暴力革命による国家の転覆と私有財産の揚棄を実行するプロレタリアートでないとすれば、国民の生命や財産を保障する国家であり、それをリードする賢明な政府でなくてはならない。
ちなみに、マルクスもその思想の根幹には、悲惨な社会状態を克服して人類を幸福に導くためには、どのような社会構想が必要かという倫理的動機が息づいており、その点に関する限りはケインズと共通しているのである。資本主義の根本的矛盾の原因を人間労働の抽象化による資本への転化に求めたその考察は、いまなお有効である。十九世紀という時代が持っていた苛酷な条件と彼自身の激しい気性とを割り引くならば。
こうして、ケインズの経済思想は、国境を超えるグローバリズムを許すような自由放任主義を是とせず、国民全員、特に中間層が豊かさをキープするためにはどうすることがよいのかという政治倫理学と経済倫理学とを内包していた。それは個別科学のなかに孕まれた公共精神の表れなのである。
個別諸科学は、それが人間自身を対象とする限り、その根底に、倫理学的な動機と観点とを必ずひそませていなくてはならない。願わくは、これほどまでに専門分化してしまった現代の人文科学のうちに、倫理学=哲学的な思考が少しでも浸透し、それによって、統一的・総合的な「人間学」との間に有機的な関連が回復されんことを。

ところで先に、ソクラテスが若いころ自然哲学に関心をもって熱心に研究したが、自分はそれに不向きなことを知って、人間学的な方面に研究の矛先を変えたといういきさつについて記した。ソクラテス以前の哲学は宇宙万物の謎を解くことを主目的としていたが、ソクラテスは大きく舵を切って、「善とはなにか」「正義とは何か」「よく生きるとはどういうことか」という方向に哲学船の方向を変えたのである。これは哲学の主たるテーマを人間学的・倫理学的なものに求めるのと同じである。
プラトンの弟子・アリストテレスは、このソクラテスの視線変更を再び軌道修正し、哲学(学問)は両方を含んだ総合的な視野を持たなくてはならないと考えた。だから彼の考察領域は、自然学、政治学、倫理学、論理学、詩学、魂の学などあらゆる分野に及んでいる。彼は、ソクラテスの遺志を受け継いだプラトンのような魂の学への激しい情熱に比して、もっと冷静さと客観性と中庸とを重んじたのだろう。そのためにその手つきは、いかにも冷ややかで、賢くて、諸学の博物学とでも形容したくなるような雰囲気を具えている。しかしそのようにしてこそ、宇宙の問題も人間の問題も統一的に理解できるというのが、アリストテレスの密かな理念だったに違いない。そうしてこの理念こそは、今日、学問とか科学とか呼ばれている営みの基本精神を形成している(はずだった)。
さて近代科学がやってきた。それは観察と実験と現実整合性を最重要視する自然学から始まった。そうしてガリレイ、ケプラー、ニュートン、ラボアジェ、ダーウィンら超天才を生み、大成功をおさめた。やがて西洋の人々は、この大成功の果実である「普遍妥当的な法則の確立」をそのまま、あるいは若干の方法的変更を加えさえすれば、人間社会の現象や魂の問題にも適用できるのではないかと考えた。
むろんこのスライド方式によっていくつかの成果は得られたであろう。しかしその際、見落とされていたことが一つある。それは、人間社会の現象や魂の問題を扱うのに、それを扱う主体自身の存立そのものが疑われることがなかったという点である。言い換えると、学問としての客観性が保証されるために、学問主体は、彼が扱う対象からあくまで神のように超越していなければならず、したがって彼自身が人間的・倫理的な問題、つまり生の不安や生活上の迷いなどに囚われていてはならないという条件が暗黙の裡に要請された。
これは自然を対象とする場合にはそれで構わない。重力の法則や天体の法則は、ガリレイやニュートンのある日の気分や彼らの生死に関係なく成り立つからである。しかし人間が人間自身の事象を扱う場合には、この問題を等閑視することは許されない。というのは、ある主体が人間世界を観察しようとするとき、彼はまさに人間世界のただなかに、その一員として参加しつつそうするので、彼自身の精神を形づくっている具体的な文化や歴史や時代の諸傾向から無縁に学問の営みを続けることは不可能だからである。これは要するに、人間世界を対象とする諸学問は、価値の問題から自由に中立的に成立することなどありえないということを意味する。彼の駆使する「学問的言語」は、そもそもの初めからある価値観に支配されているのである。それを排除しうるなどと幻想しないほうがいい。
そのことはまた、どんな人文諸科学といえども、人間学的・倫理学的関心をその方法論のうちにあらかじめ含むべきことを要求する。つまり、ソクラテスが大きく舵を切ったあの方向性を、現代の人文諸科学は見習うべきなのである。
だが現状はどうだろうか。
前期ヴィトゲンシュタインは「語りえぬものごとについては沈黙せねばならぬ」とダンディな見栄を切ったが、この語りえぬものごととは、人間学的・倫理学的な問題のことである。これを聴いた多くの人たちは、新しい哲学(学問)のご託宣を得たように感じて、論理実証主義や分析哲学や記号論理学などの道を切り開こうとした。だが彼らの志向性そのものが深層のレベルで一つの価値意識に拘束されていたのであり、その価値意識とは、「我々は、倫理のことなど無視して、人間社会の事象を純粋に、数学的に、システマティックに学問すべきなのだ!」という選択意志である。
しかし繰り返すが、どんなに細分化された現代の個別諸科学といえども、それが人間世界そのものを対象としている限り、倫理的問題と切り離されて自立的に存立することはあり得ない。そのような脱倫理の体裁を保っている学問や理論は、まさにその脱倫理性のゆえに、必ず人間の現実から乖離した空虚な、あるいは人間の幸福に資さない有害な姿をさらすのである。
たとえば経済学という学問がある。まさしく人間社会の活動そのものを扱う学問だが、現在、この学問の主流を占めている「新古典派」は、経済活動に参加するすべての人間は、利益追求という合理的な目的に従って行動するはずだという前提から出発する。この前提は、人間の意志や行動には不確定な要素が含まれるという当然の認識を無視している。また、社会は個人意志の算術的総合ではなく、まさにそれらが合成されることによって、それ自体が独自の構造と力学を持った生き物のようになるという視点も欠落している。いずれにしてもこの前提が脱倫理的であることは明らかだろう。脱倫理的であることを担保することによって、この学派は、理論的学問の純粋性追求の地歩を獲得できたと錯覚するのである。
次に、この合理的経済人の経済的目的を最大限に達成するためには、市場の自由を最大限保証しなければならないと、この学派は考える。よってどんな社会状態になろうと、国家などの公共体の市場への介入は極力排除しなくてはならない。そうすれば、需要と供給とは自動的に均衡状態に達するので、価格は安定する。モノやサービスの供給量が決定されれば需要はそれに見合うようについてくる。前者が過剰になったり後者が過小になることは単なる一時的な現象だから、長い間には完全雇用が実現するはずだ。ゆえに非自発的な失業はあり得ない……。
しかしこのようなオートマチックな考え方は、実態とまったく合わない。企業の倒産や投資の停滞、非自発的な失業は、デフレーション、すなわち供給が過剰となってモノが売れない場合にはいくらでも見られるし、インフレーション、すなわち通貨の量が膨張するときには、バブル経済で返済不能な債務が増大し、物価の上昇に賃金の上昇が追いつかず多くの人の生活は困窮する。
こうした景気の変動現象と、それが引き起こす国民の貧困化に対して、新古典派経済学はあえてそっぽを向こうとするのである。それもそのはず、彼らにしてみれば、経済学とは「純粋な」理論学問であって、低所得者の生活の困窮やそれによる社会秩序の混乱を解決しようという社会倫理的な動機など端から持っていないからである。現実と理論とが乖離しているときには、現実のほうが間違っているのだ!
しかし、ケインズはそうではない。彼の経済学は、企業が大規模に倒産もせず、失業者が増大せず、国民がそこそこ豊かな生活を送れるようにするには、どういう考え方をすればよいかを絶えず念頭に置いている。景気の極端な変動を抑制するには、市場の自由にゆだねたのではだめで、状況に応じて国家の適切な介入が必要である。失業者が増大したり深刻な不景気が出現したり貧富の格差が極端に開いたりした時には、一国の総需要を拡大するような方策を取るべきで、そのためには、政府が積極的に財政出動を行って、民間企業に息を吹き込むのでなくてはならない。じっさい世界恐慌の時代に、アメリカは彼のこの主張に基づいた大規模な公共事業によって多くの雇用を創出したのだった。
ケインズはある状況の下で一定の法則性が成り立ったとしても、それは絶対的ではなく、別の状況下では、前提を変えなくてはならないという柔軟な態度をいつも貫いた。彼は常に、経済活動というものが特定の条件の下で行われるという現場性を重視した。ある法則を抽出するためには、多数の経済学的要素の関係を複合的に組み合わせて仮定しなくてはならない。そのことが、後から見ると彼の理論が単純な法則性に収斂せず、難解に感じられる一つの理由である。そうして、こうした柔軟な態度こそ、人間生活の現実をよく見ていた証拠なのである。
つまりケインズの「経済学」には、その学的追究のモチベーションのうちに、もともと人間学的・倫理学的な観点が盛り込まれているのである。一見、欲望追求という脱倫理的な力学のみで動いているように見える経済の世界も、単純な法則や原理に依存した「純粋理論」によって解析することはできない。どういう立場の人間が、どういう条件の下で、どういう期待を抱いて自己投企するか、経済の動きには、そうした不確定な要因がもともとはたらいている。ケインズはそのことをまず深く承認する。
しかし不確定ということは、未来が全く予測不可能だということではない。その活動因子は、私たちがよく知っている生きた人間である。ゆえに、こういう場合にはこの立場の人間はこのような行動をとるということは、ある程度までは予測可能なはずである。だから経済学は、社会心理学的な要素を不可欠とする。そうして同時に、事態が深刻となった時には、どのような解決策を講ずるべきかというモチベーションを具えていなくてはならない。
ではその対策を講ずる主体はだれか。それは、マルクスが思い描いたように、暴力革命による国家の転覆と私有財産の揚棄を実行するプロレタリアートでないとすれば、国民の生命や財産を保障する国家であり、それをリードする賢明な政府でなくてはならない。
ちなみに、マルクスもその思想の根幹には、悲惨な社会状態を克服して人類を幸福に導くためには、どのような社会構想が必要かという倫理的動機が息づいており、その点に関する限りはケインズと共通しているのである。資本主義の根本的矛盾の原因を人間労働の抽象化による資本への転化に求めたその考察は、いまなお有効である。十九世紀という時代が持っていた苛酷な条件と彼自身の激しい気性とを割り引くならば。
こうして、ケインズの経済思想は、国境を超えるグローバリズムを許すような自由放任主義を是とせず、国民全員、特に中間層が豊かさをキープするためにはどうすることがよいのかという政治倫理学と経済倫理学とを内包していた。それは個別科学のなかに孕まれた公共精神の表れなのである。
個別諸科学は、それが人間自身を対象とする限り、その根底に、倫理学的な動機と観点とを必ずひそませていなくてはならない。願わくは、これほどまでに専門分化してしまった現代の人文科学のうちに、倫理学=哲学的な思考が少しでも浸透し、それによって、統一的・総合的な「人間学」との間に有機的な関連が回復されんことを。