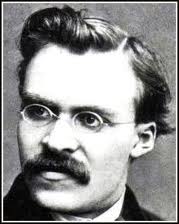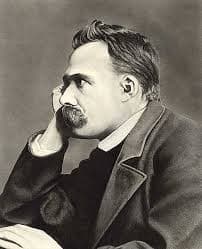ちゃぽん倫理の起源28

さて私は、道徳というものが、互いがみじめにならないように共同関係を維持しようと考えた人間が、仕方なしに編み出した方便であり世間知であり術策に他ならないことを認める。別にそれはプラトニズムの遺骨を引き取ったカントが信じたがっているように、崇高でア・プリオリな理性的精神を根拠にしているなどと思わない。しかし、そうであればこそ、かえってそうした方便や世間知や術策によって作られた「信頼」の原理が、長きにわたる生活慣習の蓄積の中で、現実により良い方向に作用するのである。どうしてそれでいけないことがあろうか。なぜ善意志は、カントが考えたように、崇高でア・プリオリでなくてはならないのか。またニーチェがこだわったように、なぜ、ある道徳原理が方便や知恵や術策にすぎないことそのもののうちに、腐臭や欺瞞や虚偽を嗅ぎつけて告発しなくてはいけないのか。
繰り返し述べてきたように、「善」とは、何か常人にはよくなしえない特別な意志や行為を指すのではなく、この現実社会が相互の信頼関係を軸としてうまく循環しているということ、日常の中で暗黙のうちに人倫精神が共有されてお互いに快適な関係が築かれているということ、そのことである。そしてこの「信頼」の原理が現実に作用して効果を発揮するのは、人間が孤立した個人存在ではなく、互いに関係しあうことをその本質としているからこそである。
この場合、主観的な意図としては自己利益だけを追求するつもりであっても、そこには互いに関係しあうことを通してそれを実現するということからくる力学的な必然がはたらく。したがって、物事がふつうに運ぶならば、その相互行為は相手の利益をおもんばからざるを得ない形でしか成り立たないのである。
物事がふつうに運ぶとは、双方に信頼関係がある程度あり、どちらかが明白な悪意をもって相手をだましてやろうとか傷つけてやろうというようなことを考えない場合である。仮にそのような悪意を一方(Aとする)が抱いている場合には、相互行為の結果として考えられるパターンは、ほぼ次の四つに絞られるだろう。
①相手(Bとする)が完全にだまされて、そのことにいつまでも気づかず(あるいは殺されてしまい)、Aは「うまいことをした」と考えて、さらにそのやり口をほかにも適用し続けようとする。
②Bが気づかない場合でも、Aは信頼を裏切ったと反省して、Bに謝罪・補償をするか、Bには打ち明けなくても、今後B、C、D…に対してそういうことをしないように慎む。
③Bがだまされたことに気づき、Aに対するなんらかの処置をとる(返済要求、契約破棄、関係断絶、告発訴訟など)。
④Bがだまされたことに気づき、Aがそんなことをするなら、自分もやってやろうと考えて、Aに復讐したり、C、D…に対しても悪意(信頼の裏切り)をもってふるまうようになる。
①の場合、多数者の相互信頼で成り立っている共同態の構造に、Aは少数者として反逆するわけだから、そのまま最後まで「悪人」として生きおおせるか、どこかで「悪事」が露見して社会的制裁を受けるかどちらかだろう。
前者の場合は、Aは、生涯たいへんな孤独を強いられることになる。それは、四六時中、剣を突きつけられている権力者ダモクレスや、不安を克服しようとするマクベスの心に似ている。孤立に耐える強い人間にしか可能でないことは確かだが、彼が生涯幸福感を維持できるかどうかは、かなり疑わしい。また後者の場合は、普通の犯罪者の例に一致するので、信頼に基づく共同態の構造そのものには致命的な傷がつかないことになる。
②の場合、Aは共同態の構造の軍門に下って、改めてそれを承認し直すことになるのだから、この場合も、信頼の構造に致命的な傷はつかない。
③の場合、Bは、「正義」として多数者に受け入れられている信頼の構造に依拠して、Aと戦うわけであるから、Bが勝つなら、信頼の構造は再確認される。Bが勝つ公算は十分高いだろう。反対にAが勝つ場合には、信頼の構造そのものが揺らいでいることが予想される(たとえば取り締まりや裁きに与かる権威筋が自己利益のためにAに加担してしまう、など)。
④の場合は、③の後者の場合よりも、さらに信頼の構造自体が破綻しつつあることを表わしている。これは、一人ひとりの精神が堕落したというよりも、現実の社会構造が、平和と秩序と繁栄を維持するための条件を失って、だれも社会を信用しなくなり、他人のことなどかまわずにエゴイズムを追求する以外生き延びる道はないと考えざるを得なくなった状態を意味している。一人ひとりの精神なぞは、現実の社会構造や歴史の蓄積しだいで気高くもなれば堕落もするのである。
以上四つの場合、いずれも、共同態の平和と秩序、すなわち人倫を支えているものが相互信頼の構造であることを示しているだろう。ただし、後に和辻哲郎について述べるように、単に「信頼」という概念に無条件に依拠しただけでは、人倫精神の維持・必要を解明したことにはならない。
とまれ、平和と秩序と繁栄とが日常的に保たれている状態こそは、「善」の実現なのである。いくら形而上学的なレベルで、理性的存在は最高善を目指すべきだとか、奴隷道徳の代わりに貴族道徳を置き換えよ、などと説いても、崇高な道徳が実現されるわけではない。
功利主義的な原理をともに軽蔑したカントもニーチェも、どうしてもこのことがわからなかったようだ。前者は「善」と「快」を対立命題であると固執し、後者は「優」と「善」とを妥協不可能な二項選択命題と考えていたからである。
ここには、一見、道徳への態度において反対であるかのようにみえる二人が、ある意味で頑固な共通点をもっていることがうかがわれる。それが、徹底性・原理性(極端と言い換えても同じだが)を追求せずにはいられないドイツ文化の特徴であること、そしてそれは、そのすさまじい迫力と同時に、大きな問題点もはらんでいることが、文化圏の異なるこちらからはよく見えるのである。
倫理学的な観点からの、カントとニーチェの相違点と共通点とを簡単に確認しておこう。
相違点は、カントが徳福二元論に固執したのに対し、ニーチェは貴賤二元論に固執したこと。カントは道徳的な善と個人の幸福や快楽とが絶対的に矛盾すると考え、この図式以外には、「よい」という概念を満たすものはないと考えた。彼の選択は当然、前者を優先すべしとはじめから決まっていたのである。しかしこれは、常識的な人間理解を著しく逸脱した捉え方である。
そこにニーチェが、「よい」の本来の意義は「優」「強」ということであるという鋭いアンチテーゼを持ち込んだ。これを堂々と認めることは、あのカリクレスが果たしたように、この世の現実を曇りなく見つめるという強力な視線変更をもたらした。じっさい、「よい」という言葉の本来の意義のなかには、ニーチェの指摘するような要素が不可欠のものとして含まれていることは事実である。
しかしニーチェはニーチェで、既成道徳を批判したいあまりに、貴賤二元論にこだわりすぎたと言えよう。というよりも、徳福二元論と貴賤二元論とが単純に反対命題であり、両者は互いに全く相いれないという論理に固執し続けたのだ。だから彼は、高貴な者、強い者は世俗的な道徳を気にしないし、生の苦悩を進んで引き受けるものだと考え、個人的な幸福やささやかな満足、またそれを支える大多数の「善人」に対してはあらわな軽蔑を示した。だが一方で彼は、人々を陶酔に誘う芸術の美的快楽、健康でおおらかに自分の力を現実の中に伸ばしていこうとする傾向を積極的に肯定しようともした。僧侶的、禁欲的な道徳理想の病理を覆すためにである。
このように、ニーチェは、奴隷道徳への嫌悪から主人道徳の支配を求める一方で、弱者救済の手段としての「あの世における勝利と幸福」という宗教的な空手形や慰藉や麻酔剤を否定する。現世における生そのもの、そのもっとも高められた表現としての芸術、文化を丸ごと肯定したいという欲求を強く押し出すのである。現実にこの二つの願いを果たそうとすれば、どうしても自己分裂の危機を免れがたいことになる。
というのは、芸術や文化の価値は、最終的には現世を生きる多数者、日常的な生を日々実践している多数者の感性によって承認されるのであり(より高い文化的価値も、その「高い」ということを承認するのは多数者である)、こちらを選ぶなら、その同じ多数者が従っている通俗道徳観を我慢して受け入れざるを得ないからである。通俗道徳を根底から否定しながら、同時に芸術が真に根付く土壌であるこの現世を肯定するというのは虫のいい話だ。
また彼は、僧侶的な禁欲主義や同情・受苦・共感のポーズをせせら笑う一方で、人が引き受けない苦悩を積極的に背負うことを来るべき超人の条件としてヒロイックに追求した。こうした自己分裂を極度に誠実に生きたために、彼は、結局、現世否定の象徴として選ばれたたったひとりの「十字架に架けられし者」のほうに自らを重ね合わせざるを得なかったのである。
つまりニーチェは、価値の問題を考える際に、道徳、芸術いずれの方面においても、徹底性、原理性を極端に強調せずにはいられない体質の持ち主だった。かくてその論述はいつも矛盾を内包する結果になったのだ。
だがまさにこの徹底性、原理性への固執という点で、倫理問題に関しては、じつはカントのそれと意外にも共通しているのである。なぜなら、二人とも、道徳の原理をそのつどの功利、幸福、快の満足、普通の「善」や「徳」の実現など、俗世間的なものに求めることを激しく否定し、何かそれらを超えた最高の道徳的価値が存在するはずだという観念に頼りつつ、たとえばイギリス流功利主義(カントの場合はベンサム、ニーチェの場合はJ・S・ミル)を頭から軽蔑していたからである。
ところで、『道徳の系譜』に、次のような気にかかる一節がある。
――「だが、なんだってまだあなたは、より高貴な理想のことなどを話すのです! われわれは事実に従おうではないですか。要するに民衆が勝ったのです、――これをあるいは〈奴隷〉がとでも、〈〉がとでも、〈畜群〉がとでも、その他どう呼ぼうとあなたの勝手ですが、――そしてこれがユダヤ人によって起こったことだとするなら、それもいいでしょう! ともあれ、彼ら以上に世界史的な使命(「ミッション」とルビあり)をもった民族というものはなかったのです。〈主人〉は片づけられてしまい、平民の道徳が勝ったのです。この勝利を同時に、血に毒を注いだものと見る人もいるでしょう(この勝利によって人種の混淆が起こったからです)、――私はこれを否認はしません。しかし、この毒の注入が成功したというのは疑いない事実なのです。人類の(つまりそれの〈主人〉からの)〈解放〉は、きわめて順調にいっています。すべては目に見えてユダヤ化し、キリスト教化し、あるいは化しつつあります(言葉などはどうでもよいのです!)この毒が人類の全身をすみずみまで侵してゆく成り行きは止めがたいものにみえるし、のみならずそのテンポと足取りは今後いよいよ緩やかに、こまやかに、ひそやかに、慎重になるものとおもわれます――時間はたっぷりあるわけですから・・・。(中略)教会がなかったとしたら、われわれの誰が自由精神などになるものでしょうか? われわれに胸くそ悪いのは教会であって、その毒ではありません・・・。教会を度外視すれば、われわれにしてもあの毒は好きなのです・・・。」――これが、私の話にたいし一人の〈自由精神〉がつけ加えたエピローグ、自らとくとその正体を示したとおりのれっきとした人物で、そのうえ民主主義者でもある一人の人物がつけ加えたエピローグであった。彼はそれまでの私の話に聞き入っていたが、私が黙ってしまったのを見て堪えられなくなったのである。それというのも、私には、ここで言わずに黙っているべきことが多々あったからなのだ――(第一論文第9節)
この「一人の人物」としてイメージされているのは、キリスト教を母胎として生まれた近代精神の開花が、じっさいに多くの個人に現世的な幸福と解放の実感を与えたその成果をただ頭だけで否定しても意味がないではないか、という立場に立つ人たち、啓蒙主義者、社会改良家、自由主義者、進歩主義者、政治的民主主義者、自然科学者、さらには、無神論者、革命家などをも含む、近代精神の持ち主であろう。事実、この人の言うとおり、「この毒が人類の全身をすみずみまで侵してゆく成り行きは止めがたいものにみえる」し、近代精神は、いろいろな暗部を抱えながらも、おおむね伝統社会が解決できなかった問題を解決し勝利したのである。いまもその趨勢は引き継がれつつある。ニーチェの貴族趣味的な別の「毒」をいくら対置したところで、この流れを変えることはできない。ニーチェ自身の冷静な自覚がよく出ているくだりである。
しかし気になるのは、それに対する「私」の述懐である。「私には、ここで言わずに黙っているべきことが多々あったからなのだ」とある。「言わずに黙っているべきことが多々あった」というときの「黙っているべきこと」とはいったい何だろうか。たいへん気をもたせる思わせぶりな言い方だが、期待してその後を読んでいっても、一向にそれに言及する気配が現われない。
ニーチェの思想に従うなら、キリスト教を母胎としつつ、その鬼っ子として生まれてきた客観主義的な近代精神もまた、「力への意志」の一形態ということになるはずである。したがって、それが私たちの生活の合理的な面を現実的に支え、政治も学問も経済活動もそのスタイルを主流として進行するのであってみれば、この箇所で異議を唱えている「一人の〈自由精神〉」の言い分は、おおむね妥当なものとして認めざるを得ないだろう。
ただし、私たちの生を全体として見渡すとき、たしかにこうした近代精神の勝利と支配をただ肯定するだけでは片づかない。
ことを政治の領域に限ってみても、いわゆる民主主義(デモクラシー、民衆自身による民衆の統治)がイデオロギーとして過剰に走ると、観念的な平等主義、直接民主制などの空想的な理念、節度を忘れた過激な革命思想、そのあとにやってくる恐怖政治や悪しき独裁政治などに帰結しやすいことは、歴史が十分すぎるほど証明している。
また、近代合理精神は、人間の実存を扱う文学の領域、人々を陶酔や躍動に誘う芸術美の領域などがもっている秘密の核心には、ほとんど介入できない。せいぜい、それらの領域における創造的営みや鑑賞者の共感などについて、その構造や由来を解釈できるだけである。
しかし、それにもかかわらず、近代合理精神は、この現世を生老病死の輪廻として絶望的にとらえていた宗教的な世界観、現世の彼岸に救済の王国を空想するほかなかった世界観に半ば打ち克ったのであり、多くの人々の生を現実的に救い、彼らに力と希望を与えたのである。ニーチェのように、畜群のために選良があるのではなく選良のために畜群があるのだとか、人間は超えられるためにあるのだなどと言ってみても、そうではない仕方で「力への意志」が動いてきたのであれば、その流れをだれも否定することはできない。
国際社会では、いまや遅れて出発したどの国々も、この近代化という目標に向かって建設の槌音を高々と響かせている。むろんそれは激しい競争の世界なので悲惨な衝突の条件をはじめから抱えている。しかし、それならそれで、ニーチェ自身の弱肉強食的な「力への意志」の宇宙原理にもかなうはずである。彼は、こうした事実に対して、もったいぶらずに誠実に応答すべきであったろう。
*次回よりJ・S・ミルを論じます。

さて私は、道徳というものが、互いがみじめにならないように共同関係を維持しようと考えた人間が、仕方なしに編み出した方便であり世間知であり術策に他ならないことを認める。別にそれはプラトニズムの遺骨を引き取ったカントが信じたがっているように、崇高でア・プリオリな理性的精神を根拠にしているなどと思わない。しかし、そうであればこそ、かえってそうした方便や世間知や術策によって作られた「信頼」の原理が、長きにわたる生活慣習の蓄積の中で、現実により良い方向に作用するのである。どうしてそれでいけないことがあろうか。なぜ善意志は、カントが考えたように、崇高でア・プリオリでなくてはならないのか。またニーチェがこだわったように、なぜ、ある道徳原理が方便や知恵や術策にすぎないことそのもののうちに、腐臭や欺瞞や虚偽を嗅ぎつけて告発しなくてはいけないのか。
繰り返し述べてきたように、「善」とは、何か常人にはよくなしえない特別な意志や行為を指すのではなく、この現実社会が相互の信頼関係を軸としてうまく循環しているということ、日常の中で暗黙のうちに人倫精神が共有されてお互いに快適な関係が築かれているということ、そのことである。そしてこの「信頼」の原理が現実に作用して効果を発揮するのは、人間が孤立した個人存在ではなく、互いに関係しあうことをその本質としているからこそである。
この場合、主観的な意図としては自己利益だけを追求するつもりであっても、そこには互いに関係しあうことを通してそれを実現するということからくる力学的な必然がはたらく。したがって、物事がふつうに運ぶならば、その相互行為は相手の利益をおもんばからざるを得ない形でしか成り立たないのである。
物事がふつうに運ぶとは、双方に信頼関係がある程度あり、どちらかが明白な悪意をもって相手をだましてやろうとか傷つけてやろうというようなことを考えない場合である。仮にそのような悪意を一方(Aとする)が抱いている場合には、相互行為の結果として考えられるパターンは、ほぼ次の四つに絞られるだろう。
①相手(Bとする)が完全にだまされて、そのことにいつまでも気づかず(あるいは殺されてしまい)、Aは「うまいことをした」と考えて、さらにそのやり口をほかにも適用し続けようとする。
②Bが気づかない場合でも、Aは信頼を裏切ったと反省して、Bに謝罪・補償をするか、Bには打ち明けなくても、今後B、C、D…に対してそういうことをしないように慎む。
③Bがだまされたことに気づき、Aに対するなんらかの処置をとる(返済要求、契約破棄、関係断絶、告発訴訟など)。
④Bがだまされたことに気づき、Aがそんなことをするなら、自分もやってやろうと考えて、Aに復讐したり、C、D…に対しても悪意(信頼の裏切り)をもってふるまうようになる。
①の場合、多数者の相互信頼で成り立っている共同態の構造に、Aは少数者として反逆するわけだから、そのまま最後まで「悪人」として生きおおせるか、どこかで「悪事」が露見して社会的制裁を受けるかどちらかだろう。
前者の場合は、Aは、生涯たいへんな孤独を強いられることになる。それは、四六時中、剣を突きつけられている権力者ダモクレスや、不安を克服しようとするマクベスの心に似ている。孤立に耐える強い人間にしか可能でないことは確かだが、彼が生涯幸福感を維持できるかどうかは、かなり疑わしい。また後者の場合は、普通の犯罪者の例に一致するので、信頼に基づく共同態の構造そのものには致命的な傷がつかないことになる。
②の場合、Aは共同態の構造の軍門に下って、改めてそれを承認し直すことになるのだから、この場合も、信頼の構造に致命的な傷はつかない。
③の場合、Bは、「正義」として多数者に受け入れられている信頼の構造に依拠して、Aと戦うわけであるから、Bが勝つなら、信頼の構造は再確認される。Bが勝つ公算は十分高いだろう。反対にAが勝つ場合には、信頼の構造そのものが揺らいでいることが予想される(たとえば取り締まりや裁きに与かる権威筋が自己利益のためにAに加担してしまう、など)。
④の場合は、③の後者の場合よりも、さらに信頼の構造自体が破綻しつつあることを表わしている。これは、一人ひとりの精神が堕落したというよりも、現実の社会構造が、平和と秩序と繁栄を維持するための条件を失って、だれも社会を信用しなくなり、他人のことなどかまわずにエゴイズムを追求する以外生き延びる道はないと考えざるを得なくなった状態を意味している。一人ひとりの精神なぞは、現実の社会構造や歴史の蓄積しだいで気高くもなれば堕落もするのである。
以上四つの場合、いずれも、共同態の平和と秩序、すなわち人倫を支えているものが相互信頼の構造であることを示しているだろう。ただし、後に和辻哲郎について述べるように、単に「信頼」という概念に無条件に依拠しただけでは、人倫精神の維持・必要を解明したことにはならない。
とまれ、平和と秩序と繁栄とが日常的に保たれている状態こそは、「善」の実現なのである。いくら形而上学的なレベルで、理性的存在は最高善を目指すべきだとか、奴隷道徳の代わりに貴族道徳を置き換えよ、などと説いても、崇高な道徳が実現されるわけではない。
功利主義的な原理をともに軽蔑したカントもニーチェも、どうしてもこのことがわからなかったようだ。前者は「善」と「快」を対立命題であると固執し、後者は「優」と「善」とを妥協不可能な二項選択命題と考えていたからである。
ここには、一見、道徳への態度において反対であるかのようにみえる二人が、ある意味で頑固な共通点をもっていることがうかがわれる。それが、徹底性・原理性(極端と言い換えても同じだが)を追求せずにはいられないドイツ文化の特徴であること、そしてそれは、そのすさまじい迫力と同時に、大きな問題点もはらんでいることが、文化圏の異なるこちらからはよく見えるのである。
倫理学的な観点からの、カントとニーチェの相違点と共通点とを簡単に確認しておこう。
相違点は、カントが徳福二元論に固執したのに対し、ニーチェは貴賤二元論に固執したこと。カントは道徳的な善と個人の幸福や快楽とが絶対的に矛盾すると考え、この図式以外には、「よい」という概念を満たすものはないと考えた。彼の選択は当然、前者を優先すべしとはじめから決まっていたのである。しかしこれは、常識的な人間理解を著しく逸脱した捉え方である。
そこにニーチェが、「よい」の本来の意義は「優」「強」ということであるという鋭いアンチテーゼを持ち込んだ。これを堂々と認めることは、あのカリクレスが果たしたように、この世の現実を曇りなく見つめるという強力な視線変更をもたらした。じっさい、「よい」という言葉の本来の意義のなかには、ニーチェの指摘するような要素が不可欠のものとして含まれていることは事実である。
しかしニーチェはニーチェで、既成道徳を批判したいあまりに、貴賤二元論にこだわりすぎたと言えよう。というよりも、徳福二元論と貴賤二元論とが単純に反対命題であり、両者は互いに全く相いれないという論理に固執し続けたのだ。だから彼は、高貴な者、強い者は世俗的な道徳を気にしないし、生の苦悩を進んで引き受けるものだと考え、個人的な幸福やささやかな満足、またそれを支える大多数の「善人」に対してはあらわな軽蔑を示した。だが一方で彼は、人々を陶酔に誘う芸術の美的快楽、健康でおおらかに自分の力を現実の中に伸ばしていこうとする傾向を積極的に肯定しようともした。僧侶的、禁欲的な道徳理想の病理を覆すためにである。
このように、ニーチェは、奴隷道徳への嫌悪から主人道徳の支配を求める一方で、弱者救済の手段としての「あの世における勝利と幸福」という宗教的な空手形や慰藉や麻酔剤を否定する。現世における生そのもの、そのもっとも高められた表現としての芸術、文化を丸ごと肯定したいという欲求を強く押し出すのである。現実にこの二つの願いを果たそうとすれば、どうしても自己分裂の危機を免れがたいことになる。
というのは、芸術や文化の価値は、最終的には現世を生きる多数者、日常的な生を日々実践している多数者の感性によって承認されるのであり(より高い文化的価値も、その「高い」ということを承認するのは多数者である)、こちらを選ぶなら、その同じ多数者が従っている通俗道徳観を我慢して受け入れざるを得ないからである。通俗道徳を根底から否定しながら、同時に芸術が真に根付く土壌であるこの現世を肯定するというのは虫のいい話だ。
また彼は、僧侶的な禁欲主義や同情・受苦・共感のポーズをせせら笑う一方で、人が引き受けない苦悩を積極的に背負うことを来るべき超人の条件としてヒロイックに追求した。こうした自己分裂を極度に誠実に生きたために、彼は、結局、現世否定の象徴として選ばれたたったひとりの「十字架に架けられし者」のほうに自らを重ね合わせざるを得なかったのである。
つまりニーチェは、価値の問題を考える際に、道徳、芸術いずれの方面においても、徹底性、原理性を極端に強調せずにはいられない体質の持ち主だった。かくてその論述はいつも矛盾を内包する結果になったのだ。
だがまさにこの徹底性、原理性への固執という点で、倫理問題に関しては、じつはカントのそれと意外にも共通しているのである。なぜなら、二人とも、道徳の原理をそのつどの功利、幸福、快の満足、普通の「善」や「徳」の実現など、俗世間的なものに求めることを激しく否定し、何かそれらを超えた最高の道徳的価値が存在するはずだという観念に頼りつつ、たとえばイギリス流功利主義(カントの場合はベンサム、ニーチェの場合はJ・S・ミル)を頭から軽蔑していたからである。
ところで、『道徳の系譜』に、次のような気にかかる一節がある。
――「だが、なんだってまだあなたは、より高貴な理想のことなどを話すのです! われわれは事実に従おうではないですか。要するに民衆が勝ったのです、――これをあるいは〈奴隷〉がとでも、〈〉がとでも、〈畜群〉がとでも、その他どう呼ぼうとあなたの勝手ですが、――そしてこれがユダヤ人によって起こったことだとするなら、それもいいでしょう! ともあれ、彼ら以上に世界史的な使命(「ミッション」とルビあり)をもった民族というものはなかったのです。〈主人〉は片づけられてしまい、平民の道徳が勝ったのです。この勝利を同時に、血に毒を注いだものと見る人もいるでしょう(この勝利によって人種の混淆が起こったからです)、――私はこれを否認はしません。しかし、この毒の注入が成功したというのは疑いない事実なのです。人類の(つまりそれの〈主人〉からの)〈解放〉は、きわめて順調にいっています。すべては目に見えてユダヤ化し、キリスト教化し、あるいは化しつつあります(言葉などはどうでもよいのです!)この毒が人類の全身をすみずみまで侵してゆく成り行きは止めがたいものにみえるし、のみならずそのテンポと足取りは今後いよいよ緩やかに、こまやかに、ひそやかに、慎重になるものとおもわれます――時間はたっぷりあるわけですから・・・。(中略)教会がなかったとしたら、われわれの誰が自由精神などになるものでしょうか? われわれに胸くそ悪いのは教会であって、その毒ではありません・・・。教会を度外視すれば、われわれにしてもあの毒は好きなのです・・・。」――これが、私の話にたいし一人の〈自由精神〉がつけ加えたエピローグ、自らとくとその正体を示したとおりのれっきとした人物で、そのうえ民主主義者でもある一人の人物がつけ加えたエピローグであった。彼はそれまでの私の話に聞き入っていたが、私が黙ってしまったのを見て堪えられなくなったのである。それというのも、私には、ここで言わずに黙っているべきことが多々あったからなのだ――(第一論文第9節)
この「一人の人物」としてイメージされているのは、キリスト教を母胎として生まれた近代精神の開花が、じっさいに多くの個人に現世的な幸福と解放の実感を与えたその成果をただ頭だけで否定しても意味がないではないか、という立場に立つ人たち、啓蒙主義者、社会改良家、自由主義者、進歩主義者、政治的民主主義者、自然科学者、さらには、無神論者、革命家などをも含む、近代精神の持ち主であろう。事実、この人の言うとおり、「この毒が人類の全身をすみずみまで侵してゆく成り行きは止めがたいものにみえる」し、近代精神は、いろいろな暗部を抱えながらも、おおむね伝統社会が解決できなかった問題を解決し勝利したのである。いまもその趨勢は引き継がれつつある。ニーチェの貴族趣味的な別の「毒」をいくら対置したところで、この流れを変えることはできない。ニーチェ自身の冷静な自覚がよく出ているくだりである。
しかし気になるのは、それに対する「私」の述懐である。「私には、ここで言わずに黙っているべきことが多々あったからなのだ」とある。「言わずに黙っているべきことが多々あった」というときの「黙っているべきこと」とはいったい何だろうか。たいへん気をもたせる思わせぶりな言い方だが、期待してその後を読んでいっても、一向にそれに言及する気配が現われない。
ニーチェの思想に従うなら、キリスト教を母胎としつつ、その鬼っ子として生まれてきた客観主義的な近代精神もまた、「力への意志」の一形態ということになるはずである。したがって、それが私たちの生活の合理的な面を現実的に支え、政治も学問も経済活動もそのスタイルを主流として進行するのであってみれば、この箇所で異議を唱えている「一人の〈自由精神〉」の言い分は、おおむね妥当なものとして認めざるを得ないだろう。
ただし、私たちの生を全体として見渡すとき、たしかにこうした近代精神の勝利と支配をただ肯定するだけでは片づかない。
ことを政治の領域に限ってみても、いわゆる民主主義(デモクラシー、民衆自身による民衆の統治)がイデオロギーとして過剰に走ると、観念的な平等主義、直接民主制などの空想的な理念、節度を忘れた過激な革命思想、そのあとにやってくる恐怖政治や悪しき独裁政治などに帰結しやすいことは、歴史が十分すぎるほど証明している。
また、近代合理精神は、人間の実存を扱う文学の領域、人々を陶酔や躍動に誘う芸術美の領域などがもっている秘密の核心には、ほとんど介入できない。せいぜい、それらの領域における創造的営みや鑑賞者の共感などについて、その構造や由来を解釈できるだけである。
しかし、それにもかかわらず、近代合理精神は、この現世を生老病死の輪廻として絶望的にとらえていた宗教的な世界観、現世の彼岸に救済の王国を空想するほかなかった世界観に半ば打ち克ったのであり、多くの人々の生を現実的に救い、彼らに力と希望を与えたのである。ニーチェのように、畜群のために選良があるのではなく選良のために畜群があるのだとか、人間は超えられるためにあるのだなどと言ってみても、そうではない仕方で「力への意志」が動いてきたのであれば、その流れをだれも否定することはできない。
国際社会では、いまや遅れて出発したどの国々も、この近代化という目標に向かって建設の槌音を高々と響かせている。むろんそれは激しい競争の世界なので悲惨な衝突の条件をはじめから抱えている。しかし、それならそれで、ニーチェ自身の弱肉強食的な「力への意志」の宇宙原理にもかなうはずである。彼は、こうした事実に対して、もったいぶらずに誠実に応答すべきであったろう。
*次回よりJ・S・ミルを論じます。