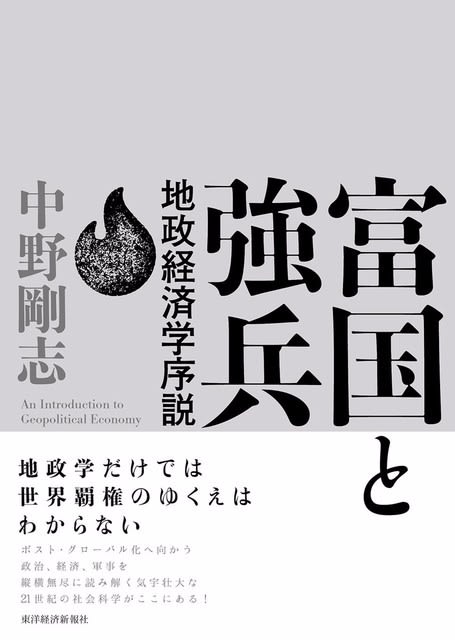次に『脳死』(一九八六年)『脳死再論』(一九八八年)『脳死臨調批判』(一九九二年)。
脳死に関する議論は、厚生省が八五年に脳死の判定基準〈竹内基準〉を公表してから、九九年に「法的脳死判定マニュアル」を発表するまでの一五年間にわたって続きました。このうち前半の八年間、立花氏は精力的にこの問題に精力的に取り組み、右の三冊を発表します。
その主旨は、脳死を人の死と認めることに反対するというものですが、なぜ反対するのか、その理由に対して筆者は大きな疑問を持ちました。その理由とは、竹内基準(瞳孔散大と対光反射喪失、自発呼吸停止、心停止)は機能死を意味しており、これだけではまだ生き残っている可能性があるから、細胞の壊死、つまり器質死を確かめるもっと精密なテストを二つ追加すべきだというのです。
立花氏はこれを訴えるために、四百字詰め原稿用紙にしてじつに二千枚を超える右の三作を著します。この膨大な枚数を費やして、反「脳死=人間死}論を展開するのですが、不思議なことに、二つのテストを追加せよという以外には、人間の死とは何かといった本質的な考察はどこにも見当たりません。しつこくしつこく二つのテストを追加せよと繰り返すのみです。
それはちょうど、田中角栄を論ずるのに、その政治家としての力量や政策のよしあしにはまったく目を配らず、ひたすら派手な金の出入りだけを問題視するのによく似ています。
筆者は、もともと「脳死=人間死」の議論に反対でした。ですから、医療のレベルでテストをより厳密にすることに異存はありません。しかし問題はその理由です。
当時、脳死をめぐる議論の中心は、医学的に「死」と認められたからといって、それをもってただちに人間の死としてよいのかという高度に倫理学的・哲学的なレベルにありました。これはもちろん、臓器移植技術の発達によって、移植医からの要請が高まり、どういう形で人間の死を規定したらよいのかという、これまでなかった問題が発生したからです。ところが立花氏は、こうした問題に少しも興味を示していないのです。
筆者の考えはこうでした。
テストの厳密化はテクニカルなレベルでやるに越したことはないが、そこに議論の中心を持ってくるのはおかしい。人間の死とは、共同関係の崩壊あるいは変容であって、当人を取り巻く親密な共同性のメンバーの同意なくしてある個人を死んだものとみなすのは誤りである。だからこそ人は路傍の死体の身元引受人を探すのだし、家族や親族の間で誰かが死ねば、必ず手厚く葬るのである。葬送はその人の死によって共同性が変容しつつあることを遺族が承認する手続きとして不可欠であり、人倫の基本をなすものである。もし立花氏の主張するように、医学的テストの厳密化だけを議論の中心にすると、裏を返せば、そこだけ厳密化すればあとは家族・親族が認めようが認めまいがどうでもよいという論理を導きかねない。
この違いを感じてから、ひょっとしてこの人(立花氏)は、人間というものをただの生物個体としてしかとらえていないのではないかと思うようになりました。もしそうだとすると、それは極めて通俗的・非哲学的な人間観の持ち主だということを意味します。
やがてこの推測は的中します。
立花氏は『脳死臨調批判』を刊行してからなぜかぷつりとこの問題について論じなくなり(議論はずっと続いていたのに)、臨死体験やインターネットや宇宙やオウム事件へとその関心を移していくのですが、臓器移植法が成立した九八年から一年後の九九年、何の迷いもなくドナーカードに署名します。脳死と判定された場合でも、心停止の場合でもすべての臓器を提供する意思がある、と。
「え? 立花さん、それはおかしくないですか?」とだれもが思いました。しかし、よく考えてみるとこれはおかしくないのです。
というのは、彼はこの疑問に答えて、ぼくはなぜドナーカードに署名したか」という論文を書き、その中で、「『脳死は人の死ではない』論の多くは、死の本質と死に付随して起こるアクシデンタルなできごと(状況)の混同の上に立論されている」と述べ、また、「生死の問題はその人自身の生死の問題でしかなく、他者の心の中にある私という存在は、私にとってはヴァーチャルな存在でしかない」とまことにあっさりと述べているからです。
この捉え方は、哲学めかしていますが、要するに「あなたはあなた、私は私」という身体の個別性にもとづいた通俗的な個体主義にほかなりません。
こうした個体主義は、わかりやすいので巷に蔓延していますが、少し哲学的に考えていくと、「どのようにして私は他者を私と同じ人間存在として認めるのか」とか、「別々の個体なのに、示し合わせもせずに感覚や感情において共感が成り立つのはなぜか」といった疑問に答えることができないことに気づきます。
答えられなくても別に生きていくのに困りませんが、問題は、立花氏が「死の本質」などといかめしい言葉を使いながら、その素朴個体主義に何の懐疑も抱いていないことです。そこがまさに彼の哲学的センスのなさなのです。
立花氏は、東大仏文科で唯心論者のメーヌ・ド・ビランについて卒論を欠き、卒業後文芸春秋に入社してから二年後に再び東大文学部哲学科に学士入学しているのですが、この哲学研究の経験はいったい何だったのでしょうか。
ほどなくこの素朴個体主義にもとづく人間観、生命観は、もっと過激な形で現れます。彼は臓器移植問題に早々と見切りをつけ、ティッシュ・エンジニアリング(遺体をバラバラに解体し、組織断片を生きた人間の身体の欠損部に埋め込む再生医療技術)に異様な興味を抱きます。ロシアやアメリカの再生医療工場を見学して感動し、この新しい技術を手放しで礼讃するのです。
理屈は、エコロジーから借りてきます。いまや人間も野生動物と同じ生命連鎖を人工的に作り出すことができるようになったのだ、と(『人体再生』二〇〇〇年)。
これは立花氏が、人間身体のすべてをパーツの組み立てによって構成できるとする科学万能主義のイデオロギーに何の疑いもなくハマってしまったことを意味しています。この発想が優生思想と紙一重なのだということ、その脱倫理性に彼は気づいてもいません。
やがてこの発想は、遺伝子組み換え食品に対する無条件な礼讃にもつながっていきます。これについては、先の『嘘八百』のなかで、粥川準二氏が、その誤りや危険性について周到に説いています)。まさに昨今問題となってきた、TPPや農協改革法などによるグローバリズムの国家侵略とかかわってきますね。
科学技術の発展に対して何の疑いも抱かないこのナイーヴな受容は、彼の知性の質が基本的に普通の人以下の幼稚なものだということを示しています。
人間の身体も機械と同じように単なるパーツの組み合わせだというのは、デカルトを連想させますが、ではデカルトが悩んだような、そしてその説明に失敗したような、「こころ」「魂」「精神」と身体とのつながりはどうなっているのだという疑問に対しては、立花氏はどう考えたのでしょうか。これについては、『臨死体験』(一九九四年)が、その恰好の材料となるでしょう。
そこで最後に『臨死体験』。
この本は、死の間近まで行きながら蘇生してきた人たちが証言する「体験」の事例をおびただしく集め、それに解釈を加える研究者やニューエイジの信奉者などの発言を加えて、その「体験」の客観的真偽を確かめようとした本です。これまた九百ページ超。
立花氏のこの領域への「浮気」は、明らかに当時の新々宗教ブームに関係があります。もともと素朴実在論者であるはずの彼が、周囲の文化的趨勢に押されて、よし、このスピリチュアルな領域も踏破してやると考えたのがおそらく本音でしょう。
そもそも多くのインテリたちまでも巻き込んで、やがてオウム事件(一九九五年)という悲惨な結末へと至る新々宗教ブームはどうして起きたのか。
筆者の考えでは、これは日本の豊かな近代化の完成と関係があります。バブル時代を経て一億総中流が唱えられましたが、それは同時に、人々を浮かれ騒ぎへと誘う「退屈な日常」を提供するものでもありました。
日本人の長年の憧れであった豊かな近代都市社会。憧れが実現してそれが日常化してみると、それは強力な個人化の流れのなかを泳ぐことでもあり、自我意識の空虚と孤独感をかき立てる光景でもありました。
こういう時、人々はきっちりと枠づけられた合理的な物質生活では得られない(と感じる)何か別の世界、スピリチュアル、霊的なもの、神秘的な経験といった、贅沢な境位を空しく求めます。この世界を超越したもっと「真実」な世界がどこかにあるのではないか?
この時期、栗本慎一郎氏や中沢新一氏など、いささかエキセントリックなインテリたちが一様にこの文化的空気に巻き込まれ、また自らその空気をリードしたのでした。足元ではすでにバブルがはじけ、以後長く続く不景気の波が押し寄せていたのですが、とかく個々人の意識はマクロ経済に無頓着です。九〇年代は足元の危機とバブル期以来の超日常感覚の残存とのタイムラグが歴然と現れた十年でした。
素朴実在論者であるはずの立花氏も例外ではありませんでした。彼もまた時代の空気には逆らえず、スピリチュアルな領域に関心を抱き、日ごろの信条を、臨死体験や超常現象の解明(?)という試練にかけようとしたのです。
彼のこの領域への挿入武器は、たったひとつ、臨死体験は「現実体験」なのか、それとも夢や幻覚と同じ「脳内現象」なのかという二元論的な問いにこだわることでした。
ただし立花氏の名誉のためにことわっておくと、この本では、膨大な告白例やインタビューの記載に対してけっして軽信に陥ってはいず、かなり慎重な態度を崩していません。それでも最終的に自ら立てたこの二元論的問いの枠組みを崩さず、結論として、自分としては「脳内現象」のほうに傾くが、「現実体験」である可能性も完全には否定しきれないというところに落ち着いています。
さて筆者の私見ですが、この二元論的問いの立て方そのものが非哲学的であり、言葉の使い方からして不正確です。そもそも脳内現象とは、ある人の脳の内部を観察・観測している他者の視点にとってのみ把握可能なものです。それは、ニューロンとニューロンとの複雑な電気化学的やりとりのことであり、それ以上のものではありません。
何かを知覚・認識している本人にとって、あるヴィジョンなり心的体験なりは、どんな形を取ろうと、それ自体としては「脳内現象」ではないのです。私たちはただ、視点を自分自身と他者とに二重化させることによってはじめて、「脳内現象」と「体験」とが並行現象であることを知ることができるだけです。
ところで夢や幻覚は、脳内現象がどんな形を取っていようと、明瞭な「体験」なのであって、現実と異なるのは、それらが必ず「醒める」ものであり、またまれにいつまでも醒めない場合にはけっして他者に承認されないという本質的な特性を持っているという点です。
現実は逆にけっして醒めることがなく、また必ず他者の承認を得られる可能性のうちにあります。これ以外に夢や幻覚と現実とをわけ隔てる条件はありません。翻って私たちが現実と呼んでいるものは、脳内現象を伴わなければ知覚不能であり、不能であれば現実として認識できないこともまた自明です。
立花氏の二元論的な問題の立て方は、初めから間違っています。
なぜ間違えたのか。それは、主観とは無縁に客観的現実なるものが厳然として存在し、それに適合しないものは「体験」とは呼べないという俗流唯物論に拘束されているからです。
彼はただこう問うべきでした――臨死体験は人が限界状況に置かれたときのヴィジョンなのか、それとも彼岸の客観的存在を証拠立てる入り口なのか、と。そして答えはもちろん前者です。
ここでは詳しく述べませんが、臨死体験のようなことは(いわゆる「幽体離脱」なども含めて)、特に何か別世界の存在を暗示するような神秘体験として扱うに値しない、十分に起こりうる自然な心的現象です。
わが国では川や橋やお花畑や亡くなった近親者が出てくる例が多いようですが、これは、私たち一人ひとりが共同性を背負った歴史的存在だからです。一部の人々はそうした共同幻想への感応力が強く、生活環境と有機的に結びついた物語性に深く染められた生き方をしています。それは別に不思議なことではありません。
立花氏はその後、「こちらの世界」に引き返したようで、今度は持ち前の「科学少年」的な情熱を、宇宙、現代物理学、遺伝子工学などに差し向けるのですが、もう深追いはしますまい。『嘘八百』には、立花氏は現代物理学の基礎もわかっていないという故佐藤進京都大学名誉教授の痛烈な指摘があります。
かくして、立花隆という人を一言で言い括るなら、一つの問題意識に取りつかれると他のことはきれいに忘れてしまい、いっときそれにものすごいエネルギーを注ぐのですが、世の流行関心が移ると、何の脈絡もなくそちらに乗り換える、子どもっぽい多元オタク志向の持ち主だということになるでしょう。
一見、社会現象や学問領域を広く扱って「総合知」を目指しているような体裁を取ってはいますが、自ら総合化して独自の思想にまで仕上げる力はないようです。もちろんまた、逆に何かの専門家になるわけでもありません。「知の巨人」ならぬ「知の風来坊」というのがふさわしい。
しかしことは立花氏一個の問題ではありません。彼の活躍期は、七〇年代から九〇年代。立花氏はいわば、日本が一番元気だったころに言論ジャーナリズム界に咲いた仇花だったのです。
そういう時期に、言論界が、スペシャリストでもジェネラリストでもない、好奇心だけは人一倍旺盛な、ヘンな物書きを、仇花としてしか咲かすことができなかったのだとすれば、これは日本という国がいまだに国際社会の中で文化後進国の位置しか占めていないという哀しい事態を象徴するものだとも言えます。ましてデフレ不況で元気をなくしている今の日本。この環境風土のなかで自立した思想家や哲学者が育つのだろうか、と心配するのは筆者だけでしょうか。