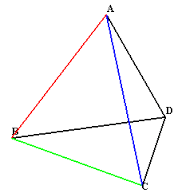ちょっとややこしい哲学の話です。
みなさんはこういうことをどう思われますか。
近代哲学の祖といわれるデカルトは、この世界を「思惟する実体」(精神)と「延長を持つ実体」(モノ)とに二分しました。
次にデカルトは、感覚で「延長体」をとらえると誤ることが多いとして、精神によってとらえられる条件だけにその資格を与えます。
では精神によってとらえられる延長体の資格とは何か。
彼は形、大きさ、運動状態の三つを選び、色、音、味、匂い、肌触り、熱などを主観的な状況次第で変わるものとして排除します。後者は「心」に属する、と。
なるほど色は光の当たり具合によって違って見えますし、味も匂いも肌触りも熱もそれを知覚した人によってさまざまな現われ方をするでしょう。
しかし形や大きさや運動状態は、観測位置を一定にしておけば、だれが計測しても客観的な数値で表すことができます。
この厳密な(?)区別に対して、猛然と反論したのが、アイルランドの哲学者・バークリです。
あらゆるモノは、これらすべての知覚印象を持って現れる。
自分には、色や肌触りを持たない形や大きさだけの物体とか、形や大きさを持たないただの色とか肌触りだけの物体などは、およそ想像することさえできない。モノの存在とは、すなわち知覚の総合なのである、と。
一見どちらも正しいように受け取れます。
そこで二つのことを指摘しておきます。
まずデカルトが延長体の資格として、形、大きさ、運動状態を選んだのには、明確な目的意識があったからです。
それは、モノの多様な現われから、あえて三つを抽象することで、物質世界を数学的・物理学的に秩序づけようという意図です。
これらはいずれも計測可能ですから、さまざまなモノの相互関係を探究することによって、そこから自然界の法則を導き出すことが可能になります。
その際、この時代にはまだ化学も波動学も熱力学も発達していませんし、まして量子力学など先の先の話ですから、色、音、匂い、肌触り、熱……が捨てられるのは当然でした。
事実ニュートンは、デカルトのこの「延長実体」の原理にもとづいて、力学の体系を生み出したのです。
しかし一方、バークリの言い分にも注目すべき点が十分に含まれています。
デカルトの延長実体の条件はすべて視覚に関わっています。
視覚は対象と一定の距離を取って初めて可能となります。それはいわば観測主体を神に近い立場に置くことと等しいのです。
これに対して、音や匂いは空気中に発散するのでモノとは見なせないし、味、肌触りなどは接触によってしか知覚できません。
物理学を可能とするためにこれらが切り捨てられると、モノが私たちに醸し出すその全体的な印象は減殺されてしまいます。
デカルトは知覚世界を主観と客観とに明瞭に分け、同時に数学的・物理学的なモノの見方を基礎づけました。
しかしバークリは神に仕える僧侶でした。
彼にとっては、「実体」とは知覚する精神(心)と、神のみであると考えられたのです。ですからそもそも延長体そのものを「実体」とすることなど、我慢のならないことでした。
いま、私たちの立場からこの両者の対立の意味を考えてみましょう。
デカルトのように、知覚の全体性から形、大きさ、運動だけを抽出すると、自然が喚起してくる生き生きとした接触感覚が失われてしまいます。
その代わり、自然界を計量可能なものとして把握できるので、物理学や数学などが創出できます。
バークリのように、心に訪れる知覚印象の総体が作る観念の束こそ実体なのだと考えると、自然が送り届けてくれる生き生きとした実感は保存されます。花の香りや美味しい食べ物などを存分に玩味できるわけです。
その代わり、物体そのものとか、物質そのものといった考えを棄てなくてはならないので、学問的対象としてモノに分け入っていくことが難しくなります。
二人の立場は、要するに、科学的自然観と情緒的自然観とをそれぞれ象徴していると思うのです。
今の時代は、科学万能信仰がまかり通っており、その中には、科学に名を借りたかなりいいかげんな知識もはびこっています。
科学的にものを考えるとはどういうことか。それを知るためには、これまで蓄積されてきた科学の中にある程度分け入ってみなくてはなりません。
それを棄ててしまうと、かえっていいかげんな知識を科学だと勘違いすることになります。
しかしまた、科学的自然観は、自然や私たちの身体を死んだ物体とみなす部分を持っていることも確かです。
目医者さんは、患者であるあなたの目を見るのに、心と心を通わせるような仕方で生き生きと「目を見る」なんてことをしていたら、診断も治療もできませんね。
いっぽう、生き生きと心を通わせ合うには、お互いの身体を、デカルトのように形と大きさと運動状態としてだけ把握するのではなく、バークリのように、知覚を総体として動員して把握するのでなくてはなりません。
両方とも大切だと思うのですが、いかがでしょうか。