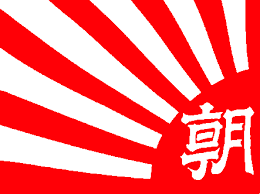倫理の起源57

*以下の記述は、当ブログにすでに掲載した「『風立ちぬ』と『永遠のゼロ』について(3)」と一部重複しますが、訂正・加筆してあります。
さてここまでくれば、近年の大ヒット作、百田尚樹作『永遠のゼロ』(2006年)および山崎貴監督の、同名の映画作品(2013年)に触れないわけにはいかないだろう。
周知のように、両作品は、大東亜戦争期と2000年代初期との60年以上を隔てた二つの時期を往復する枠組みのもとに作られている。司法試験に何度も落ちて働く気もなく浪人している弟が、ライターの姉から依頼を受けて、特攻隊で死んだ実の祖父(義理の祖父は別にいる)のことを二人で調べ始める。いまや80代前後になった生き残り兵士たちを苦労して探し当てて話を聞くうち、祖父の意外な側面がしだいに明らかになってゆく。ゼロ戦搭乗員の祖父・宮部久蔵は、必ず生きて妻子のもとに帰ることを信条としていたにもかかわらず、なぜ特攻隊に志願したのか。この謎を中心にドラマは進行し、最後近くになって劇的な展開を見せる。その劇的な展開の部分を略述すると次のようになる。
義理の祖父・大石はじつは教官時代の宮部の生徒であり、宮部を深く尊敬している。ふだんは極度に用心深い宮部が、訓練指導中に珍しく油断して米軍戦闘機の攻撃にさらされた時、大石は機銃の装備もないままに体当たりで宮部を救う。この深い縁で結ばれた二人は、もはや敗戦間近の時期、偶然にも同じ日に鹿屋基地から特攻隊員として飛び立つことになる。出発間際に宮部は飛行機を代ってくれと大石に申し出る。宮部は、自分の機のエンジン不調に気づき、大石が万に一つも助かることを期待してこの申し出をしたのである。というのも、エンジンが順調ならその搭乗員は100%死ぬが、不調で飛行不能となれば不時着することが可能となるからである。こうして大石は救われ、宮部はただ一機、激しい迎撃をくぐり抜けて敵空母に激突する。大石の機には、もし君が運良く生き残り、自分の家族が路頭に迷って苦しんでいるのを見つけたら助けてほしいという宮部のメモが残されていた。大石は四年後ようやくバラック住まいで困窮している宮部の妻子を見つける。その後、何年も彼らのもとに通って援助し続けるうち、やがて親愛の情が深まり、大石と妻・松乃とは結婚する。しかし、あれほど生き残ることを強く主張していた宮部が、なぜ特攻に志願したのか、すべてのいきさつを語ってきた当の大石さえその理由をうまく表現できない。
私はこの二作を、エンターテインメントとしての面白さもさることながら、重い倫理的・思想的課題を強く喚起する画期的な作品だと思う。その画期性のうち最も重要なものは、戦後から戦前・戦中の歴史を見る時の視線を大きく変えたことである。この場合、戦後の視線というのは、単に戦前・戦中をひたすら軍国主義が支配した悪の時代と見る左翼的な平和主義イデオロギーを意味するだけではない。その左翼イデオロギーの偏向を批判するために、日本の行った戦争のうちにことさら肯定的な部分を探し当てたり、失敗を認めまいとしたりする一部保守派の傾向をも意味している。言い換えると、この両作品は、戦後における二つの対立する戦争史観の矛盾を止揚・克服しているのだ。なぜそう言えるのかは後述する。
ともあれ、その止揚・克服に成功しているという印象を与えるのに最も大きく寄与しているのが、主人公・宮部のキャラクター造型である。
原作では、宮部久蔵のキャラクターは概略次のように造型されている。
①海軍の一飛曹(下士官)。のちに少尉に昇進。これは飛行機乗りとして叩き上げられたことを意味する。
②すらりとした青年で、部下にも「ですます」調の丁寧な言葉を使い、優しく、面倒見がよい。少年時代、棋士をめざそうかと思ったほど囲碁が強い。
③パイロットとしての腕は抜群だが、仲間内では「臆病者」とうわさされている。その理由は、機体の整備点検状態に異常なほど過敏に神経を使うこと、飛行中絶えず後ろを気遣うこと、帰ってきた時に、機体にほとんど傷跡が見られないので、本当に闘ったのか疑問の余地があること、など。
④「絶対に生き残らなくてはだめだ」とふだんから平気で口にしており、戦陣訓の「生きて虜囚の辱めを受けず」とは正反対の思想の持ち主である。ガダルカナル戦の無謀な作戦が上官から指示された時には、こんな作戦は無理だと思わず異議を唱えたため、こっぴどく殴られる。
⑤奥さんと生れたばかりの子どもの写真をいつも携行しており、一部の「猛者」連中からは軟弱者として軽蔑と失笑を買っている。しかしいっぽう彼は、ラバウルの森に深夜ひとりで入り込み、重い銃火器を持ち上げたり枝から逆さにぶら下がったりして、超人的な肉体鍛錬に励んでいる。部下の井崎が歩み寄って鍛錬の辛さを問うと、彼に家族の写真を見せて、「辛い、もう辞めよう、そう思った時、これを見るのです。これを見ると、勇気が湧いてきます」と答える。
⑥撃墜した米機からパラシュートで降下するパイロットを追撃し、武士の情けをわきまえないふるまいとして周囲の顰蹙を買う。これに対して、自分たちは戦争をしているのであり、敵の有能なパイロットを殺すことこそが大事で、それをしなければ自分たちがやられると答える。真珠湾攻撃が成功した時にも、空母と油田を爆撃しなかったことを批判する。
⑦一度だけ宮部は部下を殴ったことがある。それは撃墜されて死んだ米パイロットの胸元から若い女性のヌード写真が出てきたときのこと。部下たちが興奮し、次々に手渡して弄んだ後、宮部がそれを米兵の胸元に戻すと、ひとりの兵が彼の制止も聞かずもう一度取り出そうとしたからである。その写真の裏には、「愛する夫へ」と書かれていた。「できたら、一緒に葬ってやりたい」と彼は言う。
⑧内地で特攻隊要員養成の教官を務めている時期、やたらと「不可」ばかりつける。戦局は敗色濃厚で、厳しい実践教育をくぐり抜けた生徒(学徒動員された士官たち)に合格点を与えれば与えるほど、優秀な人材を死地に送ることに加担せざるを得ないからである。こうして、彼の苦悩と葛藤は深まってゆく。
⑨急降下訓練中に失敗して機を炎上させ自らも命を落とした生徒を、上官が、「訓練で命を落とすような奴は軍人の風上にもおけない。貴重な飛行機をつぶすとは何事か!」と非難したのに対して、ひとり敢然と「彼は立派な男でした」と異議を唱え、上官に叩きのめされる。生徒の名誉を守ったこの発言によって、彼は生徒たちから深く尊敬されるようになる。
⑩大石は体当たりで宮部を助けた時、敵の銃弾を受けて重傷を負う。宮部は命拾いをしたことに感謝しつつも、いっぽうでは大石の無謀さをなじる。
⑪戦後にやくざとなる部下の荒武者・景浦から模擬戦を申し込まれるが、宮部はきっぱりと断る。執着と憤懣を晴らせない景浦は、強引に模擬戦に誘い込み、思わず背後から機銃を発射してしまうが、宮部は難なくすり抜け、逆に信じられないほどの技によって景浦の後ろに至近距離でピタリとつける。もちろん宮部は発射しない。
映画では、⑥のパラシュート追撃部分と⑦の部分がカットされているが、これは少々残念である。というのは、この両場面には、宮部が、戦場においてあくまでも冷徹な戦士であることが象徴されていると同時に、他方では、死者に等しく畏敬の念を持ち、人情を深く理解する人格の持ち主でもあることが表されているからである。
代わりに、原作では宮部を知る者の語りという作品の構成上、描くことができなかった私生活的な場面が二つ挿入されている。一つは、宮部が一泊だけの急な休暇で帰宅した時のシーン。わが子と初めて対面し入浴させて微笑ましい役を演じ、あくる日、妻との別れ際に、離れがたくて背面から顔を寄せる妻に対して、「私は必ず帰ってきます。手を失っても、足を失っても……死んでも帰ってきます。」ときっぱりと約束する。
もう一つは、はじめは大石の援助に拒否的だった松乃、その子・清子と大石との間に、やがて愛情が芽生えて育ち、家族のように睦まじくなっていくプロセスを描いたシーン。 いずれもとても細やかで情緒豊かな映像で表現されていて、観る者の涙を誘わずにはおかない。この二つのシーンは、私の言葉ではエロス的な関係の描写であり、非常に重要な意味を持っている。

*以下の記述は、当ブログにすでに掲載した「『風立ちぬ』と『永遠のゼロ』について(3)」と一部重複しますが、訂正・加筆してあります。
さてここまでくれば、近年の大ヒット作、百田尚樹作『永遠のゼロ』(2006年)および山崎貴監督の、同名の映画作品(2013年)に触れないわけにはいかないだろう。
周知のように、両作品は、大東亜戦争期と2000年代初期との60年以上を隔てた二つの時期を往復する枠組みのもとに作られている。司法試験に何度も落ちて働く気もなく浪人している弟が、ライターの姉から依頼を受けて、特攻隊で死んだ実の祖父(義理の祖父は別にいる)のことを二人で調べ始める。いまや80代前後になった生き残り兵士たちを苦労して探し当てて話を聞くうち、祖父の意外な側面がしだいに明らかになってゆく。ゼロ戦搭乗員の祖父・宮部久蔵は、必ず生きて妻子のもとに帰ることを信条としていたにもかかわらず、なぜ特攻隊に志願したのか。この謎を中心にドラマは進行し、最後近くになって劇的な展開を見せる。その劇的な展開の部分を略述すると次のようになる。
義理の祖父・大石はじつは教官時代の宮部の生徒であり、宮部を深く尊敬している。ふだんは極度に用心深い宮部が、訓練指導中に珍しく油断して米軍戦闘機の攻撃にさらされた時、大石は機銃の装備もないままに体当たりで宮部を救う。この深い縁で結ばれた二人は、もはや敗戦間近の時期、偶然にも同じ日に鹿屋基地から特攻隊員として飛び立つことになる。出発間際に宮部は飛行機を代ってくれと大石に申し出る。宮部は、自分の機のエンジン不調に気づき、大石が万に一つも助かることを期待してこの申し出をしたのである。というのも、エンジンが順調ならその搭乗員は100%死ぬが、不調で飛行不能となれば不時着することが可能となるからである。こうして大石は救われ、宮部はただ一機、激しい迎撃をくぐり抜けて敵空母に激突する。大石の機には、もし君が運良く生き残り、自分の家族が路頭に迷って苦しんでいるのを見つけたら助けてほしいという宮部のメモが残されていた。大石は四年後ようやくバラック住まいで困窮している宮部の妻子を見つける。その後、何年も彼らのもとに通って援助し続けるうち、やがて親愛の情が深まり、大石と妻・松乃とは結婚する。しかし、あれほど生き残ることを強く主張していた宮部が、なぜ特攻に志願したのか、すべてのいきさつを語ってきた当の大石さえその理由をうまく表現できない。
私はこの二作を、エンターテインメントとしての面白さもさることながら、重い倫理的・思想的課題を強く喚起する画期的な作品だと思う。その画期性のうち最も重要なものは、戦後から戦前・戦中の歴史を見る時の視線を大きく変えたことである。この場合、戦後の視線というのは、単に戦前・戦中をひたすら軍国主義が支配した悪の時代と見る左翼的な平和主義イデオロギーを意味するだけではない。その左翼イデオロギーの偏向を批判するために、日本の行った戦争のうちにことさら肯定的な部分を探し当てたり、失敗を認めまいとしたりする一部保守派の傾向をも意味している。言い換えると、この両作品は、戦後における二つの対立する戦争史観の矛盾を止揚・克服しているのだ。なぜそう言えるのかは後述する。
ともあれ、その止揚・克服に成功しているという印象を与えるのに最も大きく寄与しているのが、主人公・宮部のキャラクター造型である。
原作では、宮部久蔵のキャラクターは概略次のように造型されている。
①海軍の一飛曹(下士官)。のちに少尉に昇進。これは飛行機乗りとして叩き上げられたことを意味する。
②すらりとした青年で、部下にも「ですます」調の丁寧な言葉を使い、優しく、面倒見がよい。少年時代、棋士をめざそうかと思ったほど囲碁が強い。
③パイロットとしての腕は抜群だが、仲間内では「臆病者」とうわさされている。その理由は、機体の整備点検状態に異常なほど過敏に神経を使うこと、飛行中絶えず後ろを気遣うこと、帰ってきた時に、機体にほとんど傷跡が見られないので、本当に闘ったのか疑問の余地があること、など。
④「絶対に生き残らなくてはだめだ」とふだんから平気で口にしており、戦陣訓の「生きて虜囚の辱めを受けず」とは正反対の思想の持ち主である。ガダルカナル戦の無謀な作戦が上官から指示された時には、こんな作戦は無理だと思わず異議を唱えたため、こっぴどく殴られる。
⑤奥さんと生れたばかりの子どもの写真をいつも携行しており、一部の「猛者」連中からは軟弱者として軽蔑と失笑を買っている。しかしいっぽう彼は、ラバウルの森に深夜ひとりで入り込み、重い銃火器を持ち上げたり枝から逆さにぶら下がったりして、超人的な肉体鍛錬に励んでいる。部下の井崎が歩み寄って鍛錬の辛さを問うと、彼に家族の写真を見せて、「辛い、もう辞めよう、そう思った時、これを見るのです。これを見ると、勇気が湧いてきます」と答える。
⑥撃墜した米機からパラシュートで降下するパイロットを追撃し、武士の情けをわきまえないふるまいとして周囲の顰蹙を買う。これに対して、自分たちは戦争をしているのであり、敵の有能なパイロットを殺すことこそが大事で、それをしなければ自分たちがやられると答える。真珠湾攻撃が成功した時にも、空母と油田を爆撃しなかったことを批判する。
⑦一度だけ宮部は部下を殴ったことがある。それは撃墜されて死んだ米パイロットの胸元から若い女性のヌード写真が出てきたときのこと。部下たちが興奮し、次々に手渡して弄んだ後、宮部がそれを米兵の胸元に戻すと、ひとりの兵が彼の制止も聞かずもう一度取り出そうとしたからである。その写真の裏には、「愛する夫へ」と書かれていた。「できたら、一緒に葬ってやりたい」と彼は言う。
⑧内地で特攻隊要員養成の教官を務めている時期、やたらと「不可」ばかりつける。戦局は敗色濃厚で、厳しい実践教育をくぐり抜けた生徒(学徒動員された士官たち)に合格点を与えれば与えるほど、優秀な人材を死地に送ることに加担せざるを得ないからである。こうして、彼の苦悩と葛藤は深まってゆく。
⑨急降下訓練中に失敗して機を炎上させ自らも命を落とした生徒を、上官が、「訓練で命を落とすような奴は軍人の風上にもおけない。貴重な飛行機をつぶすとは何事か!」と非難したのに対して、ひとり敢然と「彼は立派な男でした」と異議を唱え、上官に叩きのめされる。生徒の名誉を守ったこの発言によって、彼は生徒たちから深く尊敬されるようになる。
⑩大石は体当たりで宮部を助けた時、敵の銃弾を受けて重傷を負う。宮部は命拾いをしたことに感謝しつつも、いっぽうでは大石の無謀さをなじる。
⑪戦後にやくざとなる部下の荒武者・景浦から模擬戦を申し込まれるが、宮部はきっぱりと断る。執着と憤懣を晴らせない景浦は、強引に模擬戦に誘い込み、思わず背後から機銃を発射してしまうが、宮部は難なくすり抜け、逆に信じられないほどの技によって景浦の後ろに至近距離でピタリとつける。もちろん宮部は発射しない。
映画では、⑥のパラシュート追撃部分と⑦の部分がカットされているが、これは少々残念である。というのは、この両場面には、宮部が、戦場においてあくまでも冷徹な戦士であることが象徴されていると同時に、他方では、死者に等しく畏敬の念を持ち、人情を深く理解する人格の持ち主でもあることが表されているからである。
代わりに、原作では宮部を知る者の語りという作品の構成上、描くことができなかった私生活的な場面が二つ挿入されている。一つは、宮部が一泊だけの急な休暇で帰宅した時のシーン。わが子と初めて対面し入浴させて微笑ましい役を演じ、あくる日、妻との別れ際に、離れがたくて背面から顔を寄せる妻に対して、「私は必ず帰ってきます。手を失っても、足を失っても……死んでも帰ってきます。」ときっぱりと約束する。
もう一つは、はじめは大石の援助に拒否的だった松乃、その子・清子と大石との間に、やがて愛情が芽生えて育ち、家族のように睦まじくなっていくプロセスを描いたシーン。 いずれもとても細やかで情緒豊かな映像で表現されていて、観る者の涙を誘わずにはおかない。この二つのシーンは、私の言葉ではエロス的な関係の描写であり、非常に重要な意味を持っている。