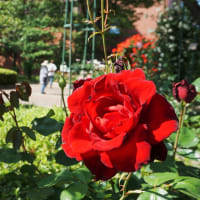柳川を訪れました。1年振りです。まずは駐車場近くの古民家へ。室内には雛人形とさげもんがびっしりと飾られていました。案内の小母さんに撮影の可否を聞いたら、じっくり見た後に1、2枚ならいいですよという返事。そういえば、数年前に来た時も同じことを言われました。庭に置かれた内裏雛を1枚だけ撮りました。

沖ノ端の川下り下船場にきて驚きました。堀端の柳並木が消えています。どうしたことかと思っていると、市の告知板が目に入りました。それによると、この通りは修景工事が始まるのだそうです。電線の地中化と歩道の拡幅や親水工事が行われます。
完成時のイメージ図には柳並木がしっかりと描かれていました。工事期間は2年なので、しばらくは殺風景な掘割になります。出来れば柳は幼木ではなく、水面に葉影を落とすような成木を植栽してほしい。

城堀を少し歩きました。コロナ禍も一段落し、川下りの客はだいぶ戻ってきています。

どんこ舟は人が歩く速さで行きます。

次々と舟が来ます。ここは「御花」の裏手です。

水辺の道に咲いていた赤い椿。

国の名勝「御花」です。旧藩主立花家の邸宅として明治末に建てられました。現在は末裔がホテルと料亭を経営しています。洋館と主屋は有料で開放されていて、いまの季節は豪華な雛飾りが観光客の目を楽しませます。

殿の倉と呼ばれている立花家史料館のそばを舟が通ります。下船場はすぐそこです。

沖ノ端に戻ってきました。やはり柳がないと風情がありません。

下の写真は数年前に来た時、同じ場所の風景です。

沖ノ端にある北原白秋の生家です。北原家は酒造家で手広く商いをしていました。現在の建物は荒廃していた母屋を修復・復元したものです。生家とはいっても、白秋が生まれたのは隣県の母の里でした。久し振りに入ってみました。

母屋の内部。明治40年の夏。与謝野寛や北原白秋、吉井勇ら明星派の詩人五人が九州を旅行します。彼らは往きと帰りに北原家に泊まり歓待されました。

二升徳利と北原酒造の銘酒「潮」。一行は毎食、倉から出したての「潮」を飲み、それぞれ歌を詠みました。彼らに面会するため、近郷から泊りがけで来る人もいたそうです。東京の新聞に連載された紀行文は、後に「五足の靴」として本にまとめられました。

座敷に飾られた雛段とさげもん。柳川のさげもんは、初節句の女の子の幸せと健康長寿を願うものです。

座敷から見た離れの隠居部屋。平成になって復元されたものです。白秋は中学生の頃、この部屋で勉強していました。

隠居部屋と向かいの土蔵の間にある柳川独特の掘割に面した汲水場。いまでも川下りの際、掘割端の家に残る汲水場の石段を見ることが出来ます。

明星派の五人は旅の帰りに再び白秋の家を訪れます。夜の帳が下りるころ、一行は旧藩主を祀る三柱神社そばの松月楼で氷水を食べて寛いだ後、舟で掘割を下ります。夜も更けた十時に舟は北原家の土蔵の裏手に着きました。多分この石段の所だったのでしょう。
「柳河は水の国だ」で始まる柳河滞在記は、「五足の靴」の中でも詩情あふれる美しい描写です。北原白秋も遺稿となった写真詩集「水の構図」で、「水郷柳河こそは、我が生れの里である。この水の柳河こそは、我が詩歌の母体である」と述べています。

白秋生家を後にして駐車場へ戻ります。ここは沖ノ端の少し外れ。どことなく漁師町の面影がします。沖ノ端は河口近くの川港です。

玄関先にあるモミジが芽吹きました。紅葉の時は上の方から色づき、芽吹きの時は下から緑が出てくるのですね。