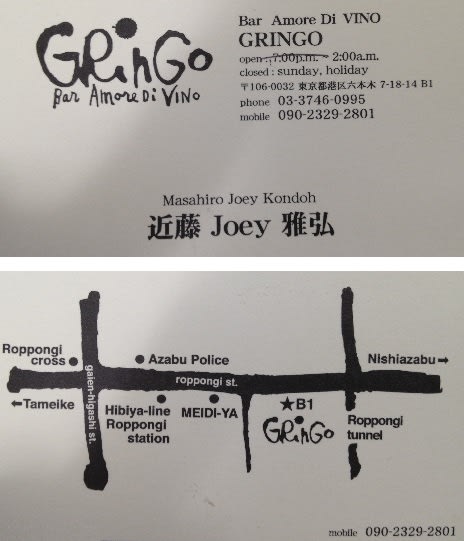これは私のビクトリノックス スーベニアである。
仕事がハネてから、アウトドアマンの友人とファミレスで落ち会う。
「まじで?」
友人いたく喜ぶ。
いろいろ貰ってたし、まあ、友情の証は刃物で、っつーことで、おいらの
スーベニアを進呈した。まじもんで喜んでいた。スーベニアは登山者や
キャンパーの定番だ。
極めてシンプルであるのだが、ここ一番の働きをする。スーベニアのおかげ
で命を拾った登山者や冒険家は多くいる。
このモデルは、肌身離さず身につけているタイプのナイフだ。私が年間
60日以上釣行していた頃は、スーベニアを紐に通して首から吊るして
いた。多くの登山者もそうしている。
寝るときにも身から離さない。
緊急時に装備を切ったり、シェラフを中から切り裂いて脱出したりする。
「『俺もスーベニア持ってるよ』と言ってザックから取り出すキャンパーって
どうよ?」と友人が笑いながら言う。
「ダメっしょ、それ」と私が言うと、「だよな〜(笑」と返ってきた。
スーベニアのスーベニアらしい使い方は、やはり、多くの登山家が
スタンダードとしているような、常に身につける使用法だと思う。
このスーベニアは、ストック分の未使用品だが、喜んで貰って良かった。
スーベニアということで、とても嬉しかったようだ。
スーベニアとは、思い出になる記念品という意味。まさにこの個体は、
晴れて本当にスーベニアと成ったようである。めでたし、めでたし。