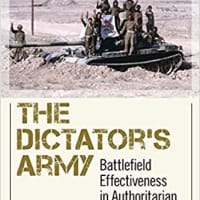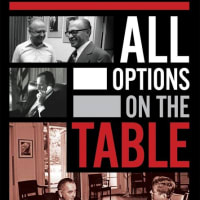抑止政策の成否を左右する1つの重要な要因は、決意の信ぴょう性だといわれています。すなわち、耐え難い損害を与えると脅された相手が、抑止国の決意は固いをと信じれば、望ましくない敵対的行動を控えるということです。ここで問われることは、何が決意に関する信ぴょう性や評判を生み出すのかです。リアリストは、パワーや利益が決意の源泉であると主張してきました。国家は、決意や威嚇が本物かどうかを過去の行動からではなく、自国と敵対国との相対的なパワーや利益で判断するということです。この理論が正しければ、国家は危機や紛争で相手に妥協したり引き下がったりしても、その評判や信ぴょう性を落さずに済みます。したがって、もっぱら自らの評判や信ぴょう性を維持するために不必要な対決姿勢をとったり、強い決意を示すために利害の小さな紛争へ軍事的に介入したりすることは、避けるべきだということになります。このような立場をとる代表的な研究者は、このブログでも紹介したダリル・プレス氏(ダートマス大学)です。かれは、威嚇の信ぴょう性は対象国の過去の行動ではなく、その時々のバランス・オブ・パワーにより判断されることを事例研究により明らかにしました。
他方、古典的なバーゲニング理論では、国家が過去にとった行動は、当該国に対する決意の評判や信ぴょう性を左右すると説明されていました。トーマス・シェリング氏は、今では、この分野で既に古典となった名著『軍備と影響力(Arms and Influence)』において、以下のように主張しています。
「見方というのは、それ自体が勢いを持つ。この最後のことは、かなりの程度、本当なのだ。ある危機において、今日、何を行うかは、明日、何を行うだろうかを予期することに影響するからだ…一連の外交的対立において、いかにして評判が弱さの兆候へと収斂していくのかは、まったく分からない。どう(対立から)手を引くと、自分自身が臆病に見られたり、傍観者にそう見られたり、敵にそう見られたりし始めるかは、まったく分からない。屈服は上記のような非対称な状況をつくってしまうと、どちらの側も感じる状況に陥ることはあり得る。それは降伏者の代償を求めない行為のようなものだから、誰であろうと引き下がってしまったら、明日かそれ以後は屈しないだろうことを誰かに言い聞かせても無駄だろう」(Thomas C. Schelling, Arms and Influence, Yale University Press, 1966, p. 93)。
シェリング氏は国家がある危機や紛争で引き下がると、その決意は疑われることになると警告しているのです。これが正しいとするならば、国家は自分の決意や信ぴょう性の評判を保持するためには、代償を払う価値があることになります。
このように決意の評判や信ぴょう性の原因については、意見が分かれています。ですので、これは研究上も政策上も、克服されるべき重要な課題でしょう。アレックス・ウェイジガー氏(ペンシルバニア大学)とカレン・ヤリ=ミロ氏(コロンビア大学)は、論文「評判再訪―いかにして過去の行動は国際政治において問題なのか―("Revisiting Reputation: How Past Actions Matter in International Politics")」(International Organization, Vol. 69, No. 2, Spring 2015) において、「軍事化された国家間紛争(MID: Militarized Interstate Dispute)」のデータセットをつかって、定量的手法により、この疑問を解き明かそうとしました。

はじめに、彼女たちは、「決意(resolve)」をジョナサン・マーサー氏(ワシントン大学)の先行研究に従い、「国家がその目的を達成するために、どのくらい戦争のリスクを冒すかの程度」と定義します。そして、決意の信ぴょう性に関する仮説を統計に検定するのですが、その前に、過去の行動が決意の信ぴょう性に影響を与えた1つの事例として、フォークランド紛争に言及しています。アルゼンチンがフォークランド島(マルビナス島)を奪還するに際して、イギリスの予想される反応を同国の過去の行動から判断していた証拠として、フンタ(軍事評議会)のコスタ・メンデス外相の発言を引き合いに出しています(前掲論文、478ページ)。
「(スエズ危機時の)1956年からイギリスの行動は常に交渉であって、軍事力を基礎にしたものではなかった…ローデシアは最近の例であった。そこでイギリスは60万人ものイギリス人を見捨てた。こういった認識を合わせて、イギリスは軍事的反応をしないだろうという結論が導き出された」(デイヴィッド・ウェルチ、田所昌幸監訳『苦渋の選択―対外政策に関する理論―』千倉書房、2016年〔原著2005年〕、128ページに引用)。
要するに、アルゼンチンは、イギリスが過去に軍事力を行使する決意に欠いていたことから、フォークランド(マルビナス)諸島に侵攻しても、戦争に訴えないだろうと判断したのです。そのうえで、ウェイジガー氏とヤリ=ミロ氏は、決意の評判に関するいくつかの仮説を1816年から2001年の間に起こった2332件の軍事化された事件(incidents)から統計的に検定することで、一般化された結論を導いています。すなわち、紛争において引き下がることは、当該国家が、その後に挑戦をうける可能性を高めるのです。過去の行動は決意や威嚇の評判に重大な影響を与えるということです。興味深いことに、著者たちは、プレス氏らの先行研究と自分たちの発見との乖離を埋める説明を試みています。危機時における意思決定において、敵国の過去の行動から収集された情報は、より広義な利益の判断に紛れ込んでしまうので、見過ごされやすいということです(前掲論文、492ページ)。これをフォークランド紛争の事例にそって述べれば、フンタは、過去の行動からして、イギリスは地理的に離れた紛争への軍事介入に利益を見いださないと判断したことになります。敵国の過去の行動に関する記録は、その国が危機や紛争にどの程度の利害を持っているのかを計算する際に埋もれがちなので、政策決定者の発言や文書には表れにくい。だから、事例研究では、過去の行動が決意や威嚇の評判に与えた影響は観察しにくいということでしょう。
ただしウェイジガー氏とヤリ・ミロ氏は、シェリング氏のバーゲニング理論を全面的に肯定しているわけではなく、その限界も指摘しています。過去の行動は、決意や威嚇の評判に普遍的な影響を与えるわけではありません。過去の行動は、同じような危機や紛争においては、国家の決意の評判に関する判断に強く影響しますが、あまり似ていない危機や紛争では、弱い効果しかないということです(前掲論文、492ページ)。著者たちの論文から、危機や紛争の類似性に関する明確な定義は見いだせませんでしたが、つまるところ、評判はそれらの状況や文脈に大きく依存するのです。たとえば、領土紛争で引き下がってしまうと、新しい領土紛争で挑戦を受ける可能性が劇的に上昇します。ある領土紛争で前年に屈服した国家は、過去10年間で屈しなかった国家よりも、15倍も挑戦を受けやすくなると、ウェイジガー氏とヤリ・ミロ氏は結論づけています(491ページ)。もしこの命題が正しいとするならば、領土紛争で譲歩した国家は、将来に高い代償を支払うことになります。なお、著者たちは、国家の評判は、政権交代が起きても、引き続き過去の行動から判断されることを統計検定から明らかにしています。これは直感的には理解しにくいのですが、決意や威嚇の信ぴょう性は、国家は指導層ではなく国家そのものの行動から判断されるようです。
研究者にとって悩ましいのは、同じ課題に対して、定性的方法と定量的方法の分析が、それぞれ異なる回答を提出する研究成果は珍しくないことです。同時に、これは政策決定者にとっても、頭の痛いことでしょう。抑止は国家安全保障にとって死活的な戦略です。もし抑止の威嚇の信ぴょう性はバランス・オブ・パワーや利益によって決まるのであれば、国家は自国優位の軍事バランスを保ちつつ、対決と妥協をうまく使い分けながら、危機や紛争を乗り切るべきだということになります。しかしながら、敵対国に妥協してしまうと抑止の脅しがブラフと受け取られやくなるのであれば、国家は危機や紛争には、基本的に対決姿勢で臨むべきだということになります。これは国家にリスク受容の行動を促すことを意味します。シェリング氏の画期的な研究から半世紀がたっても、対決や威嚇の信ぴょう性に関する因果関係については、まだハッキリしたことは分からないと考えた方がよいのかもしれません。
他方、古典的なバーゲニング理論では、国家が過去にとった行動は、当該国に対する決意の評判や信ぴょう性を左右すると説明されていました。トーマス・シェリング氏は、今では、この分野で既に古典となった名著『軍備と影響力(Arms and Influence)』において、以下のように主張しています。
「見方というのは、それ自体が勢いを持つ。この最後のことは、かなりの程度、本当なのだ。ある危機において、今日、何を行うかは、明日、何を行うだろうかを予期することに影響するからだ…一連の外交的対立において、いかにして評判が弱さの兆候へと収斂していくのかは、まったく分からない。どう(対立から)手を引くと、自分自身が臆病に見られたり、傍観者にそう見られたり、敵にそう見られたりし始めるかは、まったく分からない。屈服は上記のような非対称な状況をつくってしまうと、どちらの側も感じる状況に陥ることはあり得る。それは降伏者の代償を求めない行為のようなものだから、誰であろうと引き下がってしまったら、明日かそれ以後は屈しないだろうことを誰かに言い聞かせても無駄だろう」(Thomas C. Schelling, Arms and Influence, Yale University Press, 1966, p. 93)。
シェリング氏は国家がある危機や紛争で引き下がると、その決意は疑われることになると警告しているのです。これが正しいとするならば、国家は自分の決意や信ぴょう性の評判を保持するためには、代償を払う価値があることになります。
このように決意の評判や信ぴょう性の原因については、意見が分かれています。ですので、これは研究上も政策上も、克服されるべき重要な課題でしょう。アレックス・ウェイジガー氏(ペンシルバニア大学)とカレン・ヤリ=ミロ氏(コロンビア大学)は、論文「評判再訪―いかにして過去の行動は国際政治において問題なのか―("Revisiting Reputation: How Past Actions Matter in International Politics")」(International Organization, Vol. 69, No. 2, Spring 2015) において、「軍事化された国家間紛争(MID: Militarized Interstate Dispute)」のデータセットをつかって、定量的手法により、この疑問を解き明かそうとしました。

はじめに、彼女たちは、「決意(resolve)」をジョナサン・マーサー氏(ワシントン大学)の先行研究に従い、「国家がその目的を達成するために、どのくらい戦争のリスクを冒すかの程度」と定義します。そして、決意の信ぴょう性に関する仮説を統計に検定するのですが、その前に、過去の行動が決意の信ぴょう性に影響を与えた1つの事例として、フォークランド紛争に言及しています。アルゼンチンがフォークランド島(マルビナス島)を奪還するに際して、イギリスの予想される反応を同国の過去の行動から判断していた証拠として、フンタ(軍事評議会)のコスタ・メンデス外相の発言を引き合いに出しています(前掲論文、478ページ)。
「(スエズ危機時の)1956年からイギリスの行動は常に交渉であって、軍事力を基礎にしたものではなかった…ローデシアは最近の例であった。そこでイギリスは60万人ものイギリス人を見捨てた。こういった認識を合わせて、イギリスは軍事的反応をしないだろうという結論が導き出された」(デイヴィッド・ウェルチ、田所昌幸監訳『苦渋の選択―対外政策に関する理論―』千倉書房、2016年〔原著2005年〕、128ページに引用)。
要するに、アルゼンチンは、イギリスが過去に軍事力を行使する決意に欠いていたことから、フォークランド(マルビナス)諸島に侵攻しても、戦争に訴えないだろうと判断したのです。そのうえで、ウェイジガー氏とヤリ=ミロ氏は、決意の評判に関するいくつかの仮説を1816年から2001年の間に起こった2332件の軍事化された事件(incidents)から統計的に検定することで、一般化された結論を導いています。すなわち、紛争において引き下がることは、当該国家が、その後に挑戦をうける可能性を高めるのです。過去の行動は決意や威嚇の評判に重大な影響を与えるということです。興味深いことに、著者たちは、プレス氏らの先行研究と自分たちの発見との乖離を埋める説明を試みています。危機時における意思決定において、敵国の過去の行動から収集された情報は、より広義な利益の判断に紛れ込んでしまうので、見過ごされやすいということです(前掲論文、492ページ)。これをフォークランド紛争の事例にそって述べれば、フンタは、過去の行動からして、イギリスは地理的に離れた紛争への軍事介入に利益を見いださないと判断したことになります。敵国の過去の行動に関する記録は、その国が危機や紛争にどの程度の利害を持っているのかを計算する際に埋もれがちなので、政策決定者の発言や文書には表れにくい。だから、事例研究では、過去の行動が決意や威嚇の評判に与えた影響は観察しにくいということでしょう。
ただしウェイジガー氏とヤリ・ミロ氏は、シェリング氏のバーゲニング理論を全面的に肯定しているわけではなく、その限界も指摘しています。過去の行動は、決意や威嚇の評判に普遍的な影響を与えるわけではありません。過去の行動は、同じような危機や紛争においては、国家の決意の評判に関する判断に強く影響しますが、あまり似ていない危機や紛争では、弱い効果しかないということです(前掲論文、492ページ)。著者たちの論文から、危機や紛争の類似性に関する明確な定義は見いだせませんでしたが、つまるところ、評判はそれらの状況や文脈に大きく依存するのです。たとえば、領土紛争で引き下がってしまうと、新しい領土紛争で挑戦を受ける可能性が劇的に上昇します。ある領土紛争で前年に屈服した国家は、過去10年間で屈しなかった国家よりも、15倍も挑戦を受けやすくなると、ウェイジガー氏とヤリ・ミロ氏は結論づけています(491ページ)。もしこの命題が正しいとするならば、領土紛争で譲歩した国家は、将来に高い代償を支払うことになります。なお、著者たちは、国家の評判は、政権交代が起きても、引き続き過去の行動から判断されることを統計検定から明らかにしています。これは直感的には理解しにくいのですが、決意や威嚇の信ぴょう性は、国家は指導層ではなく国家そのものの行動から判断されるようです。
研究者にとって悩ましいのは、同じ課題に対して、定性的方法と定量的方法の分析が、それぞれ異なる回答を提出する研究成果は珍しくないことです。同時に、これは政策決定者にとっても、頭の痛いことでしょう。抑止は国家安全保障にとって死活的な戦略です。もし抑止の威嚇の信ぴょう性はバランス・オブ・パワーや利益によって決まるのであれば、国家は自国優位の軍事バランスを保ちつつ、対決と妥協をうまく使い分けながら、危機や紛争を乗り切るべきだということになります。しかしながら、敵対国に妥協してしまうと抑止の脅しがブラフと受け取られやくなるのであれば、国家は危機や紛争には、基本的に対決姿勢で臨むべきだということになります。これは国家にリスク受容の行動を促すことを意味します。シェリング氏の画期的な研究から半世紀がたっても、対決や威嚇の信ぴょう性に関する因果関係については、まだハッキリしたことは分からないと考えた方がよいのかもしれません。