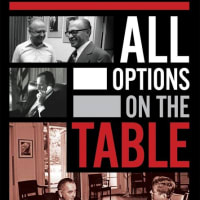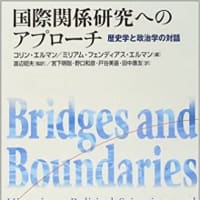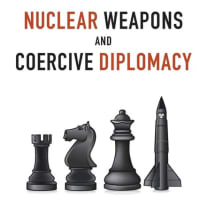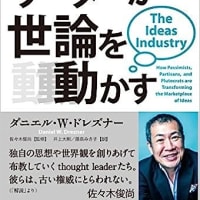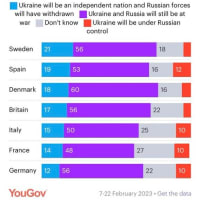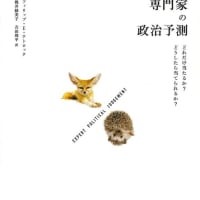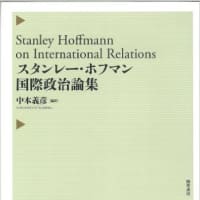社会科学の方法論に関する重要な研究書の日本語版が上梓されました。ヘンリー・ブレイディ、デヴィッド・コリアー編『社会科学の方法論争―多様な分析道具と共通の基準』勁草書房、2014年(原著2010年)です。訳出は、同書の初版と同じく、泉川泰博氏(中央大学)と宮下明聡氏(東京国際大学)が行っています。

本書の研究上の位置づけや内容、意義については、訳者まえがきで、簡潔にして包括的な解説が提供されていますので、そちらをお読み下さい。ここでは、近年の国際関係論の研究動向に関連づけながら、同書の議論が含意する問題提起を考えたいと思います。
まず、理論構築と仮説検証の乖離を指摘しなければなりません。政治学研究では、国際関係の理論構築が衰退する一方で、「統計による仮説検証」の研究が興隆していると指摘されています。その方法論上の背景は、本書がつまびらかにしています。それは、誤解を恐れず端的に言えば、この学界で圧倒的な影響力を持つテキスト、G.キング、R.O.コヘイン、S.ヴァーバ『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論―』(真渕勝監訳)勁草書房、2004年(原著1994年)が、定性的アプローチは定量的アプローチに倣うよう強力に勧めたため、結果として、「政治学方法論の地平を狭めてしまった」(『社会科学の方法論争(第2版)』vページ)ことがあります。
その1つの帰結が、理論を構築する研究の退潮です。『社会科学の方法論争』でも指摘されるように、理論構築やその方法に対する配慮が、『社会科学のリサーチ・デザイン』では十分に示されておりません。その『社会科学のリサーチ・デザイン』は、KKVの略称で政治学徒に広く知られ親しまれており、同書が国際関係論の研究をより「科学的なもの」にするよう、優秀な(厳しい?)「教師役」を務めています。このことは、間違いなく多大な学問的貢献です。しかしながら、その結果、KKVが意図したわけではないにせよ(因果関係も立証されていませんが)、国際関係研究における理論構築や発展が衰退したことも否めません。
このことについては、J.ミアシャイマー氏(シカゴ大学)とS.ウォルト氏(ハーバード大学)も、以下のように批判しています。
「理論と呼ばれるものに関心が向かなくなり、単純な仮説検証の方向に動いている。この傾向は理論に対する方法の勝利を示している。…(KKVの)この本が社会科学をどう行うかの決定版テキストである限り、単純な仮説検証がどんどん広がるのも不思議なことではない」(John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, "Leaving Theory Behind: Why Hypothisis Testing Has Became Bad for IR," Faculty Research Working paper Series, Harvard Kennedy School, Jan. 2013, pp. 4, 37 同論文は、ミアシャイマー氏の個人HPからDLできます)。
もちろん、KKVに対する批判者たちは、彼らを政治学界の悪玉に仕立て上げようとしてるのではありません。アメリカを中心する政治学/国際関係論研究の「定量帝国主義」(ラリー・バーテルズ氏)に対して、定性的アプローチの意義や学術上の貢献、理論構築や検証の道具としての効用を見直すと同時に、理論構築や開発の重要性にもっと注意を払うべきだと主張しているのです(この点で、第2版の新章である、A.ベネット「過程追跡と因果的推論」およびD.フリードマン「科学的探究のタイプについて」は、示唆に富むと思いました)。
ハンス・モーゲンソー氏は、かつて政治学分野で「行動科学」が台頭した時に、そうした研究に従事する人たちを「ささいなことにふけり、(事象の説明を)わかりにくくするために、難解な専門用語や数式、方程式、図表に熱狂的とも思えるほどの情熱をささげる」と皮肉りました(S.ヴァン・エヴェラ『政治学のリサーチ・メソッド』勁草書房、2009年、99ページに引用)。同じような指摘は、『社会科学の方法論争』にも見られます。すなわち、「KKV(の)枠組みを受け入れると、研究対象となる実質的なテーマを極度に狭めてしまい、その結果研究者は些細なテーマの研究を行ってしまう」(第2版、142ページ)ということです。
ミアシャイマー氏とウォルト氏も、「仮説検証文化(における)難解な専門用語や知る人ぞ知る方法論は、国際関係論を政策決定者や学識のあるエリートそして一般大衆の多くにとって、近づきがたいものにしてしまった。…これらの傾向は、国際関係論を現実世界の重要問題を理解したり解決したりすることと無関係なものにしてしまう危険を孕んでいる」(上記論文、41ページ)と懸念を示しています。
日本とアメリカでは、政治学/国際関係論の方法論の分布が異なりますので、上記の定量アプローチへの批判をそのまま受け入れるべきではないでしょう。同時に、日本の政治学はアメリカ化しているとも指摘されています(菅原琢「『アメリカ化』する日本の政治学」『思想地図』2010年所収参照)。もし、そうであるならば、KKVとその批判者たちが巻き起こした論争を理解して、政治や国際関係の研究の在り方や方向性を今のうちにジックリと考えることには、大きな意義があると信じています。

本書の研究上の位置づけや内容、意義については、訳者まえがきで、簡潔にして包括的な解説が提供されていますので、そちらをお読み下さい。ここでは、近年の国際関係論の研究動向に関連づけながら、同書の議論が含意する問題提起を考えたいと思います。
まず、理論構築と仮説検証の乖離を指摘しなければなりません。政治学研究では、国際関係の理論構築が衰退する一方で、「統計による仮説検証」の研究が興隆していると指摘されています。その方法論上の背景は、本書がつまびらかにしています。それは、誤解を恐れず端的に言えば、この学界で圧倒的な影響力を持つテキスト、G.キング、R.O.コヘイン、S.ヴァーバ『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論―』(真渕勝監訳)勁草書房、2004年(原著1994年)が、定性的アプローチは定量的アプローチに倣うよう強力に勧めたため、結果として、「政治学方法論の地平を狭めてしまった」(『社会科学の方法論争(第2版)』vページ)ことがあります。
その1つの帰結が、理論を構築する研究の退潮です。『社会科学の方法論争』でも指摘されるように、理論構築やその方法に対する配慮が、『社会科学のリサーチ・デザイン』では十分に示されておりません。その『社会科学のリサーチ・デザイン』は、KKVの略称で政治学徒に広く知られ親しまれており、同書が国際関係論の研究をより「科学的なもの」にするよう、優秀な(厳しい?)「教師役」を務めています。このことは、間違いなく多大な学問的貢献です。しかしながら、その結果、KKVが意図したわけではないにせよ(因果関係も立証されていませんが)、国際関係研究における理論構築や発展が衰退したことも否めません。
このことについては、J.ミアシャイマー氏(シカゴ大学)とS.ウォルト氏(ハーバード大学)も、以下のように批判しています。
「理論と呼ばれるものに関心が向かなくなり、単純な仮説検証の方向に動いている。この傾向は理論に対する方法の勝利を示している。…(KKVの)この本が社会科学をどう行うかの決定版テキストである限り、単純な仮説検証がどんどん広がるのも不思議なことではない」(John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, "Leaving Theory Behind: Why Hypothisis Testing Has Became Bad for IR," Faculty Research Working paper Series, Harvard Kennedy School, Jan. 2013, pp. 4, 37 同論文は、ミアシャイマー氏の個人HPからDLできます)。
もちろん、KKVに対する批判者たちは、彼らを政治学界の悪玉に仕立て上げようとしてるのではありません。アメリカを中心する政治学/国際関係論研究の「定量帝国主義」(ラリー・バーテルズ氏)に対して、定性的アプローチの意義や学術上の貢献、理論構築や検証の道具としての効用を見直すと同時に、理論構築や開発の重要性にもっと注意を払うべきだと主張しているのです(この点で、第2版の新章である、A.ベネット「過程追跡と因果的推論」およびD.フリードマン「科学的探究のタイプについて」は、示唆に富むと思いました)。
ハンス・モーゲンソー氏は、かつて政治学分野で「行動科学」が台頭した時に、そうした研究に従事する人たちを「ささいなことにふけり、(事象の説明を)わかりにくくするために、難解な専門用語や数式、方程式、図表に熱狂的とも思えるほどの情熱をささげる」と皮肉りました(S.ヴァン・エヴェラ『政治学のリサーチ・メソッド』勁草書房、2009年、99ページに引用)。同じような指摘は、『社会科学の方法論争』にも見られます。すなわち、「KKV(の)枠組みを受け入れると、研究対象となる実質的なテーマを極度に狭めてしまい、その結果研究者は些細なテーマの研究を行ってしまう」(第2版、142ページ)ということです。
ミアシャイマー氏とウォルト氏も、「仮説検証文化(における)難解な専門用語や知る人ぞ知る方法論は、国際関係論を政策決定者や学識のあるエリートそして一般大衆の多くにとって、近づきがたいものにしてしまった。…これらの傾向は、国際関係論を現実世界の重要問題を理解したり解決したりすることと無関係なものにしてしまう危険を孕んでいる」(上記論文、41ページ)と懸念を示しています。
日本とアメリカでは、政治学/国際関係論の方法論の分布が異なりますので、上記の定量アプローチへの批判をそのまま受け入れるべきではないでしょう。同時に、日本の政治学はアメリカ化しているとも指摘されています(菅原琢「『アメリカ化』する日本の政治学」『思想地図』2010年所収参照)。もし、そうであるならば、KKVとその批判者たちが巻き起こした論争を理解して、政治や国際関係の研究の在り方や方向性を今のうちにジックリと考えることには、大きな意義があると信じています。