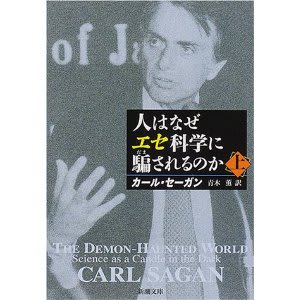軍事や安全保障を研究していると、時々、旧軍人の切腹の話にでくわします。たとえば、「統率の外道」とみなしていた神風特攻をあえて実行した大西瀧治郎中将が、終戦時に「割腹自殺」したことなどは、その例です。
私は、「切腹」という苦痛に満ちた行為で自らの命を断つことについて、前々から不思議に思っていました。人間が合理的存在であるならば、「自殺」する場合、一般的には、なるべく苦しまない方法をとるはずでしょう。しかしながら、「切腹」は、わざわざ筆舌に尽くしがたい痛みを伴うやり方により、自害する行動なのです。明らかに、人間営為の逸脱事例でしょう。では、なぜ、「日本人」はそうようなことをするのか。その理由は何なのか。
千葉徳爾氏の『日本人はなぜ切腹するのか』(東京堂出版、1994年)は、このパズルに挑戦して、説得的な答えを導き出しています。

千葉氏の仮説はこうです。「ヒトが自分の真の心持を他に示そうとする具体的手段として、切腹という形式が発生し(日本で)伝承された」(221ページ)というものです。そして筆者は、この仮説を民俗学の知見と資料を駆使して、実証しようとしています。「これを事実にもとづいて証明しなければ科学とはいえない」と(142ページ)。つまり、本書は、日本人の切腹という行為を科学的に解明しようとした労作なのです。
本書によれば、日本人の「切腹」とは、単なる「自殺」の手段ではなく、自らの「名誉」や「節操」を守る「潔白証明」の方法だということです。すなわち、「日本人たちの解剖学的知識では、獣やヒトの内蔵は生命と精神との源泉であり、それを資格によって検討することが自他ともに本心・誠意を確認しあう手段と考えらた。そのためには腹腔を切開することが是非とも必要であ(る)…日本人の責任のとりかたの基本となるのは、このような思考法といえる」(142ページ)ということです。確かに、腸には神経伝達物質セロトニンの約90%が集中していると言われており、「第2の脳」と形容されることさえありますので、この思考は、単なる「妄想」でもないと言えるでしょう。
なお、本書を読んで驚いたことが、いくつかありました。全ては、私のは浅学によるのですが、それからは以下の通りです。
第1に、腹を刃物で横一文字に切ることは、解剖学的に、腹部の弾力や腹筋の抵抗などがあるため、そう簡単なことではない、ということです(同書、28-32ページ)。くわえて、「切腹は(大血管が通っていないため)それのみで直ちに出血死に至ることは稀」(34ページ)なのです。切腹のみでの死亡率は、わずか4%というデータも示されています(36ページ)。この事実は、多くの人達が抱く「切腹」のステレオタイプ的イメージとは、大きく異なるのではないでしょうか。
第2に、「切腹」の異文化理解に対する含意です。「切腹」は、欧米人にとって日本民族の「残虐さのシンボル」であった一方、日本人にとって「いさぎよさのシンボル」でした(156-157ページ)。同じ「切腹」という行為に対する理解が、欧米と日本では正反対だったと言ってよいでしょう。このことは、異文化ギャップを埋めるのが、そう簡単ではないことを示唆しています。
『日本人はなぜ切腹するのか』は、標準的な社会科学の方法が、民俗学の分野にも活用されていることや「切腹」に関する興味深い事実を私に教えてくれる、知的刺激に満ちた研究書でした。
私は、「切腹」という苦痛に満ちた行為で自らの命を断つことについて、前々から不思議に思っていました。人間が合理的存在であるならば、「自殺」する場合、一般的には、なるべく苦しまない方法をとるはずでしょう。しかしながら、「切腹」は、わざわざ筆舌に尽くしがたい痛みを伴うやり方により、自害する行動なのです。明らかに、人間営為の逸脱事例でしょう。では、なぜ、「日本人」はそうようなことをするのか。その理由は何なのか。
千葉徳爾氏の『日本人はなぜ切腹するのか』(東京堂出版、1994年)は、このパズルに挑戦して、説得的な答えを導き出しています。

千葉氏の仮説はこうです。「ヒトが自分の真の心持を他に示そうとする具体的手段として、切腹という形式が発生し(日本で)伝承された」(221ページ)というものです。そして筆者は、この仮説を民俗学の知見と資料を駆使して、実証しようとしています。「これを事実にもとづいて証明しなければ科学とはいえない」と(142ページ)。つまり、本書は、日本人の切腹という行為を科学的に解明しようとした労作なのです。
本書によれば、日本人の「切腹」とは、単なる「自殺」の手段ではなく、自らの「名誉」や「節操」を守る「潔白証明」の方法だということです。すなわち、「日本人たちの解剖学的知識では、獣やヒトの内蔵は生命と精神との源泉であり、それを資格によって検討することが自他ともに本心・誠意を確認しあう手段と考えらた。そのためには腹腔を切開することが是非とも必要であ(る)…日本人の責任のとりかたの基本となるのは、このような思考法といえる」(142ページ)ということです。確かに、腸には神経伝達物質セロトニンの約90%が集中していると言われており、「第2の脳」と形容されることさえありますので、この思考は、単なる「妄想」でもないと言えるでしょう。
なお、本書を読んで驚いたことが、いくつかありました。全ては、私のは浅学によるのですが、それからは以下の通りです。
第1に、腹を刃物で横一文字に切ることは、解剖学的に、腹部の弾力や腹筋の抵抗などがあるため、そう簡単なことではない、ということです(同書、28-32ページ)。くわえて、「切腹は(大血管が通っていないため)それのみで直ちに出血死に至ることは稀」(34ページ)なのです。切腹のみでの死亡率は、わずか4%というデータも示されています(36ページ)。この事実は、多くの人達が抱く「切腹」のステレオタイプ的イメージとは、大きく異なるのではないでしょうか。
第2に、「切腹」の異文化理解に対する含意です。「切腹」は、欧米人にとって日本民族の「残虐さのシンボル」であった一方、日本人にとって「いさぎよさのシンボル」でした(156-157ページ)。同じ「切腹」という行為に対する理解が、欧米と日本では正反対だったと言ってよいでしょう。このことは、異文化ギャップを埋めるのが、そう簡単ではないことを示唆しています。
『日本人はなぜ切腹するのか』は、標準的な社会科学の方法が、民俗学の分野にも活用されていることや「切腹」に関する興味深い事実を私に教えてくれる、知的刺激に満ちた研究書でした。