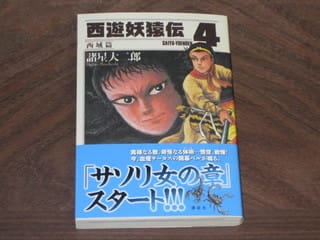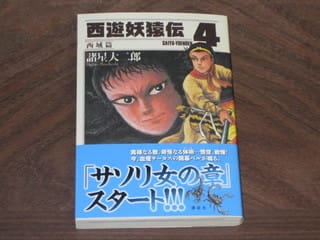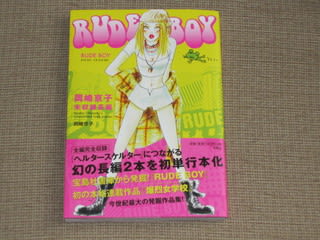朝6時集合、乗馬である。
ちなみに9時から仕事はある。でも、世のサラリーマン諸氏にしたって、自分の選んだ運動(たとえばマラソン)するために、出勤前とか帰宅してからとか、時間を見つけて・作って、やってるんで、フツーのことである。
しかし、私はといえば、3週間もサボッてしまった。「夏は、子どもたちにお任せ」とか言って。
さすがに、そろそろ行かないと、長靴にカビがはえてるといけないと思って、出かけてった。(カビはなかったけど、クモの巣みたいなのは付いてたよ、トホホ。)
さあ、さあ、気温が上がる前に、すこしでも早く乗り始めるよ。
小学生チームの部班の二番手がいいかもなあ、とか考えてたんだけど、単独でアールディスタンスに乗れって。

アールディスタンスに乗るのは、二度目だ。
前回は、先生が準備運動さんざしたあとに、ちょこっと乗せてもらって、障害を軽く飛んだだけ。
最初っから乗るのは初めて。どんな馬だっけぇ?
それはそうと、6月に入ってからだっけ、障害飛んだりしてるときに、人馬転倒して、ケガしたんだよね。(後ヒザに「穴」が開いた。)
すげえ心配したんだけど、どうにか治ったみたい。
で、ケガの功名とか言ったらイケナイんだろうけど、なんかその後から、以前よりおとなしくなったような気がする。

はい、馬装して、さっさと乗るよ。(置いてあったから“ワンコ”つけてみたら、やっぱ要らないらしい。だよな、付けてるの見た記憶がない。)
「拍車、いらないんですか!?」って言われたけど、拍車ふだんから付けたことないし、「だいじょぶでしょ」と答えて、馬場へ入る。そんなに動いてないの見たことない・イメージないし。でも、あらら、ムチも持つの忘れちゃった。ひさびさでボケてるかな。でも、ほら、俺、こないだ北海道で、道具なんもナシでも、馬乗れたし。
馬場に入って常歩。
アールディスタンスに関しては、初めて会ったのが3歳のときだったってのもあるけど、なんか子供っぽいってイメージをずっと持ってた。だから、何するかわかんないかもって、ちょっと用心してたんだけど、ところがこれが全然普通。
柵の外に置いてあるブロックの群れを見て、ちょっとよけるようなとこはあるけど、あとは堂々としたもの。ビクビクしたりしてないよ、なんだ、立派な乗馬ぢゃない。
さて、安心してひさびさの練習をするとしますか。えーと、チェックポイントは少ないほうがいい、骨盤を垂直に、太腿を鞍にくっつけての2点だな。そして、出来たら、ヒザと爪先を進行方向に、と。
んぢゃ、速歩すっか。あれ?なんかイマイチ動かない。
しばらくやってみたけど、あらら、こりゃあダメだ、動いてくんないよ。バシバシ脚入れてるうちに、こっちが疲れてきちゃった。当然、チェックポイントなんかは、ぜーんぶ頭んなかからスッ飛んでる。
申し訳ないけど、先生にムチ持ってきてもらって、仕切り直し。
それでもシャキっとしてくんないから、脚のうしろにムチ入れてみる。けっこうズルいのかな、こやつ?
乗馬ってのは、馬が前に動いてくんないと、何もできない。やがて駈歩に移行して、いろいろやってみるけど、油断するとサボられちゃう。うりゃ!ってやりたいけど、こっちが疲れてきちゃった、久々だから?暑いから?
いつものように、輪乗りでうけたり伸ばしたりをしようとする。前に出すだけで精いっぱいだけどね。
右手前のほうが、すこーし内に向きにくいかな。
「外逃がさないで。馬はすぐ逃げるとこ探してる」
言われて、ハミうけさせて、内方の脚を外の拳にぶつけるよーにって思う。思うのと、できるのは、違うけど。
輪乗りで内に入ってきたり外へふくらんぢゃったりとか、こっちのいうこときいてくれないで逃げようとする馬への対処は、ただひとつ。正しい姿勢を要求して、それができたらプレッシャーをオフにしてあげる。
イヤだってワガママいうよりも、乗ってる人の指示に従えば、早くラクになれる、おまけに誉めてもらえる、ってことがわかれば馬はいうことをきく。…理屈ぢゃ分かってんだけど、実行すんのは簡単ぢゃないよぉ~。
ときどきイイ格好になるんだけど、油断するとすぐ崩れちゃう。
私のわずかな緩みを先生は見逃さない。
「ほら、肩が外へ行っちゃう。いま(フラットワークの段階で、回転が少しでも外へ)逃がしちゃうと、障害飛ぶときに逃げるようになる!」
乗馬練習ってのは、ただ単に、私個人の運動不足解消とか騎乗技術の訓練だけぢゃない。馬の調教って言ったらおこがましいかもしれないけど、練習によって人馬の関係を正しく保つということは、どんなレベルの騎乗者でも心掛けなきゃいけない。
今日私がいい加減に四角い輪乗りをすることによって、「人のいうことなんかきかなくていーんだ」って思っちゃった馬が、あした障害練習をしようとする人に迷惑をかけるかもしれない。
そのへん、毎日の積み重ねなんである。自分だけが適当に乗れればいいってものぢゃない。
それはそうと、あれこれやってたら、マジでバテてきてしまった。
息があがっちゃうんで、呼吸を意識する代わりに、例によって「もうちょっと内を向くよ」とか「はい、外のカベ、カベ」とか、声を出したりしてんだけど(人間しゃべると自然に呼吸するものです)、ダメ、汗はダクダクだし苦しくなってくる。
私が前に出せないし、前に出ても受けられないしで、ラチがあかないので、しばし先生に乗り代わり。
降りたら、マジでヤバイ感じ。呼吸が荒いなんてもんぢゃない。息継ぎできないで25メートル泳いだような状態だ。
ふだん、そんなことしないんだけど、保護ベストの前をあけて、ヘルメットも脱いぢゃう、熱いんだもん。
先生が横木またいでるのを見てるうちに息も入ってきたので、再度騎乗。
一周目は速歩だけど、そのあとは駈歩を出して、40センチくらいの高さにした横木を飛ぶ。
馬を前に出して、手を前に置く。身体を起こすからって、手まで引っ張ってこない。手を前に置くからって、身体を前に倒さない。
先飛び厳禁なので、駈歩に坐ってジッと待つ。最後の一歩だけ、手を譲る。
何度も繰り返し。アールディスタンスは、思ったより、逃げたりしない。止まるそぶりもない、待ってれば飛ぶ。これはどうかなって思ったときでも、ポッコンと飛んでくれる。馬が上がってくるのを待ってるのは楽しい。
左右の手前でやってると、右手前のときのほうが、飛んだあととかに外(左)に張りだしちゃうことが多い。内の手綱を引っ張るだけぢゃ解決しないので、左右の手綱を同じように短く持って、脚と拳のなかに馬がいるように頑張る。(でも逃げられる。)

この位置に馬のアタマ・クビをキープしなきゃ。
でも、ときどきアタマあげられちゃうんだよな。そのとき手をジタバタするんぢゃなくて、前に踏み込ませないと解決しないんだよな、きっと。
ふぅ、クタクタでクラクラになっちゃったけど、練習おわり。
私もバテバテだけど、がんばってくれた馬も汗びっしょりなんで洗う。
手入れ終わったあとは、今シーズン初の、梨をやってみる。

でも、予想どおり、喜んで食わないし、アールディスタンス。
ま、もともとこいつはリンゴも最初のうちは食わなかったし。食べ慣れないものはヤなんだろう。
そーゆーわけで、梨はオリーにやってみる。

もちろん、なんでも食うよ、オリアンダーは。(←少年団の手入れのジャマをする悪いオッサン。)
オリーのほかには、チョコレート・ホセカレーラス・ウィスパーなんかにやってみる。やっぱ予想どおり、なんでも食うんだ、こいつらは。(かわいい)
それにしても、手入れとかしてても、落ち着いた感じになったな、アールディスタンス。
でも、ケガして痛い目にあったからぢゃないかもしんない。
誰とは言わないけど、SアトルUとかも、引っ越したあと、なんか落ち着いた雰囲気になってる。
全体に、引っ越したあと、練習中に馬が飛んだり跳ねたりしての落馬が減ってるって話も聞く。
もしかしたら、馬房が「対面」になったことが作用してるのかもしれない。