佐野真 2005年 講談社現代新書
野球の本を、もう少し何かなかったっけ、って探してたら、あった、あった。
これはけっこういいです、ソフトバンクの和田毅投手のピッチングについて書いてある本。
タイトルにあるとおり、和田がすごい凄いって言うんぢゃなくて、打てそうで打てないのは何故だろうってとこをテーマにしてる。
和田のストレートは、プロにあっては、ずばぬけて速い部類には入らなくて、スピードでいえば140キロそこそこ。
だけど、変化球で勝負するんぢゃなくて、そのストレートが打たれない、凡打に打ち取るどころか、三振がとれる。
それは高校生のときからそうで、120キロ台のストレートを相手は150キロに見えたと言っていた。
大学1年のとき、いいボールだと思ったら129キロで、自身愕然としたらしいが、その後コーチとフォーム改造に取り組んだら、2ヵ月で142キロが出たっていう大きな進歩はあったけど、でも、それよりやっぱり“速く見える”というところに特性がある。
対戦相手は、他校の150キロを投げるピッチャーより速く見えたと言っているし、結局、大学の4年間では、江川の記録を塗り替える476三振を奪っている。
高校から大学、プロ、そしてオリンピックで対戦した外国のナショナルチームまで、すべての証言をまとめると、「バッターからみると、計測した球速以上の速さに見える」「ストレートとわかっていても打てない」「体感的に加速する感じ・見たことがない球」などなどとなる。結果、数字としてはそんなに速くないストレートを、みんなボールの下を空振りしている。
こういう不思議なピッチャーなんだが、その秘密はなんなのか。
結論としては、投げたときの初速と終速の差が、ほかのピッチャーより小さい。プロで平均がその差10キロとしたら、和田は4,5キロらしいから、それが「切れ」のあるストレートだという。
ちなみに、初速と終速の差が小さいことを「切れ」と呼んでるんだけど、私の考えというか表現は、ちょっと違う。ふつうの(普通とは何だと言われそうだけど)イメージと差があることを、キレと表現すべきだと思う。たしかにストレートに関しては他人よりスピードが落ちないことだし、変化球に関しては、通常経験的に予測しているより変化することがキレだと思うから。
で、和田に関しては、どうして初速と終速の差が少ないボールを投げているかというと、ボールにかかるバックスピンがひとより多い、プロの平均が毎秒30回転程度、レッドソックスの松坂が38回転なんだけど、和田のはおそらくそれ以上だと推測している。
ここで実測してないのが本書の唯一欠けているところ。40回転くらい行ってるんではと推測してるんだけど、そこは是非証明してほしかった。ただし、傍証としては、和田は被本塁打が多い(回転が多くて、打たれるとボールが飛ぶ=軽い球質)ということを挙げているし、推測は外れていないとは思うけど。(被安打率はトップクラスの少なさなのに、ホームラン打たれやすいのは何か原因がある。)
ピッチングの分析だけぢゃない本書の魅力は、和田自身の投球や野球に対する考えがインタビューされているところで。
たとえば、和田の打ちにくさについて「腕の振りが変則で、ボールの出どこが見えにくいからだ」という意見もあるんだけど、和田自身は「それが原因だったら自分に好不調はないはずだ」と反論している。
非常に論理的であってクレバー、すべてに計画性があって、自己管理能力に長けている、そういうピッチャーの話だから、ただ単に投げているボールが偶然打ちにくいってわけぢゃなくて、面白い。(プロ野球に進むとき、親会社が危なそうなのに当時のダイエーホークスを選んだのは、DH制のあるほうが交代させられにくいし、自チームの打撃が強いほうが勝ちやすいってのがあったのではと大学の監督は言ってる。)
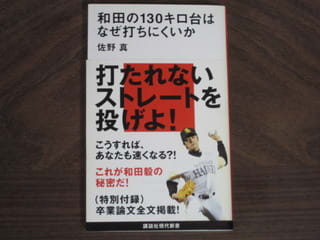
野球の本を、もう少し何かなかったっけ、って探してたら、あった、あった。
これはけっこういいです、ソフトバンクの和田毅投手のピッチングについて書いてある本。
タイトルにあるとおり、和田がすごい凄いって言うんぢゃなくて、打てそうで打てないのは何故だろうってとこをテーマにしてる。
和田のストレートは、プロにあっては、ずばぬけて速い部類には入らなくて、スピードでいえば140キロそこそこ。
だけど、変化球で勝負するんぢゃなくて、そのストレートが打たれない、凡打に打ち取るどころか、三振がとれる。
それは高校生のときからそうで、120キロ台のストレートを相手は150キロに見えたと言っていた。
大学1年のとき、いいボールだと思ったら129キロで、自身愕然としたらしいが、その後コーチとフォーム改造に取り組んだら、2ヵ月で142キロが出たっていう大きな進歩はあったけど、でも、それよりやっぱり“速く見える”というところに特性がある。
対戦相手は、他校の150キロを投げるピッチャーより速く見えたと言っているし、結局、大学の4年間では、江川の記録を塗り替える476三振を奪っている。
高校から大学、プロ、そしてオリンピックで対戦した外国のナショナルチームまで、すべての証言をまとめると、「バッターからみると、計測した球速以上の速さに見える」「ストレートとわかっていても打てない」「体感的に加速する感じ・見たことがない球」などなどとなる。結果、数字としてはそんなに速くないストレートを、みんなボールの下を空振りしている。
こういう不思議なピッチャーなんだが、その秘密はなんなのか。
結論としては、投げたときの初速と終速の差が、ほかのピッチャーより小さい。プロで平均がその差10キロとしたら、和田は4,5キロらしいから、それが「切れ」のあるストレートだという。
ちなみに、初速と終速の差が小さいことを「切れ」と呼んでるんだけど、私の考えというか表現は、ちょっと違う。ふつうの(普通とは何だと言われそうだけど)イメージと差があることを、キレと表現すべきだと思う。たしかにストレートに関しては他人よりスピードが落ちないことだし、変化球に関しては、通常経験的に予測しているより変化することがキレだと思うから。
で、和田に関しては、どうして初速と終速の差が少ないボールを投げているかというと、ボールにかかるバックスピンがひとより多い、プロの平均が毎秒30回転程度、レッドソックスの松坂が38回転なんだけど、和田のはおそらくそれ以上だと推測している。
ここで実測してないのが本書の唯一欠けているところ。40回転くらい行ってるんではと推測してるんだけど、そこは是非証明してほしかった。ただし、傍証としては、和田は被本塁打が多い(回転が多くて、打たれるとボールが飛ぶ=軽い球質)ということを挙げているし、推測は外れていないとは思うけど。(被安打率はトップクラスの少なさなのに、ホームラン打たれやすいのは何か原因がある。)
ピッチングの分析だけぢゃない本書の魅力は、和田自身の投球や野球に対する考えがインタビューされているところで。
たとえば、和田の打ちにくさについて「腕の振りが変則で、ボールの出どこが見えにくいからだ」という意見もあるんだけど、和田自身は「それが原因だったら自分に好不調はないはずだ」と反論している。
非常に論理的であってクレバー、すべてに計画性があって、自己管理能力に長けている、そういうピッチャーの話だから、ただ単に投げているボールが偶然打ちにくいってわけぢゃなくて、面白い。(プロ野球に進むとき、親会社が危なそうなのに当時のダイエーホークスを選んだのは、DH制のあるほうが交代させられにくいし、自チームの打撃が強いほうが勝ちやすいってのがあったのではと大学の監督は言ってる。)
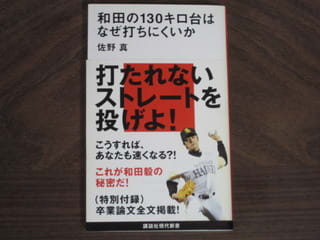











 )
)

 身体のあちこちに傷をこしらえちゃって、しばらく休んでた。
身体のあちこちに傷をこしらえちゃって、しばらく休んでた。 って、先生が勉強になるって、シロウトレベルにはチンプンカンプンなんぢゃないの?と思いつつ乗る。
って、先生が勉強になるって、シロウトレベルにはチンプンカンプンなんぢゃないの?と思いつつ乗る。
 なんか違うのがわかった。ヒジを体側につけるとき、私のは、どっちかっていうと前に出て伸びてるヒジを、後ろに引くようにして身体にくっつけるんだけど、それだと引っ張られたとき、また同じこと。肩甲骨をくっつけるようにして、横からグッとくっつける形をとらないと。
なんか違うのがわかった。ヒジを体側につけるとき、私のは、どっちかっていうと前に出て伸びてるヒジを、後ろに引くようにして身体にくっつけるんだけど、それだと引っ張られたとき、また同じこと。肩甲骨をくっつけるようにして、横からグッとくっつける形をとらないと。








