この本の 「はじめに」 に書かれていることからもう少し、引用します。
「敗者の立場で古代史を読み直すことは、さまざまな地域の隠された歴史を
掘り起こすことになるかもしれない。それとその地域の人びとに勇気をあた
えることができるだろう。」
この例が昨日記した1985年のイワイのシンポジウムの例なのですが、本文
にも書かれていますので紹介しておきます。
このシンポジウムが終わったあと八女市の青年約十人が、 “これで長年の胸
の閊(つかえ)がとれました” と喜んでくれた。 これは昨日も紹介したことで重複
しますが、続けます。
「八女市には~磐井の墓とみてよい岩戸山(いわとやま)古墳がある。江戸時
代の末に尊皇運動が盛んになりだすと、八女市とその周辺にあった磐井関係の
遺跡が傷つけられたり、その土地の人が逆賊磐井の子孫として白い目で見られ
だしたという。そのような差別の原因が今回のシンポジムウで晴れたといってく
れた。」
継体・磐井戦争は6世紀・約1500年前の出来事ですが、 『日本書紀』 に
「磐井が陰(ひそか)に叛逆」 と記載されていることを鵜呑みにして(森さんの
弁)の歴史用語として「磐井の乱」 「磐井の反乱」 が用いられ、江戸末期から
シンポジウム開催まで130年余り、その地域の人びとの精神の閊えとなって
きたということには驚かされます。
そして、森さんの提案 “磐井の反乱とか乱はやめよう。磐井戦争にしましょ
う” 、磐井の乱でなく磐井戦争、たったそれだけのことが、その地域の青年の
精神を解放したのでした。
その2 にあたる話も “考古学は地域に勇気をあたえる” の例です。
昭和49(1974)年4月に福岡県鳥栖市で吉野ヶ里遺跡のシンポジウ
ムが開かれました。
「この当時、なぜか九州人は東京や大阪にコンプレックスをもっていて、
それが古代史の解釈にも反映していた。 しかも九州島のなかでも福岡
が優越感をもって佐賀や熊本などを見下す傾向が感じられた。その佐賀
で吉野ヶ里遺跡が急浮上したのだから影響は大きい。」
そのシンポジウムの司会をしていた森さんが、閉会にさいして咄嗟に口
から出てしまった言葉が “考古学は地域に勇気をあたえる” でした。 大
観衆の熱気にうたれたためだそうです。











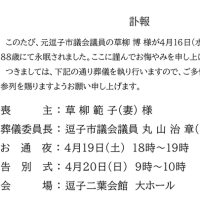



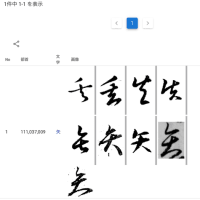




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます