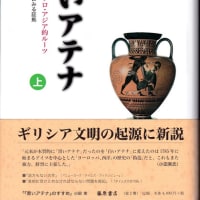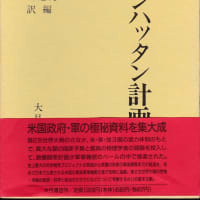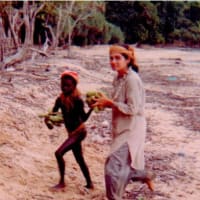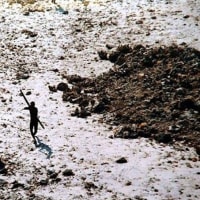▲ 『現代思想2015年10月臨時増刊 総特集 鶴見俊輔』 青土社 定価1500円+税
『現代思想2015年10月臨時増刊 総特集 鶴見俊輔』
かつて筑摩書房で出していたのだが、1960年ー1970年代に元気だった『展望』という雑誌があった。毎月購読していたわけではないが、そこには、小説あり、エッセーあり、批評あり、哲学思想論文あり、書評ありと、それほど厚いボリュームではなかったのだが、穏やかな、リベラル色のある総合雑誌だった。
鶴見俊輔さんは、自前で『思想の科学』を出していたので、書いたものは、必ずしも総合雑誌に掲載していたものではないが、筑摩書房の『現代思想大系』や、『近代思想大系』の編者であったこともあって私は筑摩文化人の人脈の人という印象があった。
けれども、今手元にある久野収・鶴見俊輔・藤田省三らの『戦後日本の思想』は、はじめ中央公論に掲載されているし、最初にまとめられて発行したのも中央公論社である。1950年代後半頃までの中央公論は、現在の政府系御用雑誌のような雰囲気ではなく、まっとうな総合雑誌だったのではないだろうか。風流夢譚事件、『思想の科学』特集号回収事件など、およそ1960年の安保闘争頃から、編集方針が変化しはじめ、1980年代以降のバブル期を経た後では、批判精神も薄れ、現状追認の雑誌に堕してしまっているのだが。
『試行』の吉本隆明のような、相手を罵倒する論争家でもなく、どこまでも対話の妙味に生きる、寛容の思想家であったので、1970年頃の血気盛んな青年には、全く見向きもされなかったのだが。それは、高橋源一郎も反省を込めて語っていた。
権力への抵抗は、美的に玉砕するのが目的ではない以上、100年粘れる抵抗の思想と、市民革命の展望を紡ぎ出すには鶴見俊輔を味わい尽くすことじゃないだろうか。
1960年の安保闘争の頃の「声なき声の会」などは、国会を取り巻く、市民のか細い声を結び合わせ、決して絶望はしない驚くべき継続性を絶やすことなく保ち続けている。
ついに、2015年、安倍政権の凶暴な政治に対して、物言う老若男女の横断的な運動体がゆるやかに、しかも、断固として生まれつつあるようだ。保守政治は驕り極まって、自らの墓穴を掘りだしたのだ。
鶴見俊輔さんは、ここ数日の国会を取り巻く、非暴力的な、創意溢れる政府批判の連帯の表明を見ることができなかったのだが、「声なき声の会」、「ベ平連」などの息の長い活動の思いは、彼らに確実に引き継がれたのではないだろうか。

▲『現代思想2015年10月臨時増刊 総特集 鶴見俊輔』 青土社 定価1500円+税
▼目次


▲ 目次
つづく