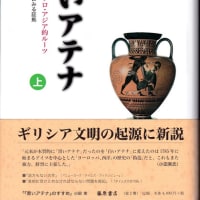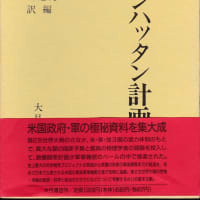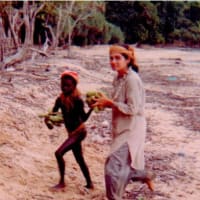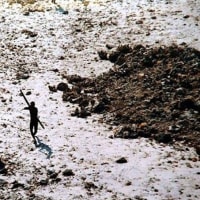▲ 岩波講座日本歴史 戦後に刊行された3つの企画 左から第1次、第2次、第3次

▲左から第1次、第2次、第3次の岩波講座日本歴史 の背
リアルタイムで買ったのは第2次の1975年の刊行のときから、この時も、最初は全巻購入にはいたらず、必要な古代史の巻と、別巻。全巻は1980年代になってから。ようやく予約注文ができたのは、第3次の「日本通史」の企画からである。
第2次と第3次の岩波講座日本史の間に、岩波書店では『日本の社会史』全8巻の企画があり。従来の時代区分から離れた、贈与の問題を扱う巻があったりと、日本史の取り組み方にも新しい方法が模索された時代があった。
これが第3次の岩波講座日本史企画の際にもあったのか、従来の通時的な総括的な論文から離れた特論などに見るべきものがあったように思う。ところが、地方史などを書いている研究者の間には意外と不評だったのだ。曰く、「その時代の全体が見えない」という声を聞くことが多かった。それはなぜなのだろう。
ところで、「その時代のぜんたい」というのは、なんのことだろう?だれがそれを決めるのだろう。あるいは、その時代のぜんたいというのはあるのか?
「手っ取り早く、時代の一般的解釈の標準を期待する暗黙の同意」というか、歴史の理解に対する方法的自覚を欠いたまま、その基準に自分がコミットすることを避け、時代の趨勢の流れについていき、「自分が集めた史料の解釈にその時代に勢いのある解釈の味付けをする」 という雰囲気。が地方史に蔓延していた。それに自分はどう対処してきた?と言うと忸怩たるものがあるなぁ。
日本史研究者には、他の学問にある「方法的自覚」「解釈に対する根拠の提起の理論的意識の欠如」を指摘されてから久しい。
すでに、第3次岩波講座「日本通史」の「別巻1」は『歴史意識の現在』という巻を用意し、その苦渋に満ちた問いを発していたのだが。
今度の4次企画には、その「歴史意識の現在」という視点から、歴史意識の未来に向けて、さらに方法的自覚に磨きをかけて、各自論説を展望しているだろうか。
岩波書店の第4次日本史講座企画の案内に
「原始・古代から現代まで,政治体制を中心に,それを支えた経済・社会構造,宗教・文化等の大きな流れを描き出す.学界の第一線研究者の総力を結集」
とあったのだが。
これはぜんたいという言葉は使用していないが、
「政治体制を中心」に、「大きな流れを描きだす」ということばに置き換えられているのだが、岩波第3次講座にあった「歴史意識の現在」という問いからはやや後退しているようにみえるのだが。
岩波の講座日本史の刊行は20年間単位のインターバルがあるので、20年後の次の機会に巡り会うチャンスである「歴史意識の現在」を 問う意識・主体である私 がもはや地上に存在していない可能性も念頭におくと、
これから、栞を挟んで、長期間・長時間、読書を中断しておくわけにもいかなくなってきたなぁ。
というわけで、
昨日、12月11日、第4次岩波講座『日本歴史』の予約を本屋に頼んだのだった。
定価は3200円+税 来年春、税が上がると1冊3360円では済まなくなるわけだ。現役の間は、講座や叢書類も複数ダブりで購入することもできたが、乏しい現在の年金生活では、企画ものの講座・叢書を複数以上予約することは御法度。これからほぼ2年間は、企画ものが買えないなぁ。そうこうするうちに『古墳時代の考古学』もかなりの巻がでてきた。浦島太郎にならないうちに読まなければ!と思いつつ。もう特定の分野では原人クラスというか、発言すると「自爆●●」といわれかねない発言も飛び出しそうなので、うっかり研究会や学会などというところに顔も出せなくなってしまったぞ。

▲第1次岩波講座日本歴史 全23巻 1962年~1964
戦後の独立回復後の約10年の成果を盛り込んだシリーズ第一弾
このシリーズは、大当たりだったようだ、私が持っているものは3次予約募集のときのもの1967年~
1975年から第2次の岩波講座がでるまで息の長い寿命があり、後からでる論文でも引用される機会も多く、私も別の論文で、引用されているので、この本に戻って頁をめくることが多かった。
下の論文タイトルにあるように、今から考えれば、大雑把な編成に見えるが、各論者、自由に隣接諸分野に越境して論じていた。今は、他の専門分野の批判を恐れて、自分の専門領域を必死に守っている雰囲気。


▲ 第2次 岩波講座 日本歴史 全26巻 1975年~1977 定価1800円

▲ 第3次 岩波講座 日本通史 21巻+別巻4巻 全25巻 1993年~1996 本体2718円 定価2800円

▲ 第1巻は日本列島と人類社会 と題する巻
総論を網野善彦 が「日本列島とその周辺ー「日本論」の現在」
この巻は、歴史学者ではなく、生態学、人類学、文化人類学、民族学、言語学、神話学などからのアプローチを据える。
網野善彦ほかの、当時の「列島から日本史を考える」という視角が強くでている。
また、別巻1が「歴史意識の現在」というタイトルで2つのテーマを設けて、これまでにない、方法の反省をこめて、巻を編集しているのが大きな特徴である。

▲第3次岩波講座日本史別巻1の「歴史意識の現在」の執筆者 1995年10月
従来の日本史専門領域では寄稿しない顔ぶれが見られる。この巻はよかった。
今回の第4次岩波講座には こんな、規格外の企画はあるのだろうか。ぜひとも注目したい分野である。

▲ 第3次岩波講座 日本通史 第2巻 1993
この巻は従来通りの古代編
総論的な巻頭の「通史」を鬼頭清明が「六世紀までの日本列島 ー倭国の成立」
論説が5本、文化論 を白石太一郎
特論として3本


▲ 歴史学研究会・日本史研究会 編 『日本史講座』 2004年5月 東京大学出版会
歴史学研究会・日本史研究会 編の講座ものは 以前は 「講座日本史」というシリーズで、戦後何回もでている。1984年頃にも出しているはず。整理が悪く、今みつからないので後日掲載する。岩波講座は20年に1回版を改め、刊行しているのだが、東京大学出版会からのものも、岩波書店の間の時期をねらって、その間に出版されている。10巻構成前後で、値段もソフトカバーの体裁で、読みやすく手頃な価格なので、岩波書店の購読者よりも数は多いのではないだろうか。岩波講座の論文が少し古びてきたなあと思う頃、こちらの講座で新知見や・新資料を使って論文を出してくる。また、歴史学研究会は西洋史学や、アジア学の研究者も集まっているので、かつては左翼色が濃厚な時代もあったが、今では歴史学の研究方法をめぐる特集も組むなどしている。日本史専門の史学意識からずれた意識が、日本史研究を活性化すると思うので、この歴史学研究会・日本史研究会 編 『日本史講座』 もみのがせない。

▲ 歴史学研究会・日本史研究会 編 『日本史講座』 2004年5月 東京大学出版会 1巻の執筆者・論文タイトル
今回の岩波講座 日本史 の執筆者といくらかだぶりがある。10年前の出版から、さらに新発見の資料も相次いでいる古代史分野は、前回岩波講座 日本通史や『列島の古代史』以後、どんな、研究が語られるのか。
また「歴史意識の現在の視点」がどう構想されているのか、期待することにしよう。
以下は、岩波書店のホームページから


▲岩波講座 『日本歴史』 全22巻の装幀 第1巻は11月19日に出版された。
岩波講座 日本歴史
■構成 全22巻
大津 透,桜井 英治,藤井 譲治,
吉田 裕,李 成市 編集委員
前講座の刊行から20年.この間,日本のあり方も世界におけるその位置も大きく変動した.いま日本はどこにいるのか,またこれからどうあるべきなのか,今こそ歴史に問い直すときである.アジアさらには世界との新たな関係を意識しながら,原始・古代から現代まで,政治体制を中心に,それを支えた経済・社会構造,宗教・文化等の大きな流れを描き出す.学界の第一線研究者の総力を結集.
■体裁=A5判・上製・函入・318頁
■定価 3,360円(本体 3,200円 + 税5%)[予約出版(分売不可)]
■2013年11月19日
■ISBN978-4-00-011321-2 C0321
古くは,大陸につながる古北海道半島,本州から九州までが連なる古本州島と島嶼部琉球によって構成された日本列島.気候や自然環境の大きな変動を経て人びとが暮らしはじめた旧石器時代から5―6世紀倭国まで,朝鮮半島・中国大陸とのかかわりのなかで形づくられていった列島の古代を,最新の研究成果をふまえて描く.
2014年2月28日予約締切

▲ 原始・古代1
古代1
1 古代史への招待 大津 透
2 日本列島の成立と狩猟採集の社会 (東京大学)佐藤宏之
3 縄文時代から弥生時代へ (東京大学)設楽博己
4 東アジアにおける弥生文化 (九州大学)岩永省三
5 倭国の成立と東アジア (国立歴史民俗博物館)仁藤敦史
6 前方後円墳の成立 (大阪大学)福永伸哉
7 古墳時代の社会と豪族 (京都府立大学)菱田哲郎
8 倭の五王と列島支配 (関東学院大学)田中史生
9 朝鮮三国の国家形成と倭 (滋賀県立大学)田中俊明
古代2
1 大王の朝廷と推古朝 (国際日本文化研究センター)倉本一宏
2 大王とウヂ (同志社大学)北 康宏
3 国造制と屯倉制 (東洋大学)森 公章
4 帰化人と古代国家・文化の形成 (愛知県立大学)丸山裕美子
5 飛鳥の都と古墳の終末 (奈良文化財研究所)小澤 毅
6 飛鳥・白鳳文化 (早稲田大学)川尻秋生
7 6-8世紀の東アジアと東アジア世界論 李成市
8 大化改新と改新の実像 (大阪大学)市 大樹
9 記紀神話と王権の祭祀 (宮内庁正倉院事務所)佐々田悠
古代3
1 律令制の形成 (九州大学)坂上康俊
2 奈良時代の政治過程 (鹿児島大学)虎尾達哉
3 律令官僚制と天皇 (山梨大学)大隅清陽
4 律令財政と貢納制 (国立歴史民俗博物館)武井紀子
5 平城京と貴族の生活 (奈良文化財研究所)渡辺晃宏
6 郡司と古代村落 (学習院大学)鐘江宏之
7 天平文化論 (京都大学)吉川真司
8 遣唐使の役割と変質 (工学院大学)榎本淳一
9 律令国家と仏教・神祇 (富山大学)鈴木景二
古代4
1 平安前期の王権と政治 (京都教育大学)吉江 崇
2 平安京の成立と官僚制の変質 (山口大学)橋本義則
3 地方支配の変化と天慶の乱 (愛媛大学)寺内 浩
4 律令国家と夷狄 (近畿大学)鈴木拓也
5 古代国家の軍事組織とその変質 (工学院大学)吉永匡史
6 古代の土地制度 (文部科学省)三谷芳幸
7 古代の生産と流通 (山形大学)三上喜孝
8 古代の家族と女性 (岡山大学)今津勝紀
9 平安新仏教と東アジア (東北大学)堀 裕
古代5
1 摂関政治と政治構造 (法政大学)春名宏昭
2 財政の再編と宮廷社会 大津 透
3 受領の支配と在地社会 (甲南大学)佐藤泰弘
4 平安京の展開と都市の生活 (京都府立大学)櫛木謙周
5 唐風文化から国風文化へ (関西大学)西本昌弘
6 古代の裁判と秩序 (神奈川大学)前田禎彦
7 北宋・遼の成立と日本 (愛知県立大学)上川通夫
8 平安仏教の展開と信仰 (就実大学)曾根正人
9 摂関・院政期の宗教儀礼と天皇 (奈良国立博物館)斎木涼子
中世1
1 中世史への招待 桜井英治
2 院政論 (東京大学史料編纂所)本郷恵子
3 治承・寿永の内乱と鎌倉幕府の成立 (大阪大学)川合 康
4 鎌倉幕府論 (東京大学)高橋典幸
5 荘園制と中世年貢の成立 (首都大学東京)鎌倉佐保
6 武士団と領主支配 (茨城大学)高橋 修
7 中世前期の村と百姓 (北海道教育大学)鈴木哲雄
8 鎌倉時代の仏教 (京都大学)上島 享
9 中世前期の文化 (創価大学)坂井孝一
中世2
1 モンゴル襲来と鎌倉幕府 (富山大学)熊谷隆之
2 建武政権論 (立命館大学)桃崎有一郎
3 宋・元交替と日本 (国際日本文化研究センター)榎本 渉
4 中世の交通と地域性 (東北大学)柳原敏昭
5 中世の法と裁判 (日本学術振興会)佐藤雄基
6 中世の身分と社会集団 (立命館大学)三枝暁子
7 中世の家と女性 (文部科学省)高橋秀樹
8 中世都市論 (東京大学史料編纂所)高橋慎一朗
9 中世の民衆思想 (東北大学)佐藤弘夫
中世3
1 室町幕府論 (龍谷大学)吉田賢司
2 東アジア世界の変動と日本 (北海道大学)橋本 雄
3 応仁・文明の乱 (東京大学史料編纂所)末柄 豊
4 中世所有論 (福岡大学)西谷正浩
5 一揆と徳政 (京都女子大学)早島大祐
6 中世後期の貨幣と流通 (皇學館大学研究開発推進センター)千枝大志
7 室町幕府と仏教 (東京大学史料編纂所)川本慎自
8 室町時代の文化 (慶應義塾大学)小川剛生,(東京大学)高岸 輝
中世4
1 戦国の争乱 (愛知大学)山田邦明
2 国人一揆と大名家中 (島根大学)長谷川博史
3 検地と知行制 (北海道大学)平井上総
4 地域的統一権力の構想 (高知大学)市村高男
5 惣村と土豪 (専修大学)湯浅治久
6 宗教一揆 (大阪市立大学)仁木 宏
7 戦国の法と習俗 (明治大学)清水克行
8 自然環境と中世社会 (別府大学)田村憲美
9 中世の技術と労働 桜井英治
近世1
1 近世史への招待 藤井讓治
2 織田政権論 (共立女子大学)堀 新
3 豊臣政権論 (九州大学)中野 等
4 朝鮮からみた文禄・慶長の役 (仁荷大学)李啓煌
5 兵農分離と石高制 (東京大学)牧原成征
6 キリシタンと統一政権 (東京大学史料編纂所)岡美穂子
7 江戸幕府の成立と公儀 (九州産業大学)福田千鶴
8 近世都市の成立 (東京大学)伊藤 毅
9 近世の身分制 (京都大学)横田冬彦
近世2
1 江戸幕府の政治構造 (福島大学)三宅正浩
2 大名と藩 (九州大学)高野信治
3 近世の公家社会 (東京大学史料編纂所)松澤克行
4 近世の対外関係 (長崎大学)木村直樹
5 近世の村 (一橋大学)渡辺尚志
6 三都と城下町 (学習院女子大学)岩淵令治
7 近世貨幣論 藤井讓治
8 近世の仏教 (日本大学)朴澤直秀
9 江戸時代前期の社会と文化 (一橋大学)若尾政希
近世3
1 吉宗の政治 (大阪大学)村田路人
2 畿内近国論 (京都大学)岩城卓二
3 近世の蝦夷 (北海道大学)谷本晃久
4 東アジア世界のなかの琉球 (神奈川大学)渡辺美季
5 全国市場の展開 (新潟大学)原 直史
6 水運と陸運 (富山大学)深井甚三
7 近世の法 (大阪大谷大学)小倉 宗
8 儒学・国学・洋学 (愛知教育大学)前田 勉
9 近世の神道・陰陽道 (京都女子大学)梅田千尋
近世4
1 宝暦天明から寛政 (聖心女子大学)深井雅海
2 世界認識の転換 (京都大学総合博物館)岩崎奈緒子
3 藩財政改革論 (山口大学)田中誠二
4 近世の漁業・塩業・鉱業
〈漁業〉 (東京農工大学)高橋美貴
〈塩業〉 (青山学院大学)落合 功
〈鉱業〉 (高知大学)荻慎一郎
5 百姓一揆と都市騒擾 (国立歴史民俗博物館)久留島浩
6 教育社会の成立 (国立台湾大学)辻本雅史
7 芸能と文化 (お茶の水女子大学)神田由築
8 飢饉と災害 (宮城学院女子大学)菊池勇夫
近世5
1 文政・天保期の幕政 (東北大学)平川 新
2 開国と幕末の改革 (東京大学史料編纂所)保谷 徹
3 大庄屋と組合村 (関西学院大学)志村 洋
4 在来経済・産業の発展 (東京大学)谷本雅之
5 流通構造の転換 (東北学院大学)斎藤善之
6 民衆宗教の展開 (埼玉大学)井上智勝
7 近世の性 沢山美果子
8 近世後期の民衆運動 (天理大学)谷山正道
9 近世後期の政治思想 (名古屋大学)羽賀祥二
近現代1
1 近現代史への招待 吉田 裕
2 戊辰戦争と廃藩置県 (中央大学)松尾正人
3 地租改正と地域社会 (立正大学)奥田晴樹
4 殖産興業政策の展開 (明治学院大学)神山恒雄
5 地方自治制と民権運動・民衆運動 (専修大学)松沢裕作
6 北海道・沖縄・小笠原諸島と近代日本 (琉球大学)塩出浩之
――主権国家・属領統治・植民地主義
7 官僚制と軍隊 (東京大学)鈴木 淳
8 文明開化の時代 (東京大学)苅部 直
9 教化・教育政策と宗教 (京都大学)谷川 穣
近現代2
1 明治憲法体制の成立 (國學院大学)坂本一登
2 伝統文化の創造と近代天皇制 (京都大学)高木博志
3 藩閥と政党 (東京大学)五百旗頭薫
4 日清・日露戦争 (学習院大学)千葉 功
5 日本の産業革命 (東京大学)中村尚史
6 近代学校教育制度の確立と家族 (京都大学)小山静子
7 地主制の成立と農村社会 (広島修道大学)坂根嘉弘
8 軍部の成立 (明治大学)山田 朗
9 社会問題の発生 (一橋大学)石居人也
近現代3
1 韓国併合と植民地官僚制の形成 (同志社大学)小川原宏幸
2 帝国日本の形成と展開 (中京大学)浅野豊美
3 都市民衆騒擾と政党政治の発展 (創価大学)季武嘉也
4 戦間期の家族と女性 (立教大学)小野沢あかね
5 国際連盟・ワシントン体制の成立と政党内閣の時代 (中央大学)服部龍二
6 「改造」の時代 (静岡大学)黒川みどり
7 大衆文化の端緒的形成 (日本大学)大岡 聡
8 昭和恐慌と日本経済――1919-1937 (東京大学)武田晴人
9 満州事変・日中戦争の勃発と立憲政治 (首都大学東京)源川真希
近現代4
1 大政翼賛会の成立から対英米開戦まで (東京大学)加藤陽子
2 戦局の展開と国内政治 吉田 裕
3 総力戦の遂行と社会変容 (日本学術振興会)佐々木啓
4 戦時統制経済 (首都大学東京)山崎志郎
5 「大東亜共栄圏」論 (東北大学)安達宏昭
6 戦時・戦後農村の変貌 (神奈川大学)森 武麿
7 戦争と大衆文化 (関西学院大学)高岡裕之
8 象徴天皇制の形成 (都留文科大学)瀬畑 源
9 占領と戦後改革 (一橋大学)中北浩爾
近現代5
1 サンフランシスコ講和条約と日本の戦後処理 (関東学院大学)林 博史
2 アジア冷戦のなかの日米安保体制 (立命館大学)吉次公介
3 保守支配体制の構造と展開 (獨協大学)福永文夫
4 戦後日本の社会運動 (和光大学)道場親信
5 高度経済成長と日本社会の変容 (横浜国立大学)大門正克
6 冷戦後の国際社会と日本 (早稲田大学)李鍾元
7 戦後史の中の家族――その形成と変容 (大阪府立大学)田間泰子
8 新自由主義・新保守主義の台頭と日本政治 (都留文科大学)菊池信輝
9 メディア社会・消費社会と大衆文化 (京都大学)伊藤公雄
地域編 テーマ巻1
序論――境界・接触領域・交流 李成市
1 古代北海道地域論 (苫小牧駒澤大学)蓑島栄紀
2 韓国木簡論――漢字文化の伝播と受容 (早稲田大学)橋本 繁
3 接触領域としての古代平泉 (岩手大学)樋口知志
4 東アジア海域論 (神戸女子大学)山内晋次
5 中世・近世アイヌ論 (函館工業高等専門学校)中村和之
6 対馬――外交・通商における接触領域 (産業能率大学)木村直也
7 近世琉球王国と東アジア交流 (東京大学総合研究博物館)石井龍太
8 漂流と送還 (名古屋大学)池内 敏
9 東アジアにおける雑居と居留地・租界 (仁荷大学)朴俊炯
10 環日本海交通圏 (新潟大学)芳井研一
11 移民と遠隔地ナショナリズム (法政大学)今泉裕美子
12 近代日本における国籍と戸籍 (早稲田大学)遠藤正敬
13 海外神社論――大日本帝国と地域秩序の編成 (國學院大学)菅 浩二
史料編 テーマ巻2
序論 大津 透
1 木簡史料論 (東京大学)佐藤 信
2 正倉院文書と古代史料学 (東京大学史料編纂所)山口英男
3 国史の編纂 (活水女子大学)細井浩志
4 中世史料学の現在 (国立歴史民俗博物館)高橋一樹
5 中世史と考古学 (同志社女子大学)山田邦和
6 図像資料論 (東京大学史料編纂所)藤原重雄
7 近世史料と調査論 (静岡文化芸術大学)西田かほる
8 文庫論 (東京大学史料編纂所)田島 公
9 アーカイブズと歴史学 (学習院大学)保坂裕興
10 オーラル・ヒストリーの切り拓いたもの (上智大学)蘭 信三
11 近現代展示論 (神奈川大学)安田常雄
12 歴史資料の保全と活用――大規模災害と歴史学 (神戸大学)奥村 弘
歴史学の現在 テーマ巻3
序論 李成市
1 文明史からみた日本史 (成均館大学)宮嶋博史
2 東アジア世界論と日本史 李成市
3 近世論から見たグローバルヒストリー (京都大学)永井 和
4 植民地と歴史学 (京都大学)吉井秀夫
5 マルクス主義と日本史学 (東京経済大学)戸邉秀明
6 社会史の成果と課題 (元静岡文化芸術大学)山本幸司
7 女性史/ジェンダー史 (日本女子大学)成田龍一
――近現代日本の領域を軸に
8 国民国家論と日本史 (小樽商科大学)今西 一
9 国境を越える日本史学 (東京大学)三谷 博
10 教科書訴訟・教科書問題と現代歴史学 (信州大学)大串潤児
日本史研究者には、他の学問にある 「方法的自覚」 「解釈に対する根拠の提起の理論的意識の欠如」を指摘されてから久しい。
すでに、第3次岩波講座「日本通史」の「別巻1」は『歴史意識の現在』という巻を用意し、その苦渋に満ちた問いを発していたのだが。
今度の4次企画には、その「歴史意識の現在」という視点から、歴史意識の未来に向けて、さらに方法的自覚に磨きをかけて、各自論説を展望しているだろうか。
このあたりに留意しながら続々刊行される4次岩波講座 日本歴史を読んでみたい。