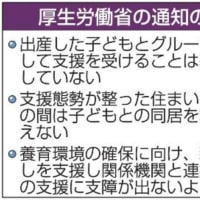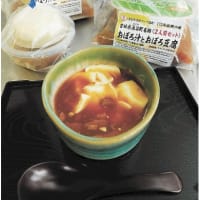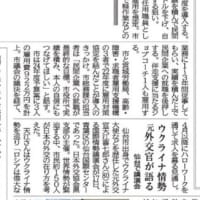(「河北新報」平成24年9月23日(日)付け記事より引用)
多面的に継続支援を
東北大大学院教育学研究科 本郷 一夫 教授
東北大のリベラルアーツサロンが14日、「『気になる』子どもと発達障害」をテーマに、仙台市青葉区のせんだいメディアテークで開かれた。東北大大学院教育学研究科の本郷一夫教授が「気になる」子どもと支援の在り方について解説した。
「気になる」子どもとは知的に顕著な遅れがなく、感情や行動のコントロールがしにくい子のこと。ここ10年で相談件数が増えてきた。
園児から高校生までの調査で、対人トラブルが多い、落ち着きがない、順応性が低い、ルール違反をするなど共通した特徴かあった。医学的な診断がなされていない場合が多く、理解が難しいため、「気になる」という表現が使われる。
原因には発達障害、性格・気質、家庭環境の三つが考えられる。その何割かには発達障害の診断が下るが、残りは障害ではなく、本人の気質や虐待などが原因である場合もある。
発達障害には自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などがあり、判断は難しい。小さい子は年齢で行動が変わるので、どの時点で診断するかという難しさがあり、基準も変わる。気になる行動がある場合は原因を一つに定めず、いくつかの問題が重なっていると考えて対応する必要がある。
気になる子どもの支援は①子ども本人への支援②クラス集団への支援③席の配列など物的環境の調整④保育体制の整備⑤保護者への支援-の五つの柱で、同時に進めることが大切だ。
年齢につれてさまざまな問題も生じる。小学校に入学すると、クラスへの適応が難しい。児童1447人の調査では、学校生活に「不満足」と感じる傾向が見られた。学年が上がると、集団の中でうまくやっていけないという気持ちを持ちやすい。
高校では女子の割合が増える。中学校までは男子が8割を占めるが、高校で女子が36・1%と小学校(14・6%)の倍になる。男子より、対人関係や感情の調整が難しくなるのが特徴だ。
高校生は発達障害の診断名がある生徒より、ない生徒に問題行動が多い。診断名のある生徒は幼少時からの継続支援で集団に適応できるが、そうでない生徒は問題行動がより顕著になる。
そうした現状を踏まえ、本郷教授は「気になる子どもの支援は、診断名の有無にかかわらず、曖昧な部分も含めて早期からの継続的な支援が重要だ」と強調した。
<良い面に目を向けて>
気になる子ども本人への支援では、良い面に目を向け、個性を理解しながら集団に適応できる力を育てる一方、自尊心と有能感をはぐくむことが大切だ。
級友の対応で、本人が落ち着くこともある。双方が互いに成長し合う循環的な関係を考え、他の子どもを含めたクラス全体を支える取り組みが必要だ。
会場からは教員養成に関する質問などが出され、本郷教授は「発達障害や気になる子に対応できる専門知識を持った教員が必要だ」と述べた。
多面的に継続支援を
東北大大学院教育学研究科 本郷 一夫 教授
東北大のリベラルアーツサロンが14日、「『気になる』子どもと発達障害」をテーマに、仙台市青葉区のせんだいメディアテークで開かれた。東北大大学院教育学研究科の本郷一夫教授が「気になる」子どもと支援の在り方について解説した。
「気になる」子どもとは知的に顕著な遅れがなく、感情や行動のコントロールがしにくい子のこと。ここ10年で相談件数が増えてきた。
園児から高校生までの調査で、対人トラブルが多い、落ち着きがない、順応性が低い、ルール違反をするなど共通した特徴かあった。医学的な診断がなされていない場合が多く、理解が難しいため、「気になる」という表現が使われる。
原因には発達障害、性格・気質、家庭環境の三つが考えられる。その何割かには発達障害の診断が下るが、残りは障害ではなく、本人の気質や虐待などが原因である場合もある。
発達障害には自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などがあり、判断は難しい。小さい子は年齢で行動が変わるので、どの時点で診断するかという難しさがあり、基準も変わる。気になる行動がある場合は原因を一つに定めず、いくつかの問題が重なっていると考えて対応する必要がある。
気になる子どもの支援は①子ども本人への支援②クラス集団への支援③席の配列など物的環境の調整④保育体制の整備⑤保護者への支援-の五つの柱で、同時に進めることが大切だ。
年齢につれてさまざまな問題も生じる。小学校に入学すると、クラスへの適応が難しい。児童1447人の調査では、学校生活に「不満足」と感じる傾向が見られた。学年が上がると、集団の中でうまくやっていけないという気持ちを持ちやすい。
高校では女子の割合が増える。中学校までは男子が8割を占めるが、高校で女子が36・1%と小学校(14・6%)の倍になる。男子より、対人関係や感情の調整が難しくなるのが特徴だ。
高校生は発達障害の診断名がある生徒より、ない生徒に問題行動が多い。診断名のある生徒は幼少時からの継続支援で集団に適応できるが、そうでない生徒は問題行動がより顕著になる。
そうした現状を踏まえ、本郷教授は「気になる子どもの支援は、診断名の有無にかかわらず、曖昧な部分も含めて早期からの継続的な支援が重要だ」と強調した。
<良い面に目を向けて>
気になる子ども本人への支援では、良い面に目を向け、個性を理解しながら集団に適応できる力を育てる一方、自尊心と有能感をはぐくむことが大切だ。
級友の対応で、本人が落ち着くこともある。双方が互いに成長し合う循環的な関係を考え、他の子どもを含めたクラス全体を支える取り組みが必要だ。
会場からは教員養成に関する質問などが出され、本郷教授は「発達障害や気になる子に対応できる専門知識を持った教員が必要だ」と述べた。