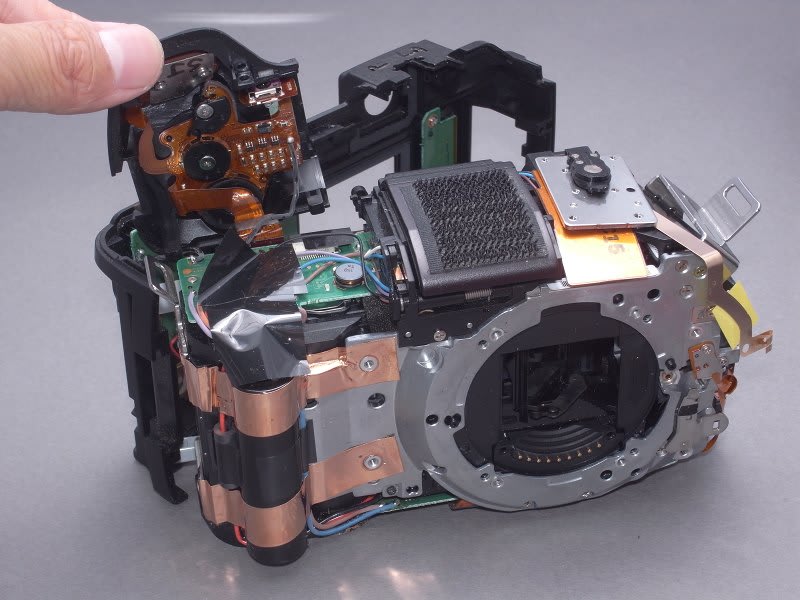先日、渋谷で手に入れた「近未来デジカメ」とは、このニコン・クールピクス900でした。
ジャンク品扱いでごひゃくえんでしたが、電池を入れたら完動品で感動です。
1998年発売で、当時は10万円以上したはずです。
ニコンとしては初めての本格的デジカメで、130万画素の高画質を誇ります。

レンズ部がクルリと回転するスイバル式、永遠の近未来スタイルです。
デザインも、カメラとは思えない妙なテイストでステキです。

「ZOOM NIKKOR」の文字が誇らしげな3倍ズームを装備してます。
当時としてはかなり高性能なレンズで、フィルムより格段に小面積のCCDに適したレンズの製造は非常に難しかったわけです。

記録媒体はCFカードなので、現在でも使用できます。
昔のデジカメは現在のパソコンではデータの読み出しができない機種も多いですから、これは助かります。
なぜか、D70用の256MBのCFが付属してました。

主な撮影設定は、ボディ上面の液晶に表示されます。
ストロボがオートになってますが、発光禁止を設定しても電源オフでまたオートに戻ってしまいます。
これは当時も評判が悪かったみたいです。

背面モニターの表示は至ってシンプルです。
当時としては大きなモニターですが、明るい屋外ではほとんど見えなくなってしまうこともあります。
この写真は、実はパソコンのモニターを映したところを撮影したヤラセです(笑)。
実際の撮影はシャッタータイムラグがほとんどないのに感心してしまいますが、さすがに書き込みには時間がかかって数秒待たされます。

露出補正はメニュー内にあって、これも不便です。
フォントが中国製のトイデジみたいで、味わい深いです。