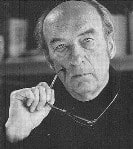「ただ外部をしか見ないというのは農夫のやり方だ。内なるものを、隠されているもを見ることこそ医師の課題なのだ。」
(『オープス・パラミールム』)
T. パラケルスス(Theophrastus Paracelsus, 1492? - 1541)
スイスの医学者。本名は、テオフラトゥス・フィリップス・アウレオールス・ボンバトゥス・フォン・ホーエンハイム (Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim)。
ルネサンスと宗教改革の時代、人体を化学的にとらえ、「病気」は無機物の服用で治療できるとして、鉛や銅などの金属の内服薬やチンキ剤などを作った。「医科学の祖」と言われる。
その生涯で、大半を逃亡(伝統的医学の改革者は「当局への反抗と侮蔑的態度」の廉で、大学を追われた)と遍歴で過ごしたが、実際の治療を数多く行い、同時に著作や手稿も大量に残した。
その非伝統的な/革新的な実験的態度から、ファウスト博士のモデルの一人とも言われる。
科学技術の進展は、人類に何をもたらすのか。
かつて、それには「進歩」と答えれば用が足りた。
しかし、現在、生活の利便性と同時に、科学技術は効率的な人類の殺戮方法をももたらすことが明かになっている(と同時に自然の破壊方法も)。
その長いリストの最後の方には、「核兵器」「化学兵器」「細菌兵器」といったものが挙げられる。
パラケルススにおいて、人間存在は宇宙(コスモス)を忠実に模した小宇宙(ミクロ・コスモス)だった。であるから、医師自体も、患者もミクロ・コスモスの一部であり、医師は神を代行して知と力を発揮し、自然を助け、病気を治療する。
「内なるもの、隠されているもの」とは、コスモスの秩序=ミクロ・コスモスの秩序を知ることを意味する。
信仰の問題は、さて置いて、ここにあるのは、機械論的な自然観・人間観への反措定である。
「科学の知は、その方向を歩めば歩むほど対象もそれ自身も細分化していって,対象と私たちとを有機的に結びつけるイメージ的な全体性が対象から失われ、したがって、対象への働きかけもいきおい部分的なものにならざえるをえない」(中村雄二郎『哲学の現在』)
のである。
科学技術が、機械論的な自然観によって、人類を滅ぼすに到る道を切り開いたとするなら、非機械論的な自然観の可能性を確かめる必要が充分にあるだろう。
参考資料 大橋博司『パラケルススの生涯と思想』(思索社)
*上記引用は、本書から行なった。
(『オープス・パラミールム』)
T. パラケルスス(Theophrastus Paracelsus, 1492? - 1541)
スイスの医学者。本名は、テオフラトゥス・フィリップス・アウレオールス・ボンバトゥス・フォン・ホーエンハイム (Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim)。
ルネサンスと宗教改革の時代、人体を化学的にとらえ、「病気」は無機物の服用で治療できるとして、鉛や銅などの金属の内服薬やチンキ剤などを作った。「医科学の祖」と言われる。
その生涯で、大半を逃亡(伝統的医学の改革者は「当局への反抗と侮蔑的態度」の廉で、大学を追われた)と遍歴で過ごしたが、実際の治療を数多く行い、同時に著作や手稿も大量に残した。
その非伝統的な/革新的な実験的態度から、ファウスト博士のモデルの一人とも言われる。
科学技術の進展は、人類に何をもたらすのか。
かつて、それには「進歩」と答えれば用が足りた。
しかし、現在、生活の利便性と同時に、科学技術は効率的な人類の殺戮方法をももたらすことが明かになっている(と同時に自然の破壊方法も)。
その長いリストの最後の方には、「核兵器」「化学兵器」「細菌兵器」といったものが挙げられる。
パラケルススにおいて、人間存在は宇宙(コスモス)を忠実に模した小宇宙(ミクロ・コスモス)だった。であるから、医師自体も、患者もミクロ・コスモスの一部であり、医師は神を代行して知と力を発揮し、自然を助け、病気を治療する。
「内なるもの、隠されているもの」とは、コスモスの秩序=ミクロ・コスモスの秩序を知ることを意味する。
信仰の問題は、さて置いて、ここにあるのは、機械論的な自然観・人間観への反措定である。
「科学の知は、その方向を歩めば歩むほど対象もそれ自身も細分化していって,対象と私たちとを有機的に結びつけるイメージ的な全体性が対象から失われ、したがって、対象への働きかけもいきおい部分的なものにならざえるをえない」(中村雄二郎『哲学の現在』)
のである。
科学技術が、機械論的な自然観によって、人類を滅ぼすに到る道を切り開いたとするなら、非機械論的な自然観の可能性を確かめる必要が充分にあるだろう。
参考資料 大橋博司『パラケルススの生涯と思想』(思索社)
*上記引用は、本書から行なった。