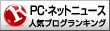江戸天下祭
江戸天下祭とは江戸時代、神田神社の「神田祭」と山王日枝神社の「山王祭」はその豪華さや、行列が江戸城内に入り徳川将軍の上覧を受けたことから「天下祭」と呼ばれていました。
当時の「天下祭」では、神輿と、神話や歴史上の人物をモデルにした人形などを取り付けた山車を曵き回すことが特徴でした。
江戸城下の町内から山車、屋台、造物やお囃子、踊りなどが練り歩き、「神田祭」では36台、「山王祭」では45台が江戸城下を順行し、その趣向が常に江戸で話題になったと伝えられています。
こうした江戸時代の伝統と流行が凝縮された趣向は、やがて関東各地の祭にも影響を及ぼして行きました。
しかし明治22年、憲法発布を記念して山車100台が皇居前に集結したのを最後に、様々な理由により順行が行われなくなり、江戸の伝統を継続することも難しくなりました。
時代は流れ平成15年、江戸開府400年を記念して江戸天下祭が復活をとげました。
今回(9月29日)の『江戸天下祭』においても『山車・神輿順行』で、数々の山車・神輿の行列が長時間掛けて日比谷公園から皇居前広場を練り歩きます。
「江戸木遣り」「お囃子」「手古舞」などの先導と付祭を伴って、再び華やかな江戸天下祭が甦ります。
(まちづくり千代田)
江戸天下祭とは江戸時代、神田神社の「神田祭」と山王日枝神社の「山王祭」はその豪華さや、行列が江戸城内に入り徳川将軍の上覧を受けたことから「天下祭」と呼ばれていました。
当時の「天下祭」では、神輿と、神話や歴史上の人物をモデルにした人形などを取り付けた山車を曵き回すことが特徴でした。
江戸城下の町内から山車、屋台、造物やお囃子、踊りなどが練り歩き、「神田祭」では36台、「山王祭」では45台が江戸城下を順行し、その趣向が常に江戸で話題になったと伝えられています。
こうした江戸時代の伝統と流行が凝縮された趣向は、やがて関東各地の祭にも影響を及ぼして行きました。
しかし明治22年、憲法発布を記念して山車100台が皇居前に集結したのを最後に、様々な理由により順行が行われなくなり、江戸の伝統を継続することも難しくなりました。
時代は流れ平成15年、江戸開府400年を記念して江戸天下祭が復活をとげました。
今回(9月29日)の『江戸天下祭』においても『山車・神輿順行』で、数々の山車・神輿の行列が長時間掛けて日比谷公園から皇居前広場を練り歩きます。
「江戸木遣り」「お囃子」「手古舞」などの先導と付祭を伴って、再び華やかな江戸天下祭が甦ります。
(まちづくり千代田)