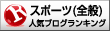法隆寺金堂壁画「釈迦浄土図」
日本書紀成立1300年特別展「出雲と大和」を、友人の大崎啓博さんの案内で鑑賞してきました。
会場は上野の国立博物館平成館です。来場者は男女とも年配者が多く、時節柄マスクをしている人がかなりおりました。
「日本書紀」が編纂されてから1300年。祭祀と政治を象徴する地、島根県(出雲)と奈良県(大和)の古代日本の成立やその特質が鑑賞できました。
大和の地から国を護る、謎多き最古級の石仏、800年守り伝えられた出雲大社の神宝等々が見られました。国宝の「広目天立像」「秋野鹿蒔絵手箱」はじめ、重要文化財の「浮彫伝薬師三尊像」。
圧巻は法隆寺金堂壁画「釈迦浄土図」などは古を思い出させる作品となっておりました。
(2月20日記)
新一万円札の肖像となる渋沢栄一
王子駅そばの北とぴあ17階に「渋沢栄一史料展」が開催されています。
飛鳥山に邸宅があったことで北区が力を入れて広報しています。
渋沢栄一(1840-1931)は、生涯に約500の企業の育成に係わり、同時に約600の社会公共事業や民間外交にも尽力。
2024年には新一万円札の肖像として使用されることが決定しています。
また、令和3年(2021年)に渋沢栄一を主人公としたNHK大河ドラマ『青天を衝け』が放送される。
(10月31日記)
勝海舟記念館
洗足池のそばに新しくオープンした「勝海舟記念館」に行って見学をしました。
この記念館は、国登録有形文化財 旧清明文庫をリニューアルして開館しました。建物は、外観正面中央部のネオゴシックスタイルの柱型4本が特徴的で、内部にはアールデコ調の造作が施されるなど、西洋の建築技法も取り入れられたモダンな建造物となっています。
勝海舟は、幕末から明治にかけて激動の時代を駆け抜けてきた人です。咸臨丸で渡米し、海軍の育成に努めた幕臣です。慶応4年(1868年)に新政府軍が江戸の進軍した際、薩摩藩邸における西郷隆盛との会見や、池上本門寺での会談を経て「江戸城無血開城」実現させた人物です。
記念館の一階は、勝海舟の活動内容や全国行脚した時の記録などの資料が展示してあります。二階は大型モニター映像で「若き日の海舟」などを上映しており、海舟が愛した洗足池の紹介や、別荘「洗足軒」のジオラマ等が展示してあります。
記念館に隣接したところに「勝海舟夫妻の墓所」があります。
(9月17日記)
東京駅丸の内南口に原敬首相遭難現場の説明板が設置されています。
すぐそばの床にはポイントのマークが記されております。
天井の鳩が見守っているようです。
東京駅中央口には、たくさんの私服SPが待機しております。
黒服にノーネクタイの集団はとても目立ち異様な雰囲気を漂わせておりました。
ニュースによると天皇陛下と皇后陛下が東北へ出かけるための警備擁護でした。
(6月19日記)
新政府軍の江戸城総攻撃は、慶応4年(1868年)3月15日と予定されていた。
その直前、西郷隆盛と勝海舟の会談は2回にわたって行われ、一度目の予備会談は3月13日高輪の薩摩藩邸で、二度目は翌14日の田町薩摩蔵屋敷(当地)で行われた(薩摩藩上屋敷は前年末に幕府側によって焼き討ちにされ焼失していた)。
勝は、徳川家が降伏する条件を西郷に提示した。
会談の結果、西郷は江戸総攻撃を中止、勝の案を京都に持ち帰って討議することとなった。
そして4月4日には新政府側と徳川家の間で最終的な合意がなされ、4月11日に徳川慶喜は謹慎先の寛永寺を出て水戸へ出立し、江戸城は無血開城された。
(2月27日記)
近藤勇の墓碑です。
近藤の名前とともに土方歳三の名前も併記されています。
また側面には新撰組隊士などの名前も彫られています。
近藤勇の墓であるとともに、新撰組隊士たちの供養塔でもあるようです。
この墓碑は、新撰組二番隊組長などを勤めた永倉新八が発起人になり、松本順(松本良順)などの協力を得て1876年に建てられたものです。
その永倉新八の墓もあり、遺骨の一部と遺髪が埋葬されているとのことです。
なお1990年、123回忌記念に建てられた碑もあります。
(7月5日記)
東京の桜も満開を迎えて多くの人の目を楽しませてくれている。
桜といえば、ソメイヨシノ桜が代表とされている。
今では米国のワシントンポトマック河畔の桜も花見の名所となっている。
染井吉野(ソメイヨシノ)桜の由来について
400種類くらいある 全国にある桜の70%はソメイヨシノであるといわれている。
《ソメイヨシノ》
自然に咲いている「オオシマザクラ」と「エドヒガン」が合わさってできた。
オオシマザクラの特徴の大きな花。
エドヒガンの特徴の葉っぱより先に花が咲く。
どうしてソメイヨシノという名前がつけられたかというと、 東京都豊島区にあった、「染井村(そめいむら)」からソメイヨシノが広まった。
この、染井と昔から桜の名所であった奈良県の吉野山の吉野が合わさって名づけられたのが、ソメイヨシノです。
(4月7日記)
山村美紗さんの家から急な坂道を登って行き、左側に霊山(りょうぜん)歴史館がある。
わが国唯一の幕末維新の専門歴史館であり、初代館長には松下幸之助氏が就任している。
京都は、幕末維新の志士たちの生きた青春の跡は色あせることなく語り継がれている。
御所、二条城、壬生寺、寺田屋、池田屋、近江屋、月真院、維新の道、翠紅館跡についての収蔵資料などが5000点も展示してある。
新撰組が襲った池田屋や坂本竜馬が暗殺された近江屋の再現模型が忠実に復元されている。竜馬が襲われた時の実物の刀が展示してありリアルさを感じた。
霊山歴史館の前には護国神社があり、坂本竜馬や中岡慎太郎ら先覚志士たちの墓がある。竜馬の墓からは京都市街が見渡される。
(9月19日記)
水道歴史館の裏手には、本郷給水所公苑がある。
そこには、神田上水の石樋が復元して展示してある。
神田上水石樋(かんだじょうすいせきひ)
神田上水は、井の頭池の湧水を水源とする神田川に、善福寺川、妙正寺川の水路を合わせ、目白台下の大洗堰に至り、水戸藩邸を通って神田川を懸樋で渡し、神田、日本橋方面の飲み水などに利用していた江戸時代から明治時代はじめの水道である。
上水道が無かった時には、水を売りに来た商売人がいたようだ。
江戸の物売り声の第一人者である宮田章司師匠に聞いたことがある。
それくらい水は貴重な存在であった。
神田上水について、小学校の時にこんな話を聞いたことがある。
三代徳川将軍家光公は郊外に鷹狩りに出かけた。鷹を三羽獲ったことから「三鷹」の名が残った。家光公が休んだところは今では御殿山として井の頭公園の中に存在する。お茶を出されてあまりにも美味しいものだから「どこの水を使っている?」と聞くと「この水は井の頭池の湧き水です」との返事だった。家光公は「このような美味しい水を江戸の市民にも飲ませるように」と命じて、井の頭池の湧水を神田上水としてひいて江戸の街中まで完成させた。その終着地は、今の御茶ノ水である。
(8月25日記)
夏休みの一日、孫の凌也くんのリクエストで本郷にある東京都水道歴史館(東京都水道局)へ行った。
江戸・東京のくらしを支える水の道。
1階展示室は近現代水道。2階展示室は江戸上水。3階は特別企画展「昭和39年東京大渇水・サバクからオアシスへ」。屋外「本郷給水所公苑・神田上水の石桶」に分かれて展示してある。
受付でわくわく水の探検スタンプラリーで、奥多摩水と緑のふれあい館に続いての入館なので、プチアートボックスを受け取り、ガイド音声の説明を受けて見学をする。
上水井戸は、昭和57年(1982年)、千代田区内幸町で発掘されたもので、原型をよくとどめている。
様々な大きさや形の木樋が継ぎ手により連結され、上水井戸へと給水されていた。木樋には、角形、丸形、三角形があり、角形が最も広く用いられていたようだ。
(8月23日記)
7月1日は、十条冨士神社の例大祭で通称「お冨士さん」と呼ばれている。
近隣の小中学校は臨時の休校となる。
浴衣を着た子どもたちは、冨士塚にお参りをする。
冨士塚は6メートルほどの山の上にある。急な30段の石の階段を上がっていく。
そんなに広くないので下山口専用の階段が脇についている。
冨士神社横の冨士通りは歩行者専用となっており、道の両側には200店の露天が並んでいる。
子どもたちは露天で買物をするのを楽しんでいる。
この道が人で埋め尽くされる。
(7月4日記)
7月1日は、富士山の山開き。
多くの登山客が御来光を見るために富士山に登る。
この日に十条の冨士神社の冨士塚に登ると富士山に登ったと同じご利益が受けられるという。
十条冨士塚(十条冨士神社内)で、富士山の山開きにちなみ、十条冨士神社大祭が開催される。
この大祭は、地元では「お冨士さん」の名で親しまれ、富士山に見立てた冨士塚頂上の石祠に参拝する多くの人や、200を超える露天の出店でにぎわいを見せる。
また、境内では、例年売り切れになるほど人気の縁起物「麦わら蛇」が数量限定で販売される。
「麦わら蛇」は、冨士塚とともに、江戸時代の祭礼の雰囲気や信仰のあり方を今に伝える貴重な文化遺産となっている。
(7月3日記)
上野の国立西洋美術館で開催されている「ルーヴル美術館展―17世紀ヨーロッパ絵画」を鑑賞した。
9時30分からの開館前に到着したので、敷地内にあるモニュメント「考える人」、「カレーの市民」、「地獄門」などを見てから美術館の中に入った。
入り口で音声ガイドを500円で借りる。音声ガイドは美術の造詣が深い中尾彬のナレーションによるものであった。
ガイド番号が貼ってある作品のところで音声ガイドの番号を入れると詳しい解説が耳に伝わってくる。
日本では江戸時代初期にあたる17世紀ヨーロッパ絵画を3つの大きなテーマ①「“黄金世紀”とその陰の領域」、②「旅行と“科学革命”」、③「“聖人の世紀”、古代の継承者?」で分類されていた。
川から救われるモーセ、縁なし帽を被り、金の鎖を付けた自画像、レースを編む女、トロイアを逃れる人々を導くアイネイアス、アイネイアスの傷口にディクタムヌスの薬液を注ぐウェヌス、ユノに欺かれるイクシオン、6人の人物の前に現われる無原罪の聖母、ペテロの涙などが印象に残った。
常設展を鑑賞して美術館の外に出ると、たくさんの人が並んで入場まで整然と列を作っていた。最後尾にはここから入場まで80分と記載されていた。
並んでいる列には中年の婦人たちが多かった。
やはり早くから美術館に来ていてよかった。
中に入ってもゆったりとルーヴル美術館の世界を鑑賞もでき、まるでパリにいる感じを醸し出していた。
(6月12日記)
4月10日は、天皇陛下と美智子皇后の金婚式です。
50年前(昭和34年)の13歳のときを思い出します。
家にはテレビがなかったので、中学校の恩師である貝塚斌先生の家に友達と一緒に訪れました。
貝塚先生の家にはテレビがあって、快く私たちを迎え入れてくれました。
皇室の結婚式は、初めて遭遇した祝辞でありました。
馬車によるパレードに感動してテレビに見入っていました。
なんと優雅に進行していく馬車パレード。
戦後の混乱期を過ごしてきた日本の時代に明るい話題を提供してくれました。
軽井沢のテニスが取り持つ縁となり、ミッチーブームとテニスブームが到来しました。
テニスをする若い人が多くなる社会現象が起きたのです。
結婚50周年を健康に迎えられることは喜ばしいことです。
いつまでも健康に過ごしてほしいと祈念しています。
(4月10日記)