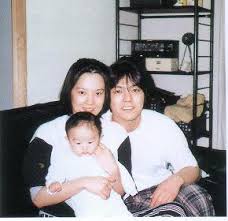和歌山県の田和茜選手による選手宣誓
全日本躰道選手権大会が東京武道館で開催されました。
観覧する目的の一つは、全国から集まる親しい指導者と選手たちに会って話をしてコミュニケーションを図ることです。
朝、集合場所では熱海市で指導している大川公男先生が元気な声で近寄ってきました。
和歌山の小西美智子先生と小西愛先生、そして船本高正先生とも久し振りの再会であります。
昨年の優勝した田和茜選手と準優勝の瀬藤有希選手も元気な姿を見せてくれました。
田和茜選手の選手宣誓は「躰道創始者・祝嶺正献最高師範」の名前を入れて力強くはっきりと宣誓をしておりました。躰道の井戸を掘った人のことを忘れていないことは立派です。
女子個人法形競技では、瀬藤有希選手が余裕の優勝で圧倒していました。そして優秀選手賞も獲得しておりました。日頃から精進して訓練をしてきた躰道の実技を如何なく発揮しておりました。
(12月7日記)
全日本躰道選手権大会が東京武道館で開催されました。
観覧する目的の一つは、全国から集まる親しい指導者と選手たちに会って話をしてコミュニケーションを図ることです。
朝、集合場所では熱海市で指導している大川公男先生が元気な声で近寄ってきました。
和歌山の小西美智子先生と小西愛先生、そして船本高正先生とも久し振りの再会であります。
昨年の優勝した田和茜選手と準優勝の瀬藤有希選手も元気な姿を見せてくれました。
田和茜選手の選手宣誓は「躰道創始者・祝嶺正献最高師範」の名前を入れて力強くはっきりと宣誓をしておりました。躰道の井戸を掘った人のことを忘れていないことは立派です。
女子個人法形競技では、瀬藤有希選手が余裕の優勝で圧倒していました。そして優秀選手賞も獲得しておりました。日頃から精進して訓練をしてきた躰道の実技を如何なく発揮しておりました。
(12月7日記)