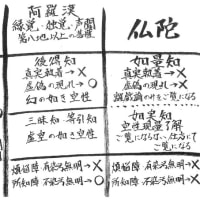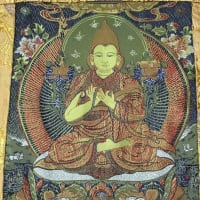昔の葬儀における引導は、火葬場の龕前堂にて行われていたのであろう。
入龕念誦、龕前念誦、鎖龕念誦、起龕念誦、山頭念誦→葬列、龕前堂へと移動→法語、引導(法炬投下)→下炬(火葬)
が、本来の正式な流れであったのだろう。
山頭念誦はまさに別れの表白であるから、出棺の贐となるわけである。「〜茶三点を傾け、香一炉に焚いて、雲程に送り奉りて〜」
現代では、法語の前に法炬、下炬があるということは、もともとは、火葬点火後→引導法語ということであったのかもしれない。
いや、黄檗引導の故事は、引導法語→法炬投下だったであろうか?法炬投下→引導法語だったか?
法炬投下→引導法語→下炬
または、引導法語→法炬投下→下炬
が正しいことになるのかもしれない。つまり、松明は二回使わねばならないということなる。
ならば、二つ用意して、一つは投下、もう一つは点火と分けねばならないのかもしれない。
引導法語前に、一本だけで、下炬→投下している今の拙生の作法はいずれにしても見直した方がよさそうである。
引導法語→一本目の松明の投下→二本目の松明で火葬点火
とするべきなのであろう。
・・
近世公家(鷹司家)の葬送の記録がなかなか興味深い。鷹司兼煕公の葬儀、満中陰までの記録がある。
戒名、院号(通例、戒名は天皇、摂関家は院号のみ)を三宝院に頼むも、突き返して、自分たち(身内に僧侶関係も多い)で(心空華院と)付けている。
20日に亡くなって、23日に通夜、入棺。24日に出棺。25日〜27日は、そのまま二尊院に安置されていたのだろう。
28日に送葬行列とあるが、実質、引導、焼香とあるため、葬儀が28日であることがわかる。死後1週間後である。龕前堂は火葬場にある建物であり、火葬場への送葬後、龕前堂にて葬儀が営まれる感じであったのだろう。
火葬、収骨を終えて戻り(二尊院)、七ヵ日法事が勤められている。七ヵ日法事は、七日間、毎日勤めるものであるようだ。
七ヵ日法事とはどのような法事であったのだろうか。
そして、初七日忌を、29日に勤めている。逮夜で数えるなら25日。
二七日忌が、11月2日。逮夜の正当日にあたるかな。
ところが、三七日忌が4日、四七日忌が6日と、えらい早くにまとめて勤めている。二尊院の行事の影響だろうか、、
五七日忌が、11日、六七日忌が18日、初月忌20日で石塔供養、納骨(?)。25日、満中陰の法事。
中陰が少し日がまばらであること以外は、しっかりとお勤めがなされてあることが分かる。
一ヶ月での石塔建立、納骨が通例だったのかもしれない。なかなかに興味深い。
https://otemae.repo.nii.ac.jp/record/1593/files/1989_wu_h027-056_fujii.pdf
入龕念誦、龕前念誦、鎖龕念誦、起龕念誦、山頭念誦→葬列、龕前堂へと移動→法語、引導(法炬投下)→下炬(火葬)
が、本来の正式な流れであったのだろう。
山頭念誦はまさに別れの表白であるから、出棺の贐となるわけである。「〜茶三点を傾け、香一炉に焚いて、雲程に送り奉りて〜」
現代では、法語の前に法炬、下炬があるということは、もともとは、火葬点火後→引導法語ということであったのかもしれない。
いや、黄檗引導の故事は、引導法語→法炬投下だったであろうか?法炬投下→引導法語だったか?
法炬投下→引導法語→下炬
または、引導法語→法炬投下→下炬
が正しいことになるのかもしれない。つまり、松明は二回使わねばならないということなる。
ならば、二つ用意して、一つは投下、もう一つは点火と分けねばならないのかもしれない。
引導法語前に、一本だけで、下炬→投下している今の拙生の作法はいずれにしても見直した方がよさそうである。
引導法語→一本目の松明の投下→二本目の松明で火葬点火
とするべきなのであろう。
・・
近世公家(鷹司家)の葬送の記録がなかなか興味深い。鷹司兼煕公の葬儀、満中陰までの記録がある。
戒名、院号(通例、戒名は天皇、摂関家は院号のみ)を三宝院に頼むも、突き返して、自分たち(身内に僧侶関係も多い)で(心空華院と)付けている。
20日に亡くなって、23日に通夜、入棺。24日に出棺。25日〜27日は、そのまま二尊院に安置されていたのだろう。
28日に送葬行列とあるが、実質、引導、焼香とあるため、葬儀が28日であることがわかる。死後1週間後である。龕前堂は火葬場にある建物であり、火葬場への送葬後、龕前堂にて葬儀が営まれる感じであったのだろう。
火葬、収骨を終えて戻り(二尊院)、七ヵ日法事が勤められている。七ヵ日法事は、七日間、毎日勤めるものであるようだ。
七ヵ日法事とはどのような法事であったのだろうか。
そして、初七日忌を、29日に勤めている。逮夜で数えるなら25日。
二七日忌が、11月2日。逮夜の正当日にあたるかな。
ところが、三七日忌が4日、四七日忌が6日と、えらい早くにまとめて勤めている。二尊院の行事の影響だろうか、、
五七日忌が、11日、六七日忌が18日、初月忌20日で石塔供養、納骨(?)。25日、満中陰の法事。
中陰が少し日がまばらであること以外は、しっかりとお勤めがなされてあることが分かる。
一ヶ月での石塔建立、納骨が通例だったのかもしれない。なかなかに興味深い。
https://otemae.repo.nii.ac.jp/record/1593/files/1989_wu_h027-056_fujii.pdf