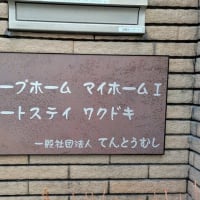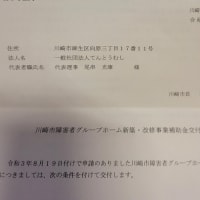当ブログをご覧いただきありがとうございます。尾串光康です。
今回は、滝乃川でのケース会のお話を、と1週間前から考えていたのですが、その矢先に、私が直接教えている教え子の親から写真が送られてきましたので、今回は、それに因んだ記事を。
ということで、以下の写真をご覧ください。

上記写真の著作権を尾串光康と私の教え子の親は放棄しておりません。そのため、いかなる理由であっても、上記写真の使用、転載は、法的処置をとらせていただきます。
こんな写真です。
この子、信じられないと思いますが、余暇が昔は全くないお子さんでした。
もちろん、数年前まではひらがなも読めませんでした。
しかし、今はスマホを自分で操作して、じぶんで「ひらがなのアプリ」を起動させ、平仮名なぞりを行うようになりました。それが、つい最近の事。
昔から「こういった遊びを自分で」行っていたわけではありません。じゃあなぜできるようになったかって?それは、「毎日継続させてきた」からです。
一般的に、遊びは自分で見つけるもの。とか言っちゃってる人いますよね?しかし、周囲をモデリングできない子たちはそれができないから困っているわけです。
「知識」は、ある日突然「降ってくる」のではなく、蓄積された周囲から得られる情報なのです。「アレンジ」も、個人差はあっても、結局は知識と経験から得られる物でしょう。
だから教えるのです。
勉強は勉強。遊びは遊び。そう考えちゃってません?勉強がつまらないと思うのは出来ないと怒られるから。結局勉強も遊びも同じです。ブログじゃわかんないよね(笑)?わかってくださる方はもちろん有り難い。わかりかけている方は嬉しく思います。特に心理、教育をやっている人や目指している人がそうであれば嬉しいですね。
話は戻りますが、当然子どもにとって無理は無駄でしかありません。子どもの能力からあまりにもかけ離れている指導では意味が無いということです。
つまり、そこも親の認識。親が「いや、うちの子はわかっているはずだ!」とか思っていて、難しいことをガンガンやらせても目標は達成できません。
同時に、「うちの子は無理なく楽しくやれれば良いんだ!」と言っている人も「?」です。目標を達成させていく楽しさを知らない子どもは「不適応」を起こしやすいからです。
すなわち「チャレンジ精神」です。チャレンジするためには、「いきなりチャレンジできる人」もいるでしょうが「何度もリハーサルしてチャレンジする人」もいるのです。
何度リハーサルしても、チャレンジはチャレンジ。「人といてこそやること」→「人がいなくてもやること」に変わっていくのもチャレンジだって思いませんか?
小さいうち、小さくなくても療育開始時はしっかりとルールを教えて行くのです。そして、教わる姿勢をしっかりと作るのです。
そして、少しずつ一人でできるように指導していくのです。スモールステップで、徐々に声をかけずに自分でできるようにしていくのです。
そして、十分に成熟したら、必ず自分でやろうとする日が来ます。どんな子でも。それができたら静かに見守っているか、しっかりと褒めてください子どもに合わせて。
それでもちゃんと指導してください。2歳でも7歳でも10歳でも15歳でも、しょせん子どもです。だんだん変わっていきますが、主導権をしっかりと握ってください。いつか「対等」になります。すなわち、「大人の付き合い」ができていると感じる日が来ます。
「対等」になれば、別れるのがより悲しくなります。悲しくなりますが、巣立っていきます。それが子どもです。障がいとか、別に関係ありません。
これは1歳から20過ぎてもずっと一人の子を文字通り「指導」し、そして「見ている」私の言葉。どう?含蓄あるでしょ?(笑)
アプリやっている子どもの写真から、テーマが壮大になってしまいましたね(苦)。
疲れたから今週はこの辺で(笑)。
それでは、また来週に。
今回は、滝乃川でのケース会のお話を、と1週間前から考えていたのですが、その矢先に、私が直接教えている教え子の親から写真が送られてきましたので、今回は、それに因んだ記事を。
ということで、以下の写真をご覧ください。

上記写真の著作権を尾串光康と私の教え子の親は放棄しておりません。そのため、いかなる理由であっても、上記写真の使用、転載は、法的処置をとらせていただきます。
こんな写真です。
この子、信じられないと思いますが、余暇が昔は全くないお子さんでした。
もちろん、数年前まではひらがなも読めませんでした。
しかし、今はスマホを自分で操作して、じぶんで「ひらがなのアプリ」を起動させ、平仮名なぞりを行うようになりました。それが、つい最近の事。
昔から「こういった遊びを自分で」行っていたわけではありません。じゃあなぜできるようになったかって?それは、「毎日継続させてきた」からです。
一般的に、遊びは自分で見つけるもの。とか言っちゃってる人いますよね?しかし、周囲をモデリングできない子たちはそれができないから困っているわけです。
「知識」は、ある日突然「降ってくる」のではなく、蓄積された周囲から得られる情報なのです。「アレンジ」も、個人差はあっても、結局は知識と経験から得られる物でしょう。
だから教えるのです。
勉強は勉強。遊びは遊び。そう考えちゃってません?勉強がつまらないと思うのは出来ないと怒られるから。結局勉強も遊びも同じです。ブログじゃわかんないよね(笑)?わかってくださる方はもちろん有り難い。わかりかけている方は嬉しく思います。特に心理、教育をやっている人や目指している人がそうであれば嬉しいですね。
話は戻りますが、当然子どもにとって無理は無駄でしかありません。子どもの能力からあまりにもかけ離れている指導では意味が無いということです。
つまり、そこも親の認識。親が「いや、うちの子はわかっているはずだ!」とか思っていて、難しいことをガンガンやらせても目標は達成できません。
同時に、「うちの子は無理なく楽しくやれれば良いんだ!」と言っている人も「?」です。目標を達成させていく楽しさを知らない子どもは「不適応」を起こしやすいからです。
すなわち「チャレンジ精神」です。チャレンジするためには、「いきなりチャレンジできる人」もいるでしょうが「何度もリハーサルしてチャレンジする人」もいるのです。
何度リハーサルしても、チャレンジはチャレンジ。「人といてこそやること」→「人がいなくてもやること」に変わっていくのもチャレンジだって思いませんか?
小さいうち、小さくなくても療育開始時はしっかりとルールを教えて行くのです。そして、教わる姿勢をしっかりと作るのです。
そして、少しずつ一人でできるように指導していくのです。スモールステップで、徐々に声をかけずに自分でできるようにしていくのです。
そして、十分に成熟したら、必ず自分でやろうとする日が来ます。どんな子でも。それができたら静かに見守っているか、しっかりと褒めてください子どもに合わせて。
それでもちゃんと指導してください。2歳でも7歳でも10歳でも15歳でも、しょせん子どもです。だんだん変わっていきますが、主導権をしっかりと握ってください。いつか「対等」になります。すなわち、「大人の付き合い」ができていると感じる日が来ます。
「対等」になれば、別れるのがより悲しくなります。悲しくなりますが、巣立っていきます。それが子どもです。障がいとか、別に関係ありません。
これは1歳から20過ぎてもずっと一人の子を文字通り「指導」し、そして「見ている」私の言葉。どう?含蓄あるでしょ?(笑)
アプリやっている子どもの写真から、テーマが壮大になってしまいましたね(苦)。
疲れたから今週はこの辺で(笑)。
それでは、また来週に。