・せっかく北大のKさんからlmer解釈を習ったので、忘れないうちに結果をまとめてしまわねば・・・。ということで、再び、トドマツ標高別相互植栽の解析に戻る。この試験地では、230,340,530,730,930,1100mの6標高に8標高から採種育苗したトドマツを2反復で植栽している。各種子産地では、5つの母樹から採種している。試験設計はシンプルなようでいて、母樹や反復の影響も捨てがたく、なかなか一筋縄ではいかなかったというわけだ。
・今回は、「母樹と反復の効果には興味がないが、かといって無視するわけにもいくまい」、ということで、母樹と反復をランダム効果、種子産地標高と種子産地と植栽地の標高差が固定効果として、生存/死亡や樹高を説明する一般化線形混合モデルを用いている。植栽地を全て込みにすると、樹高も生存も、種子産地と標高差の両方を考えたモデルがよい。ちなみに、生存については、種子産地が高いほど、標高差が小さいほど高いという関係にある。一方、樹高については、種子産地が低いほど、標高差が小さいほど高いという関係がある。種子産地が高いほど生存がよいというのは少し面白いが、これは高標高に植栽したときに、低標高産の個体がばたばたと死亡してしまうことに起因しているようだ。
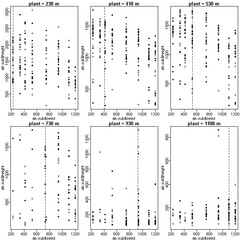
・しかし、植栽地自体の環境が標高によって著しく変動するので、どのくらいまでがまとめられるかどうかというのが問題となっているわけである。生データを眺める限り、明らかに530m以下と930m以上はそれぞれ一まとめにできそうだ。問題は730mの扱いである。そこで、このモデルを530m以下を低標高、1)730m以上を高標高という2つに分割する場合、2)730m以下を低標高、930m以上を高標高と2つに分割する場合、3)530m以下を低標高、730mを中(?)標高、930m以上を高標高に分割する場合の3つを考えてみた(それ以上、細かく分けても現実的に意味がないだろうし・・・)。
・その結果、AICを比較すると、いずれも3)がもっとも当てはまりが良いことが分かった(パラメータ数は多くて複雑になるが、それでもよいモデルといえるようだ)。しかし、生存率と樹高では少し傾向が異なる。生存率では2つに分ける場合は730/930に比べて530/730で区分するのがよく、一方樹高では、530/730に比べて730/930で区分する方がよい。いずれも、これらの区分は3つの区分とそれほど大きな差がないといえる。
・このように考えると、600m以下、600-800m付近、800m以上というあたりにラインをいれて、それぞれに対応を考えるのがベストだといえそうだ。3つも分けるのは大変だから2つに区分したい、というような場合には、生存率を重視するならば600m付近、成長を重視するならば800m付近でラインを入れるということになるんだろうか・・・。。
・富良野の現場では、600m以上にトドマツを植栽することはまれで、800m以上はほとんどないといってよいので、植栽標高が600m以下の場合には一般的な低標高産を用いている限り問題はなく、600mを超えて少し標高が高いところに植栽したい、というような場合には、用いる種子の種子産地には留意した方がよい、ということになるのかもしれない。もう少し、細かいパラメータの値を検討していかないといけないが、まずは先に進めそうな予感がしている。
・ところで、これは書いておかねばなるまい。先日の札幌で立ち寄ったパン屋”パン吉”のハード系のフランスパンは絶品だ。ワインに合うと書いてあったトマトとバジルの調理パンも美味しかったが、何気ないダッチ風のフランスパンには驚かされる。皮は薄いがバラバラにならず、中はもっちり、ふわふわである。しまった、もっと買っておくのであった・・・。
・今回は、「母樹と反復の効果には興味がないが、かといって無視するわけにもいくまい」、ということで、母樹と反復をランダム効果、種子産地標高と種子産地と植栽地の標高差が固定効果として、生存/死亡や樹高を説明する一般化線形混合モデルを用いている。植栽地を全て込みにすると、樹高も生存も、種子産地と標高差の両方を考えたモデルがよい。ちなみに、生存については、種子産地が高いほど、標高差が小さいほど高いという関係にある。一方、樹高については、種子産地が低いほど、標高差が小さいほど高いという関係がある。種子産地が高いほど生存がよいというのは少し面白いが、これは高標高に植栽したときに、低標高産の個体がばたばたと死亡してしまうことに起因しているようだ。
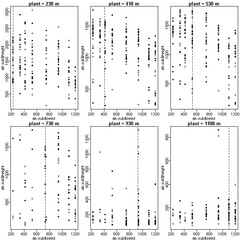
・しかし、植栽地自体の環境が標高によって著しく変動するので、どのくらいまでがまとめられるかどうかというのが問題となっているわけである。生データを眺める限り、明らかに530m以下と930m以上はそれぞれ一まとめにできそうだ。問題は730mの扱いである。そこで、このモデルを530m以下を低標高、1)730m以上を高標高という2つに分割する場合、2)730m以下を低標高、930m以上を高標高と2つに分割する場合、3)530m以下を低標高、730mを中(?)標高、930m以上を高標高に分割する場合の3つを考えてみた(それ以上、細かく分けても現実的に意味がないだろうし・・・)。
・その結果、AICを比較すると、いずれも3)がもっとも当てはまりが良いことが分かった(パラメータ数は多くて複雑になるが、それでもよいモデルといえるようだ)。しかし、生存率と樹高では少し傾向が異なる。生存率では2つに分ける場合は730/930に比べて530/730で区分するのがよく、一方樹高では、530/730に比べて730/930で区分する方がよい。いずれも、これらの区分は3つの区分とそれほど大きな差がないといえる。
・このように考えると、600m以下、600-800m付近、800m以上というあたりにラインをいれて、それぞれに対応を考えるのがベストだといえそうだ。3つも分けるのは大変だから2つに区分したい、というような場合には、生存率を重視するならば600m付近、成長を重視するならば800m付近でラインを入れるということになるんだろうか・・・。。
・富良野の現場では、600m以上にトドマツを植栽することはまれで、800m以上はほとんどないといってよいので、植栽標高が600m以下の場合には一般的な低標高産を用いている限り問題はなく、600mを超えて少し標高が高いところに植栽したい、というような場合には、用いる種子の種子産地には留意した方がよい、ということになるのかもしれない。もう少し、細かいパラメータの値を検討していかないといけないが、まずは先に進めそうな予感がしている。
・ところで、これは書いておかねばなるまい。先日の札幌で立ち寄ったパン屋”パン吉”のハード系のフランスパンは絶品だ。ワインに合うと書いてあったトマトとバジルの調理パンも美味しかったが、何気ないダッチ風のフランスパンには驚かされる。皮は薄いがバラバラにならず、中はもっちり、ふわふわである。しまった、もっと買っておくのであった・・・。









