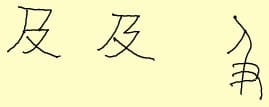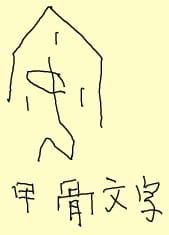「手」の音はtとeに分解出来るが、日本では古く、そのeとaが入れ替わったり
iとoが入れ替わることが有った事が知られている。
目(me)が目(ma)とも読まれることが有り、木(ki)が木(ko)と読まれる
例が有る。「目のあたり」は「まのあたり」、眼(まなこ)やまなじり、も
そうだろう。木は、こかげ、打ち出の木(こ)づち、なども。
話を「手」に戻すと、「手(て)もつ(保つ)」、「手(た)ずさえる」
手向(たむ)ける、手綱(たづな)などが有る。
何か法則が有りそうだ。対象への働きかけが有るときに音の変化が
現れるのか、わたしには良く分からない。
iとoが入れ替わることが有った事が知られている。
目(me)が目(ma)とも読まれることが有り、木(ki)が木(ko)と読まれる
例が有る。「目のあたり」は「まのあたり」、眼(まなこ)やまなじり、も
そうだろう。木は、こかげ、打ち出の木(こ)づち、なども。
話を「手」に戻すと、「手(て)もつ(保つ)」、「手(た)ずさえる」
手向(たむ)ける、手綱(たづな)などが有る。
何か法則が有りそうだ。対象への働きかけが有るときに音の変化が
現れるのか、わたしには良く分からない。