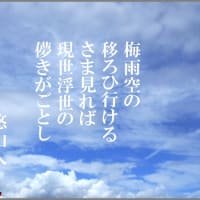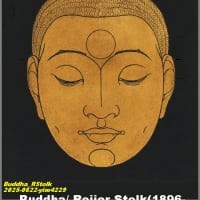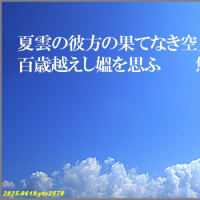■親しかった人を偲ぶ気持ちが、自分にはいくらあったところで、いざ自分が死ん
だら、だれがそんなふうに思ってくれるだろうか。俊成さん、杞憂に終りましたね、
800年経っても電網世界でさえ、ますます人気者ですよ。
ところで、かおる・におう・かぐ、の使い分けは?

【補注】○藤原俊成(しゅんぜい、としなり、両読み)=皇太后宮大夫(こうたいごう
ぐう だいぶ)。60歳過ぎて出家、釈阿(しゃくあ)と号。入集は72首。
【補説】平安神宮に入ってすぐ、左右に花木が相対している。右近の橘の説明文
にこうあった。(去年秋確認)
「橘は、蜜柑の仲間で唯一の野生種であり、その実は/古くから『常世の
国』の不老長寿の妙薬として珍重された。/さつき待つ 花橘の香をかけ
ば/昔のひとの 袖の香ぞする」(振り仮名略。「かけば」表記はそのまま)
この有名な本歌「五月待つ花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする」
は、古今集(夏、、読人しらず)と伊勢物語(60段)に登場。伊勢では女性
の改悛の場に使われている。
すぐあとの 0240 式子詠は、またまた妖しい雰囲気。
かへり来ぬ昔を今と思ひ寝の 夢の枕ににほふ橘
さらに 0242 慈円の「夜半のうたたねに花橘」、0245 俊成の娘の「橘のに
ほふあたりのうたた寝」も、申し合わせたように、橘(の花香)と夢を結びつ
けている。ここにも新古今歌人の五感統合の意図が、はっきりと見て取れ
る。
* ブログ開設して、きょうで満一か月。背伸びしすぎないように自戒。