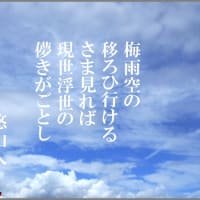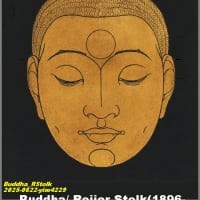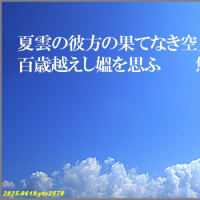伝統と格式のある石清水八幡宮での、目にも鮮やかな青(山藍)の衣を纏っての、春の舞い。ともに舞ったあの春が懐かしい。
ひらかなy148:やまあいの みなもにうつる ころもきて
ともにまいした はるがこいしい
ひらかなs1796:ころもでの やまゐのみづに かげみえし
なほそのかみの はるぞこひしき
【略注】○山ゐ(「山藍」、やまあゐ)=「山野の日陰に多く生え、葉の汁を
青色の染料とする。<源氏・若菜下 ~に摺れる竹の節は> 訳
山藍で(青色に)摺り染めにした(小忌衣の)竹の節(の模様)は。」
(旺文社版 古語辞典) 石清水宮なので、「山井」(山の井戸)との
掛詞。補説に小忌衣。さらに補説。
○藤原実方(さねかた)=貞時の子。陸奥(任地)で客死。12首入集。
【補説】①小忌衣(おみごろも)。「大嘗会・新嘗会・五節(ごせち)、その他の
神事に装束の上に着る衣服。」(小学版) 毎年の新嘗会のうち、天
皇即位直近に行われるものが大嘗会。いまの天皇家に伝わる。ここ
では長い詞書から、石清水八幡宮の臨時奉納で、二人舞いしたとき
の上掛けのこと。なおさらに、次の歌も参照。
1798 立ちながらきてだに見せよ小忌衣
あかぬ昔の忘れがたみに 加賀左衛門
だから、一見恋歌のようだが、男の友情を詠んでいる。
②山藍。「トウダイグサ科の多年草。高さ約40センチメートル。山野の
草地に自生。葉は長楕円形。雌雄異株。春、上部の葉の付け根に緑
白色の小花を穂状につける。昔は葉から汁をとって青色の染料にし
た。万葉集(9)「紅の赤藻裾引き~もち摺れる衣(きぬ)着て」(広辞苑)
写真で見たのは、調布の神代植物園、市川の万葉植物園のもの。
万葉集 巻九 1742 高橋虫麻呂
しなてる片足羽川のさ丹塗の 大橋の上ゆ紅の赤裳裾引き
山藍もち摺れる衣着てただひとり い渡らす児は若草の夫あるらむ
なお、ウェブサイト「万葉の花とみどり」はさらに詳しい。
http://manyo.web.infoseek.co.jp/index.html