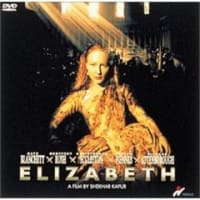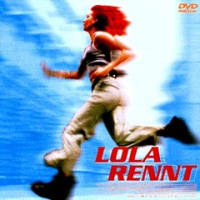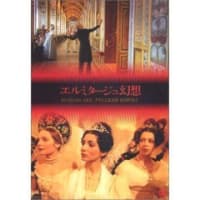「べてるの家」は、知的障害者や統合失調症などの精神病を抱える人々の「自助施設」だ。いわゆる「共同作業所」みたいなもんだけど、ちょっといやかなり違う。べてるの家は毎日毎日問題だらけ。救急車やパトカーが毎日のように走り回り、近所迷惑もはなはだしい。だが、そのビョーキの人々が見事に商売をやってのける、このすごさ。
本書には、北海道稚内に近い日高という過疎の地に建つ「べてるの家」の人々が、昆布の袋詰め内職から始めて起業し、やがて年商1億を売り上げるまでになったその10年の日々が綴られている。
amakoさんに「全部を読み通す本が一年に2冊しかないという上野千鶴子さんが、最後まで読み通した稀少な本がこれです。ものすごくおもしろいから」と薦められて読み始めた。ほんとにおもしろい。過疎の町の起業についても、企業経営についても、対人関係についても、効率と能率ということについてもたくさん考えさせられる。
とにかくべてるの家の人々の開き直りがすごい。町民を招いて「差別偏見歓迎大集会! 糾弾しません」なんていう集会を開いてしまうし、毎年「妄想幻聴大会」を開いて大賞を決める、とか。「病気は売れる」と、いちばん妄想のひどい人間に講演と営業をさせてしまうとか。
べてるの家の人たちは「社会復帰」なんて考えない。逆なのだ。自分たちが過疎の浦河町を復帰させてしまおうと考える。リハビリして病気を治そうなんて思わない。もちろん治ったほうがいいんだけど。「そのままでいいんだよ」と言ってもらえることで精神が安定し救われる患者がここには何人もいる。べてるの家と病院を行ったり来たりしながらここの人々は自分たちのやり方で生きていく。
朝にならないと誰が出勤してくるかわからないといういいかげんさ。不祥事が起きて警察に「責任者、来てください」と呼び出されても誰が責任者かわからないから全員で警察に行ってしまうというおもしろさ。
なんかいいよな~、べてるの家って。実際に住んでみたら困ることがいっぱいあるんだろうけど、そんな場所が羨ましくなる。
ただし、「そのままのあなたでいい」という肯定論はすべての人に当てはまるわけではないだろう。べてるの家で心の病を癒す人にはそういう言葉が有効でも、すべての人間にそんなことを言って回った日には「あなたはそんなにひどい人だけど、そのままでいいよ」「あ、そう、今のままでなんの努力もせずにだらけていればいいんだ。わたしってほんとはもっと大きな人間なのよ」と自省を否定する言葉としてうまく利用されてしまうおそれがある。じっさい、「そのままのあなた」では困る人がいっぱいいるんだから!
べてるの人々の妄想ぶりも自己中心的発想も心の弱さも、「ふつうの人々」のそれと違いはなくて、ただ規模が大きくなっただけなのだ。だから、この本を読む「健常者」も、べてるの家の人々のコミュニケーションの悩みや苦しみがすっと胸に落ちるだろう。
べてるの家の成功の裏には、本書の大部分を書いた向谷地(むかいやち)生良さんというケースワーカーの力が随分大きかったんじゃないかな。個性豊かな(豊かすぎる!)人々に苦労しつつ、向谷地さん自身がコミュニケーションや仕事の悩みを抱えつつ、みながそれぞれの弱さを認め合ってやってきた。
そしてなにより「狂者の文化」を肯定的にとらえる視線がいい。こういう流れは60年代の「青い芝の会」の頃からあったけれど、かなり論調が違う。なにより「糾弾しません」という集会がいい。べてるの家の人々は、「住民は偏見と先入観に凝り固まっている」と思うことじたいが「偏見と先入観」そのものだったことに気づいたという。
今までだって問題だらけだったという「べてるの家」は、これからも問題だらけなんだろう。この先10年20年、どうなるんだろう。
<書誌情報>
べてるの家の「非」援助論 : そのままでいいと思えるための25章
浦河べてるの家著.- 医学書院, 2002. (シリーズケアをひらく)
本書には、北海道稚内に近い日高という過疎の地に建つ「べてるの家」の人々が、昆布の袋詰め内職から始めて起業し、やがて年商1億を売り上げるまでになったその10年の日々が綴られている。
amakoさんに「全部を読み通す本が一年に2冊しかないという上野千鶴子さんが、最後まで読み通した稀少な本がこれです。ものすごくおもしろいから」と薦められて読み始めた。ほんとにおもしろい。過疎の町の起業についても、企業経営についても、対人関係についても、効率と能率ということについてもたくさん考えさせられる。
とにかくべてるの家の人々の開き直りがすごい。町民を招いて「差別偏見歓迎大集会! 糾弾しません」なんていう集会を開いてしまうし、毎年「妄想幻聴大会」を開いて大賞を決める、とか。「病気は売れる」と、いちばん妄想のひどい人間に講演と営業をさせてしまうとか。
べてるの家の人たちは「社会復帰」なんて考えない。逆なのだ。自分たちが過疎の浦河町を復帰させてしまおうと考える。リハビリして病気を治そうなんて思わない。もちろん治ったほうがいいんだけど。「そのままでいいんだよ」と言ってもらえることで精神が安定し救われる患者がここには何人もいる。べてるの家と病院を行ったり来たりしながらここの人々は自分たちのやり方で生きていく。
朝にならないと誰が出勤してくるかわからないといういいかげんさ。不祥事が起きて警察に「責任者、来てください」と呼び出されても誰が責任者かわからないから全員で警察に行ってしまうというおもしろさ。
なんかいいよな~、べてるの家って。実際に住んでみたら困ることがいっぱいあるんだろうけど、そんな場所が羨ましくなる。
ただし、「そのままのあなたでいい」という肯定論はすべての人に当てはまるわけではないだろう。べてるの家で心の病を癒す人にはそういう言葉が有効でも、すべての人間にそんなことを言って回った日には「あなたはそんなにひどい人だけど、そのままでいいよ」「あ、そう、今のままでなんの努力もせずにだらけていればいいんだ。わたしってほんとはもっと大きな人間なのよ」と自省を否定する言葉としてうまく利用されてしまうおそれがある。じっさい、「そのままのあなた」では困る人がいっぱいいるんだから!
べてるの人々の妄想ぶりも自己中心的発想も心の弱さも、「ふつうの人々」のそれと違いはなくて、ただ規模が大きくなっただけなのだ。だから、この本を読む「健常者」も、べてるの家の人々のコミュニケーションの悩みや苦しみがすっと胸に落ちるだろう。
べてるの家の成功の裏には、本書の大部分を書いた向谷地(むかいやち)生良さんというケースワーカーの力が随分大きかったんじゃないかな。個性豊かな(豊かすぎる!)人々に苦労しつつ、向谷地さん自身がコミュニケーションや仕事の悩みを抱えつつ、みながそれぞれの弱さを認め合ってやってきた。
そしてなにより「狂者の文化」を肯定的にとらえる視線がいい。こういう流れは60年代の「青い芝の会」の頃からあったけれど、かなり論調が違う。なにより「糾弾しません」という集会がいい。べてるの家の人々は、「住民は偏見と先入観に凝り固まっている」と思うことじたいが「偏見と先入観」そのものだったことに気づいたという。
今までだって問題だらけだったという「べてるの家」は、これからも問題だらけなんだろう。この先10年20年、どうなるんだろう。
<書誌情報>
べてるの家の「非」援助論 : そのままでいいと思えるための25章
浦河べてるの家著.- 医学書院, 2002. (シリーズケアをひらく)