マグニチュード(M)9・0の巨大地震と大津波を想定できなかった科学者たち。悔恨の思いを胸に、国民のための地震学を模索してほしいと願います。
「地震学全体の敗北である」。今月、静岡市で開かれた日本地震学会の特別シンポジウムは衝撃的な問題提起で始まりました。東日本大震災に遭遇し、多くの学者は「われわれはいったい何をしてきたのか」「どのように社会にかかわっていけばいいのか」と自問自答しています。これらは、阪神大震災直後も議論に上りながら集約しなかったテーマなのです。
探求優先ゆえに…
地震学会は理学系が主流で、未知の探求を優先します。社会とのかかわり、すなわち防災を考える工学系と性質的に違い、ここに問題点の一つがあります。シンポジウムの開催自体が画期的で、特別講演に日本の地震学に批判的なロバート・ゲラー東大教授を招いたことは、学会が変わろうとする意欲の表れで、評価します。
ゲラー氏は「現時点で地震の事前予知はできない」と持論を繰り返し、地震科学も災害対策も白紙に戻す時期だ、と強調しました。会長の平原和朗京大教授はシンポジウムを「地震学会の始まりだ」と例えています。
日本の地震学会は一八八〇年の横浜地震を機に世界で初めて創設されました。国は九一年の濃尾地震(犠牲者七千二百人余)後に設けた震災予防調査会で本格的な研究を始め、一九二三年の関東大震災(同十万五千人余)後、東大地震研究所に引き継がれました。
地震の正体に迫る中、国と学者たちは「地震は将来予知できる」と真剣に考え始めました。七六年に石橋克彦東大助手(現神戸大名誉教授)が東海地震切迫説を発表すると、予知を前提に被害を少なくするための規制を盛り込んだ大規模地震対策特別措置法(大震法)が制定されました。
短期予知できない
年間数十億円が観測網整備などに投入され、学者もマスコミも国民の期待をあおり、予知が予算獲得の手段と化していきました。そして九五年、東海ではなく直下型の阪神大震災が起こり、予知はトーンダウンするのです。
東海地震が三十年以内に起きる確率は87%と言われて、国民のどれだけがすぐに備えたでしょうか。望むのは長期予測ではなく短期予知なのです。それができないならできない、とはっきり言うべきです。難しい理由を述べるべきです。「科学では分からない」を、丁寧に説明することも学者の務めではないでしょうか。
シンポジウムでは「予算をいくら使い、どれだけの成果を挙げたかを考えよ」と、これまでの予知研究に反省を求める声がありました。一方で「世間から認められるために研究をやっているわけではない」「すべてを背負わず肩の荷を下ろして研究に専念を」との反論がぶつかりました。地震学のいまとこれからについて、大いに議論を続けてほしいと思います。
学会への注文ばかりを述べましたが、一つの知見が社会に貢献した事例も多いのです。先の石橋説で静岡県は防災対策を進めました。対策前と比べ犠牲者は半減できるとシミュレーションしています。二〇〇六年から運用されている緊急地震速報や津波警報も、予知研究の成果です。
津波堆積物による歴史地震の地道な調査も意義は大きいでしょう。近年の仙台平野での調査で貞観地震(八六九年)が今回の大震災と似ていて、その千年前にも大津波があったことが分かり、報告書をまとめて注意喚起する矢先でした。もう少し調査が早ければ、と悔やまれます。
二十世紀の科学は知識の生産を重視し、活用は使う側に任せてきました。それだけでは社会の信頼が得られなくなり、世界科学会議は一九九九年、二十一世紀の科学の責務として「平和」「開発」そして「社会のための科学」を加えました(ブダペスト宣言)。
大震災を受けて日本学術会議が出した声明は、社会のための科学を「社会の中で科学者ができるだけの知識を提供しながら市民と問題を共有し、解決を共に模索する在り方を要求するもの」と位置付けています。地震が人の生命にかかわる以上、地震学と防災は分けて考えることはできないのです。地震学は生命を守る情報を支えていることを、学者自身が再認識しなければなりません。
国民と積極対話を
予知だけが社会の要請ではありません。地震について、地球について、科学で分かることを少しずつでも増やしてほしいのです。学会は徹底した未知の探求と、批判を恐れない健全な議論を続けるべきです。同時に、研究成果を期待する国民との積極的な対話や情報提供も担ってもらいたいのです。










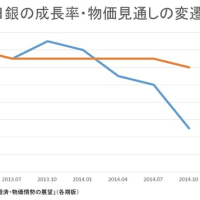
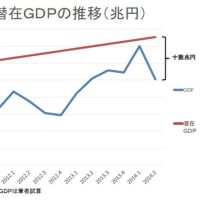


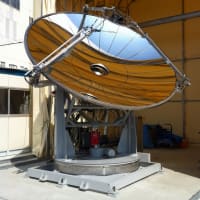
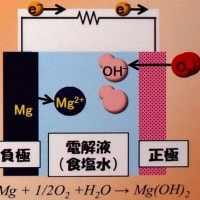

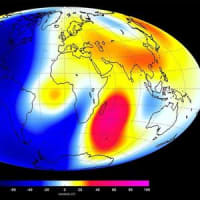


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます