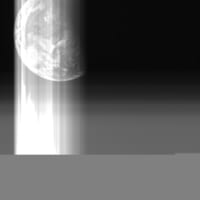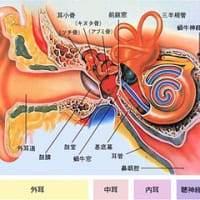花を扱う知人がいる。
知人は、ほんとうは絵描きであったりもする。
花の何たるかを知ろうとし、日々絵を描く友のパフォーマンスは、花や絵という既に定まって見える固体が常に時間を含んでいるのだという至極アタリマエのことを、改めて示してくれた。
知人は、まず、針金を組み上げて作った馬を大きな蒼いガラスの花瓶に活けた。そして、その馬を模る針金の隙間に赤いバラとバラの実にマユミの枝、そしてぐにゃりとうねった何かよく判らない枝を少しずつ、差し入れていった。馬はもとあった形状のままに、しかし徐々に馬のかたちを失くしてゆき、そこには赤い花や実が生えた針金の土台が廃墟のようにしてあった。
赤い花が生え揃ったのは、恐らく最初の花を手に取ってから30分も経っただろう頃であった。花を活ける知人の指先は、顔料によって真っ青にべったりと彩られていた。真っ青な手先は別の生き物のようで、それが運ぶ花はその手を有する人の意識とは隔絶されたもののように見えた。人がその身に持たない青という強い色が、その手の持ち主の身体と花とが直接触れることを遮り、ただ青という冷静な媒介者となって花を運んでいた。
すべての花があるべきところに収まると、知人は後ろの壁に貼られたモノクロームの大きな絵と対峙した。そもそもから青かった手を顔料に浸し、絵に青色を置いていった。赤い花の束を前に、背後の白い画面は徐々にその青い面積を大きくしていく。
顔料壺と白い画面の間を幾度となく往復する青い手。暗がりのなかでただ黙ってそれを見ていると、青という色が虚空を飛んで画面に到達し、その上を滑ってゆくように見える。この場面において意思のあるものはただ青だけで、赤い花も、人の手さえもその青に操られてゆらゆらと漂い、青の気紛れが示すままにあるべき場所へと着地する。
知性の色だとか修羅の色だとか、人が勝手に定義した青のイメージは見事に崩壊し、そこにはれっきとした青という独立した存在と意思があった。
すべてが終わったあと、定められた赤い花と青く彩られた絵を前にして、私達は煙草を挟んで語り合った。
「先ほどまでは普通に触ることに躊躇いがなかった花は、どうして今は触っちゃいけないものに見えるのかな。」
これまでの時間を見てきた私はそう訊いた。
「触っちゃえばいいんだよ、こんなふうに。」
知人はバラの花を形が崩れるほどにぎゅっと指先で強く摘まんだ。
そこに私は、時間の中に居た人と時間を横目で見ていた人の乗り越えがたい壁を見た。
知人は、ほんとうは絵描きであったりもする。
花の何たるかを知ろうとし、日々絵を描く友のパフォーマンスは、花や絵という既に定まって見える固体が常に時間を含んでいるのだという至極アタリマエのことを、改めて示してくれた。
知人は、まず、針金を組み上げて作った馬を大きな蒼いガラスの花瓶に活けた。そして、その馬を模る針金の隙間に赤いバラとバラの実にマユミの枝、そしてぐにゃりとうねった何かよく判らない枝を少しずつ、差し入れていった。馬はもとあった形状のままに、しかし徐々に馬のかたちを失くしてゆき、そこには赤い花や実が生えた針金の土台が廃墟のようにしてあった。
赤い花が生え揃ったのは、恐らく最初の花を手に取ってから30分も経っただろう頃であった。花を活ける知人の指先は、顔料によって真っ青にべったりと彩られていた。真っ青な手先は別の生き物のようで、それが運ぶ花はその手を有する人の意識とは隔絶されたもののように見えた。人がその身に持たない青という強い色が、その手の持ち主の身体と花とが直接触れることを遮り、ただ青という冷静な媒介者となって花を運んでいた。
すべての花があるべきところに収まると、知人は後ろの壁に貼られたモノクロームの大きな絵と対峙した。そもそもから青かった手を顔料に浸し、絵に青色を置いていった。赤い花の束を前に、背後の白い画面は徐々にその青い面積を大きくしていく。
顔料壺と白い画面の間を幾度となく往復する青い手。暗がりのなかでただ黙ってそれを見ていると、青という色が虚空を飛んで画面に到達し、その上を滑ってゆくように見える。この場面において意思のあるものはただ青だけで、赤い花も、人の手さえもその青に操られてゆらゆらと漂い、青の気紛れが示すままにあるべき場所へと着地する。
知性の色だとか修羅の色だとか、人が勝手に定義した青のイメージは見事に崩壊し、そこにはれっきとした青という独立した存在と意思があった。
すべてが終わったあと、定められた赤い花と青く彩られた絵を前にして、私達は煙草を挟んで語り合った。
「先ほどまでは普通に触ることに躊躇いがなかった花は、どうして今は触っちゃいけないものに見えるのかな。」
これまでの時間を見てきた私はそう訊いた。
「触っちゃえばいいんだよ、こんなふうに。」
知人はバラの花を形が崩れるほどにぎゅっと指先で強く摘まんだ。
そこに私は、時間の中に居た人と時間を横目で見ていた人の乗り越えがたい壁を見た。