
「修羅場」というのは、案外悪いものではない。
なぜなら、その戦いが始まった時点で、既に勝負はついているからだ。
阿修羅王が帝釈天に決して打ち勝つことができず、不条理とも思える敗北を喫したように。
興福寺の阿修羅像は三面六臂、上半身は裸で、上帛と天衣をかけ、胸飾りと臂釧や腕釧をつけ、裳をまとい、板金剛を履く。この像は、もしかしたら日本で最もファンの多い仏像かもしれない。阿修羅像そのものが決して代表的なモティーフとして今日まで残っているわけでないとしても。更に云うなら、それが阿修羅像としての典型の姿を成していなかったとしてもだ。
阿修羅という存在そのものからは、大陸における絡み合った信仰の歴史が透けて見える。そして、個人的な正義は往々にして社会に打ち勝つことが不可能であることをまっすぐ我々に突き付ける。それは悪でもなく、不条理でもなく、ただ「そうあった」のだいうことを。
興福寺の阿修羅像は、憤怒を示す赤にその身を染めつつも、硬直したように足を揃えてまっすぐに立つ。膝にも、ぴんと高く張って合掌する腕にも緩みがない。まるで、自らの表皮を用いて形成した静というバリアを堅固に張って、その内部に渦巻く様々なうねりを封じ込めんとするかのように。この像と対峙したとき、抗えず私は息をつめ、上半身に緊張が走る。この像が身を呈して護ろうとするなにかのために、そのすぐそばに居る私が緩んでいてはいけない。そう感じさせるからだ。
戦いの末に削ぎ落とされた肉体は、不自然に長い6本の腕をかろうじて支えている。造形的には、奇跡的にバランスの崩れる半歩手前で危うい均衡を保っている。腕があと少しだけ短かったら危機感や切迫感が足りず、あと少しだけ長かったら冗長な弱さ、頼りなさを生み出す。もう少し太かったなら哀しみが足りず、さらに細かったなら、恐らく当代まで残っていなかったろう。それに加えて、もう少しこの腕が「腕らしい」フォルムをしていたなら、そもそも我々がこの像を見たときに最初に感じる異形感、あの独特な「めまい」を感じることは決してない。
見るものをぞくりとさせるぎりぎりの均衡は、その7割以上が腕によって支えられていると云っても過言ではない。
そして、最も典型から外れているのがその面立ちだ。口をかっと開けて怒りを表す相が多い中で、これはどう見ても憂いを帯びた少年相だ。三面ともども、薄い唇を噛むような風情で引き結び眉間に皺を寄せて、眼差しは彼方を見遣る。
悔悟。
苦悩。
焦燥。
葛藤。
克己。
憧憬。
そのいずれとも見え、いずれでも不自然な気にさせる表情は、身体や腕の記号的な表現とは対照的に、まるで人間そのもののようにリアリスティックで、我々はそれにまんまと騙される。動的な情動を華奢な身体に封じ込め、長い長い硬直を続ける姿に我々は自己を投影して安堵し、そのヒロイズムに陶酔するのだ。
たとえ、彼が戦っているものが「自分自身」などという陳腐なものなどではないとしても。
阿修羅が天界の住人ではないということが、こんなにも人間の視線を、そして感情までもを不躾にするものなのか。
我々が容易に惚れることのできる像の哀しみがここにある。
なぜなら、その戦いが始まった時点で、既に勝負はついているからだ。
阿修羅王が帝釈天に決して打ち勝つことができず、不条理とも思える敗北を喫したように。
興福寺の阿修羅像は三面六臂、上半身は裸で、上帛と天衣をかけ、胸飾りと臂釧や腕釧をつけ、裳をまとい、板金剛を履く。この像は、もしかしたら日本で最もファンの多い仏像かもしれない。阿修羅像そのものが決して代表的なモティーフとして今日まで残っているわけでないとしても。更に云うなら、それが阿修羅像としての典型の姿を成していなかったとしてもだ。
阿修羅という存在そのものからは、大陸における絡み合った信仰の歴史が透けて見える。そして、個人的な正義は往々にして社会に打ち勝つことが不可能であることをまっすぐ我々に突き付ける。それは悪でもなく、不条理でもなく、ただ「そうあった」のだいうことを。
興福寺の阿修羅像は、憤怒を示す赤にその身を染めつつも、硬直したように足を揃えてまっすぐに立つ。膝にも、ぴんと高く張って合掌する腕にも緩みがない。まるで、自らの表皮を用いて形成した静というバリアを堅固に張って、その内部に渦巻く様々なうねりを封じ込めんとするかのように。この像と対峙したとき、抗えず私は息をつめ、上半身に緊張が走る。この像が身を呈して護ろうとするなにかのために、そのすぐそばに居る私が緩んでいてはいけない。そう感じさせるからだ。
戦いの末に削ぎ落とされた肉体は、不自然に長い6本の腕をかろうじて支えている。造形的には、奇跡的にバランスの崩れる半歩手前で危うい均衡を保っている。腕があと少しだけ短かったら危機感や切迫感が足りず、あと少しだけ長かったら冗長な弱さ、頼りなさを生み出す。もう少し太かったなら哀しみが足りず、さらに細かったなら、恐らく当代まで残っていなかったろう。それに加えて、もう少しこの腕が「腕らしい」フォルムをしていたなら、そもそも我々がこの像を見たときに最初に感じる異形感、あの独特な「めまい」を感じることは決してない。
見るものをぞくりとさせるぎりぎりの均衡は、その7割以上が腕によって支えられていると云っても過言ではない。
そして、最も典型から外れているのがその面立ちだ。口をかっと開けて怒りを表す相が多い中で、これはどう見ても憂いを帯びた少年相だ。三面ともども、薄い唇を噛むような風情で引き結び眉間に皺を寄せて、眼差しは彼方を見遣る。
悔悟。
苦悩。
焦燥。
葛藤。
克己。
憧憬。
そのいずれとも見え、いずれでも不自然な気にさせる表情は、身体や腕の記号的な表現とは対照的に、まるで人間そのもののようにリアリスティックで、我々はそれにまんまと騙される。動的な情動を華奢な身体に封じ込め、長い長い硬直を続ける姿に我々は自己を投影して安堵し、そのヒロイズムに陶酔するのだ。
たとえ、彼が戦っているものが「自分自身」などという陳腐なものなどではないとしても。
阿修羅が天界の住人ではないということが、こんなにも人間の視線を、そして感情までもを不躾にするものなのか。
我々が容易に惚れることのできる像の哀しみがここにある。













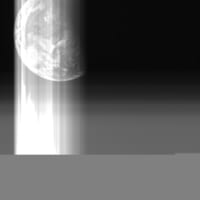


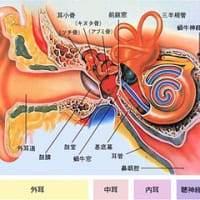



眉を寄せた顔を見て、『女の悩み』と言ってしまった。
もっとも、大仏の下品な顔よりずっといいけどね。
『悩み』に見えるのは、恐らく98%以上の人が同意すると思う。
「女」かどうかは・・・分かれるところですね。
多分、マジョリティは「少年」(十代後半ってところか?)だと思います。
二度と取り戻せない(女性だったら、もう共感も憧れもできない)『少年』は、その存在だけで、いつの時代もきっと特別なんだものね。
で、帰ってきて、この「仏像大辞典」を探してみたが見つからなかったので、いつか現れる日を待っていたわけです。
なんであんなにも惹きつけられたのか、ちょっとだけわかりました。サンキュ。
確かに、あの顔、見る者を同じ顔にさせる。
あんなに自己を投影してしまう像って少ないのかな。
あぁ、項目が偏っている時点で辞典にはならないや。
いや、ベタの力は凄いですよ。
それが、仏像界において(たぶん)ベタでは決してないヴァージョンの方だからこそ、その結果が非常に興味深い訳です。(※例えば、あまりに完璧な薬師寺の聖観音立像なんてのは仏像界でもベタな正統アイドルだったりするはず)
相棒がこの像に子供の頃からベタボレらしいので、リクエストに応じて書いてみた次第です。
大いなるスキマ産業としてのわたしは、意図的にこれまで避けてきたのですが・・・
哲学者メルロ・ポンティは云いました。
「人は、目の前にあるものの真似を無意識にするものだ」
しかし、人間界よりも上の「天界」に住む仏像たちは、多分意図的に、こちらが真似できない(したいとも思わない)崇高さを提示してくることが多いのです。
だから、やっぱり、投影してしまえる余地がここの阿修羅像の中にわざと残してあるんじゃないかな、と思うの。