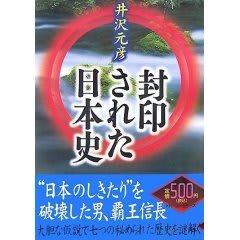久しぶりの更新です。
ここ数日、仕事疲れもあり、帰宅後は休んでいました。
現在、今年に入ってから3冊目となる本『耳こそはすべて』を読んでいます。
*(原題:All You Need Is Ears 1979年出版)
この本の著者はビートルズのデビュー・アルバムから実質上のラスト・レコーディング・
アルバム『アビイ・ロード』までをプロデュースした《ジョージ・マーティン》氏です。
《George Martin イギリス 1926-》
前回読んだ『ザ・ビートルズ・サウンド 最後の真実~著者:ジェフ・エメリック』と
合わせて読むと〈プロデューサー:ジョージ・マーティン〉と〈サウンド・エンジニア:
ジェフ・エメリック〉の2人の立場の違いによる、見つめる視点・留意すべき点の異なる
ところが興味深いです。
一言でいうと〈プロデューサー〉は音楽的な仕上りと同時にビジネス面も考え、レコー
ド会社へ経済的な利益をもたらす事も考えなければならない。
〈サウンド・エンジニア〉はサウンドそのものを第一義と捉え、アーティスト側が意図す
るサウンドへの手助けとなるよう常に可能性の限界へ挑戦していく姿勢が優先する。
*アルバムによっては〈プロデューサー〉よりも〈サウンド・エンジニア〉の”色”の方が
出る場合もあります。
読む順序としてはジェフ・エメリック氏の本を読んでからジョージ・マーティン氏の本を
読んだ方が理解しやすいように思います。
まだ読み始めて間もないのですが、すぐに感じたのはジョージ・マーティン氏がビートル
ズのプロデューサーになった幸運はマーティン氏よりも、むしろビートルズの方だったと
思いました。
音楽業界に数多くいるプロデューサーの中でもマーティン氏の音楽的才能・力量・洞察力
は群を抜いており、常にアーティスト側の立場からの観点で音楽を創造しているように思
います。大物プロデューサーになればなるほど確固たるサウンド・スタイルがあるため、
時にはアーティスト側が希望するサウンド・スタイルとの相違による対立が生まれる場合
もあります。
ビートルズはデビュー当時から自分たちの音楽に対する確固たるサウンド・スタイル=
サウンド指向があったのでマーティン氏の意向に従わないことも多々ありました。
しかしそんな時こそマーティン氏の力量が発揮される時で、ビートルズ側のサウンド指向
を理解したうえで、さらにその上を目指し、実際にそれを”サウンド”にしてしまうのです。
ビートルズの曲にはクレジットされていなくても(ビートルズ通の方々は勿論知っていま
すが)マーティン氏のアレンジ及び演奏における貢献度は絶大なものでした。
マーティン氏がEMIに入社した1950年はレコードといえばSP盤(78回転)が主流で、
LP盤(33回転)はこれからという時代でした。まさにレコードの黎明期です。
そういった時代だったからこそ、そこでいろんな経験を積み、また多数のアーティストと
仕事をし、そこから多種多様な音楽ジャンルにも精通していったと考えられます。
マーティン氏の懐の深さ(音楽だけでなく、人としても)はこの時代に培った経験から
来ているのかもしれません。
まだまだ本は続いていきますので読了後、あらためて感想を記したいと思います。