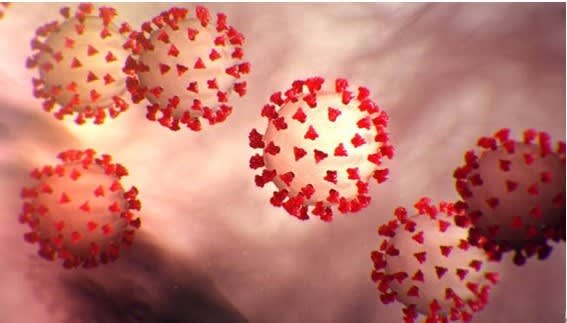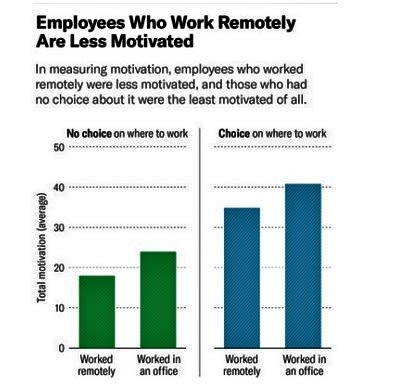僕が書き残しておきたいと思っている恩師、つまり先生は、大学も含めてたくさんいらっしゃるが、中でも高校時代に親切にして頂いた先生がとても印象深い。

<奥野先生>
一人は僕が卒業した洲本高校の奥野先生。もう何度かブログに書いている。僕の一番の友達だった炬口勝弘が亡くなった1年後に 先生は亡くなってしまった。それで、僕には洲本に旅するという理由はなくなってしまった。
もう一人高校時代の先生を紹介して僕の文章として残しておきたい。
洲本高校は一年と二学期を過ごしたことになるが、その前は岡山の田舎にあるO高校で一年一学期を過ごした。その時、本当にお世話になったのが妹尾先生で、あだ名は 「河童」だった。なぜ河童だったのかは先輩に聞くしかないが、もう聞く相手もいない。この先生には、公私共に本当に親身になって私を支えていただいたことを覚えている。
ニックネームは河童(カッパ)でしたが、本名は与三次で、高校の数学の先生でした。
そのころ僕は一人でO高校に通っていた。ある時、親父のおかげで、一人で引っ越しが必要になった。その際、リヤカーで何往復かしたが、その引越しを肉体労働で手伝っていただいた。またある時は、僕が体育の授業でサッカーをやっていて、僕がボールをキックした瞬間、友達が残った軸足を同時に蹴飛ばして、僕は宙に舞い腕の骨を折った。その時、妹尾先生は、僕を高校から僕の下宿まで自転車で送っていただいたこともはっきり覚えている。

<O高校>
この与三次先生に出会ったのは、僕が16歳だから1958年だと思う。そのころ、先生は30歳を超えたばかりの年齢だったから、おそらく生まれは1928年ぐらいだ。論拠は、僕が17歳、そのころ先生は最低30歳だったから、逆算して1928年と言ったわけだ。
実は妹尾河童先生は、近くの村の大地主の末裔で、元々、妹尾屋敷と呼ばれるとてつもなく大きな敷地と大きな二階建ての建物、大きな池、そしてそれを取り巻く林、さらには周囲には畑が作ってあった。

堀に囲まれた屋敷に入るには石橋を渡って、大きな長屋門をくぐっていかなければならないくらい大きな建物だった。地元では 妹尾屋敷と呼ばれていた。この屋敷は戦後、 新制中学校の校舎として使われるほどの大きさがあった。この屋敷に、僕は下宿する羽目になって、毎朝学校に行く前に幅一間以上ある、長い濡れになった廊下を雑巾掛けをやらされていた。僕を一人で置いて奈良の方に入った、親父との取り決めだった。だから辛い嫌な思いもある屋敷でもあった。
この妹尾屋敷の絵とか写真とかを入手しようと努力したのだが、後で述べる経過で入手に至っていない。想像から絵をかいてみようと試みたが、やはり力不足だった。
実はこの先生とは後日(約20年は経っていた)、親父を連れて僕の子供たちとともに我が家のルーツを調べておこうと岡山に帰郷した際、与三次先生を思い出し、僕が車を運転していたので、じゃあ寄ってみようと、そのへ向かった。妹尾先生は右か左かどちらかの腕を骨折していて、肘関節がくの字に曲がっていたので、自転車を運転していても河童だということがすぐわかる。まさにそんな格好をした先生が自転車に乗ってこちらに向かっていらした。すれ違った際、あっ先生だと気づいて、僕は慌ててUターンして、先生追っかけて途中で捕まえた。
おやじも社会文化活動の関係で、河童と顔見知りで、(僕よりも先に先生を知っていた)3人で懐かしい昔話をした記憶がある。その時、先生は娘さんの結婚のために、町に買い物に出掛けられるところだった。そして、それが先生に会った最後だった。
そんなこともあって、どうしても妹尾先生のことを書きたいと思ったわけだ。
妹尾河童といえば、別に有名な人がいる。フジテレビ「ミュージックフェア」の舞台美術で、1960年代には、日本の舞台美術を素晴らしいものに完成された芸術家、妹尾河童だ。彼は、1930年生まれで、1954年にデビューされたとある。彼は、妹尾肇さんで、今年(2020)90歳とある。先の妹尾河童と、つながりがあるかどうかわからない。

<河田町のフジTV>
実は僕は、フジテレビが新宿の河田町にあったころ、深夜の台本作りのアルバイトをしばらくやっていた。そして、妹尾河童さんの舞台芸術にあこがれて、何としてでもフジテレビに入社したいとの思いで、畑は違うがアナウンサー試験を大学卒の時に受けて、4次試験まで合格したが、最終5次で終わった残念な思い出がある。彼の書いた「河童が覗いたヨーロッパ」のイラストも楽しくて、夢中になって読んだものだ。

<アマゾンの中古本として、本が売られていた>
なんだか、僕は妹尾河童には深い縁がある、いやあったらしいのだ。
そんなこともあって、なんとかその後の妹尾屋敷のことを知ることはできないかと、ググってみたり、妹尾屋敷のあった村(今は町村合併でM市となっている)の生涯教育・村史に詳しいというT.Moさんに電話インタビューをして取材をしてみたが、屋敷の絵や写真は得られなかった。
同じ市のIiさんの紹介で、昔の妹尾屋敷を知っている85歳のS.MYさんとも電話インタビューをしてた。妹尾屋敷は僕の記憶通りに存在していて、姿は僕の記憶通りだったと裏は取れた。今は、妹尾屋敷跡地には、ソーラーパネルが立ち並ぶ姿が見えると話していただいた。
皆様のご協力に感謝です。