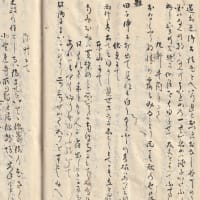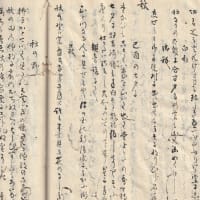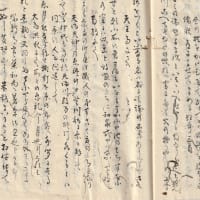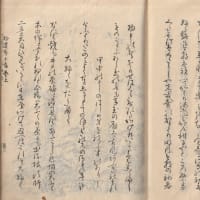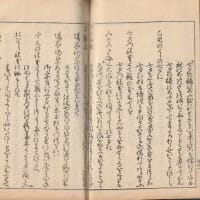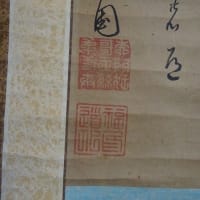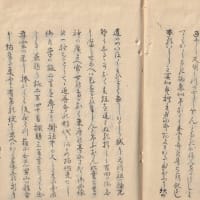阿武山麓の八木に伝わる蛇落地(じゃらくじ)の伝承を調べるうちに、最初は陰徳太平記に描かれた天文元年(1532)の大蛇退治に注目したけれど、私の興味は次第に阿武山山頂の観音様(蛇落地観世音菩薩)が麓に降ろされた弘化四年(1847)に移って行った。蛇落地とは、もちろん大蛇伝説をふまえた上で、すでに字として成立していた上楽地(じょうらくじ)、あるいは観音様が降り立つとされる補陀落(ふだらく)山をもじった、この観音様のためのネーミングという可能性もあるのではないか、そう考えるようになった。最近、江戸時代の狂歌とその周辺の資料を読み進めるうちに、少しこちらの話のために書き留めておきたいことがあった。そのあたりをだらだらと書いてみたい。
前に書いた弘化二年の土石流は大野村でも被害があったようで「豊助日録」に、
「八月六日から大雨、大洪水、中山山くずれ」
とある。大竹から呉まで広い範囲で被害があったことがわかっているけれど、阿武山の沼田郡ではどうだったのかまだ見つけられていない。江戸では弘化二年に青山(権田原)火事(表中弘化三は弘化二の誤り)、翌三年佃火事と連続して大火があったようだ。また、大野古文書管見(一)の解説によると、広島藩では天保頃からインフレが始まって、弘化四年には藩札の下落により物価は三十倍、四十倍になったという。また、沼田郡八木村ではこの頃、阿武山に設定した中島村の入会地の境界で訴訟になっている。明治維新の二十年前、幕藩体制の崩壊の足音が聞こえてくるような世相に見える。
なお、幕末に向けて広島藩の財政は悪化の一途をたどり、鋳物の町である可部でも大がかりな贋金造りが行われたと可部高校近くの寺山の観音様の説明文にあった。
藩札の下落も歯止めがかからず、明治29年「狂歌ねさめの伽」には、
宮島の水月庵といへるに石の地蔵尊半より金
になりたりと聞き当時藩札下落の折柄とて
札さへも金にならさる此国に石の地蔵のかねになるとは
とある。これは三首あとに鞆の津にて東京舩便という詞書があることから東京と藩札が同居していた明治初年の作と思われる。話が少しそれてしまった。
弘化という時代の世相は徐々にわかってきた。一方、当時の八木村の観音信仰とはどのようなものであったのか、これが中々手掛かりが見つからない。江戸時代の沼田郡、高宮郡といえば浄土真宗の安芸門徒の勢力が強かった。広島城下は殿様も毛利、福島、浅野と交代があり武士も入れ替わりがあったせいだろうか、色々な宗派のお寺がある。しかし、私が住んでいる安佐北区では可部の福王寺(可部には高野山の荘園があった)が真言宗というのが唯一の例外であとはすべて浄土真宗だ。深川薬師も江戸時代以降は浄土真宗のお寺になっている。こうなった理由について「秋長夜話」には、
「此国は一向宗盛にして、郡中村々一向門徒にあらざるはなし、元来村々に寺ある事なし、多くは仏護寺十二坊の門徒なり、其村所にて農民の僧形となりて勧化するものを手次坊主といふ、一向宗に限りていにしへよりこれあり、蓮如上人の文章にも手次坊主たちと書れしなり、此手次坊主ども漸々村の用意を得て勢つき、後は堂をも建立し、おのづから寺のやうになりしなり、取次頼み本願寺へ請て、寺号・木仏・開山上人画像・太子七高僧代々門跡上人の御影など申受て一寺を創立するなり、創寺の事は他宗にては一向なりがたき事なれども、本願寺門徒にてはいかなるゆゑは知らねど殊外容易なり、一向宗の年を逐て盛るは是をもての故なるべし」
とある。この通りかどうかはわからないが、貞国の歌をみても浄土真宗の宗旨はしっかり浸透していて、その中で観音様はどれぐらいの重みがあったのだろうか。中世の観音信仰は現世利益から浄土信仰へと変質していったと言われている。すると江戸時代は浄土信仰に位置づけられるはずだが、たとえば曾根崎心中の観音廻りはどちらかと言えば現世利益、あるいは当時の娯楽のようにも思える。このあたりが山頂にあったのでは不都合な理由だったのかもしれない。しかし、曾根崎心中の観音廻りは都会の話だ。この時代の地方の農村に暮らす人々の観音信仰、心の内を表した資料、手掛かりはないものだろうか。阿武山の観音様に近づくには、まだまだ努力が足りないようだ。
(安佐北区口田南あたり、高陽団地行きバスの車窓から太田川の向こうに権現山、阿武山を望む)