伊東静雄論のために、小津安二郎の「秋刀魚の味」を見た。ずいぶん以前にも見た。小津の最後の作品。この映画、論法ははっきりしている。悲しみだけを浮き彫りにしようとしている。何の、悲しみ?人への思慕か、嫁ぐ娘への思慕か。いや、独りであることの悲しみ。それは、何か状況から作用して悲哀するのではなく、根源的な自らの生を思慕する悲しみなのだ。あたかも様々な茶飯的な小状況が、悲哀を誘発しているように映画は語ろうとしているかのようにみえて、後半、小津の論法は、明らかな虚無を浮かび上がらせて終...わる。この映画は、「軍艦マーチ」の映画なのだ。バーの場面、前半で二回、後半で一回、さらに主人公が口ずさみ、最後半では、ストリングスの効果音楽として挿入される。小状況が作用した悲哀への増幅効果ではなく、主人公の存在の根に響く、悲しい音楽なのだ。それにしても、虚を尽くして描きながら、実も尽くしている。ビールとつまみ、居酒屋、ラーメン屋、駅、同窓生、日本人、欧米化、サラリーマン、映画の中のリアルがおそろしいほど、見る者の身に沁みこむように仕掛けられている。映画的には、岩下志麻と岡田茉莉子、東野英治郎と中村伸郎の演技的対照をよくもここまで際立たせたものだと思う。加東大介もすごい存在だった。
★
「秋刀魚の味」続き
小津の「秋刀魚の味」。いまのぼくの日常に、まとわりつく。まとわりついてなかなか伊東の詩編に照応できない。なにがまとわりついているかというと、映画の中の記号的な事物なのだ。映画の虚は、眼前の映像が「終」になれば、映像は消滅する。もちろん演者も演技も物語も消える。そこでは、テクスチャーだけがからまって記憶に記される。
この茫洋とした織物の、その結節にからまっているのが、記号的な事物の彩だ。たとえば、妙にこちらの見る側の心象の糸にからまりまとわりついているのが、随所にインサートされた「軍艦マーチ」の旋律なのだが、ほかに、高架ホームの駅を地上から撮った場面。その駅名が付された看板。その他、飲み屋の看板、棚に並んだ洋酒のラベル、サッポロビールととんかつ、居酒屋の猪口などの器の類。もう、事物の記号の洪水だ。
これは、実を「造作」していることの共犯を観客に強要もしている。あるいは、この実のつまりは、偽装された実をやすやすと「虚」に混在させない技なのだろう。
小津は、この閾に拘泥している。この閾を映画で滅しようとしている。そこから、まるで泥まみれの観念を、そっと洗い出してみせる。巧妙としかいえない。もちろん、映画とは、この「巧妙」のことであるのだが。
★
「秋刀魚の味」続き
次号の『海鳴り』誌で、小津安二郎の「秋刀魚の味」と伊東静雄の戦後の詩篇「都会の慰み」を同時に批評した。映画と詩を一度に読み解くのは、とても難儀だった。「読んだもの」と「観たもの」なのだが、観たものの心象がまさって、強く記憶される。快、不快の深度も観たものの方が強い。また、想像力も無尽に開放される。
たとえば、映画の中で、とても驚いたのが、劇中の話だが、主人公の娘が兄の同僚に思いを寄せている。それを兄が同僚に伝える場面。ちょっとした行き違いで同僚にはすでに婚約者がいると告白される。「もっと早くいってくれればよかったのに」と苦笑する。観る者は落胆するが、そこでこの同僚は、ビールとトンカツをおかわりする。「このトンカツおいしいね」という。観る者は、日常の些事の次元に突き落とされて、無情の地べたへ連れ戻される。つまりは虚/実の綾にからまれながら、さみしい往還を強いられる。その作用を、小津は、無駄なく見せる。語っているのは、台詞もそうだが、「うまいトンカツ」でもある。ただ、これがリアリズムであるとか日常の再現かというと、よくよく考えればそうでもない。トンカツのおかわりなんて、尋常ではないとぼくには思える。このあたりが、映画作法の“凄み”なんだなあと思った。象徴力をできうるかぎり隠れるぎりぎりまで薄く削いで、観る者の欲望の綾の細部に紛れ込ませる。
それからこの映画、劇中ふたつの冗談めいた嘘をつく場面が演じられる。ここでも観る者は映画の詐術に翻弄される。しかも平気で“映画の詐術だよ”と晒されて顕れる。これも凄み。なかなか詩にはできない技。
★
「秋刀魚の味」続き
小津の「秋刀魚の味」。いまのぼくの日常に、まとわりつく。まとわりついてなかなか伊東の詩編に照応できない。なにがまとわりついているかというと、映画の中の記号的な事物なのだ。映画の虚は、眼前の映像が「終」になれば、映像は消滅する。もちろん演者も演技も物語も消える。そこでは、テクスチャーだけがからまって記憶に記される。
この茫洋とした織物の、その結節にからまっているのが、記号的な事物の彩だ。たとえば、妙にこちらの見る側の心象の糸にからまりまとわりついているのが、随所にインサートされた「軍艦マーチ」の旋律なのだが、ほかに、高架ホームの駅を地上から撮った場面。その駅名が付された看板。その他、飲み屋の看板、棚に並んだ洋酒のラベル、サッポロビールととんかつ、居酒屋の猪口などの器の類。もう、事物の記号の洪水だ。
これは、実を「造作」していることの共犯を観客に強要もしている。あるいは、この実のつまりは、偽装された実をやすやすと「虚」に混在させない技なのだろう。
小津は、この閾に拘泥している。この閾を映画で滅しようとしている。そこから、まるで泥まみれの観念を、そっと洗い出してみせる。巧妙としかいえない。もちろん、映画とは、この「巧妙」のことであるのだが。
★
「秋刀魚の味」続き
次号の『海鳴り』誌で、小津安二郎の「秋刀魚の味」と伊東静雄の戦後の詩篇「都会の慰み」を同時に批評した。映画と詩を一度に読み解くのは、とても難儀だった。「読んだもの」と「観たもの」なのだが、観たものの心象がまさって、強く記憶される。快、不快の深度も観たものの方が強い。また、想像力も無尽に開放される。
たとえば、映画の中で、とても驚いたのが、劇中の話だが、主人公の娘が兄の同僚に思いを寄せている。それを兄が同僚に伝える場面。ちょっとした行き違いで同僚にはすでに婚約者がいると告白される。「もっと早くいってくれればよかったのに」と苦笑する。観る者は落胆するが、そこでこの同僚は、ビールとトンカツをおかわりする。「このトンカツおいしいね」という。観る者は、日常の些事の次元に突き落とされて、無情の地べたへ連れ戻される。つまりは虚/実の綾にからまれながら、さみしい往還を強いられる。その作用を、小津は、無駄なく見せる。語っているのは、台詞もそうだが、「うまいトンカツ」でもある。ただ、これがリアリズムであるとか日常の再現かというと、よくよく考えればそうでもない。トンカツのおかわりなんて、尋常ではないとぼくには思える。このあたりが、映画作法の“凄み”なんだなあと思った。象徴力をできうるかぎり隠れるぎりぎりまで薄く削いで、観る者の欲望の綾の細部に紛れ込ませる。
それからこの映画、劇中ふたつの冗談めいた嘘をつく場面が演じられる。ここでも観る者は映画の詐術に翻弄される。しかも平気で“映画の詐術だよ”と晒されて顕れる。これも凄み。なかなか詩にはできない技。










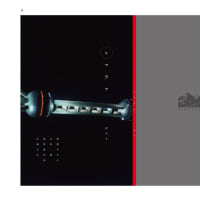



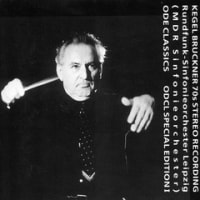




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます