夏の詩人 15 内声と外声
「春の雪」で語られている些景の奥行は、浅い。詩人がその時住んでいた、堺市三国ヶ丘の御陵に、雪が降る。木にうっすら積もった雪が、光に透けている。「ながめゐしわれが想ひ」は、「下草のしめりもかすか」と体感し「春來むと」「ゆきふるあした」の今にいることを確かめている。
些景と言ったが、それは景物の描写に頼らないがための詩人の細い感性が選択した詩法であったろう。たとえば、俳諧における名辞や事物の象徴性に仮託させる方法に近しい。象徴性を高めるために、景物描写のまわりで修飾される雅語は、けっして浅くない。詩の内、つまり言葉の内声において、「些」であったとしても、一篇の数行を通して渡る時、そこに外なる声も響かせている。
では、外なる声とはなんだろう。
みささぎにふるはるの雪
枝透きてあかるき木々に
つもるともえせぬけはひは
なく聲のけさはきこえず
まなこ閉じ百(ルビもも)ゐむ鳥の
しづかなるはねにかつ消え
(詩集『春のいそぎ』「春の雪」全三連のうちの前二連)
詩とは、言葉によって書かれていることがすべてであるという考え方もあるだろう。伊東の場合その「すべて」が「些」にすぎない。それを内声といってしまい、書かれた詩の余情や、漏れ出る行間からの声を、外声といって、考えてみると見えてくるものがある。
もちろん伊東詩の本質を、内と外どちらに見るかといったことを考えることの方法的な正否は、別にしてである。
外の声といって、まず考えられるのが、詩人の存在を包む時代の気分があげられる。この詩が書かれたのは、戦中のまさにその最中であろう。住まいの近隣へ歩み出で、浅き春の雪に出会う。その雪は、積りもせずただ、朝の光を受けて解けはじめている。光景は、まばゆいばかりの光に満ちてはいるが、それだけにしだいに淡彩に均されて見える。圧倒的な光、そして淡く薄い眼前の様子。詩篇の行末の言葉は、「消え」である。詩人はもう、光景とともに、消滅への予感を察知している。
たとえば、この一冊の詩集の標題である『春のいそぎ』の「いそぎ」という言葉を取り出してみてもいい。詩集の標題とは、詩人の内と外を繋ぐ、特別な声なのである。仮に、この「春の雪」一篇との接点を考えてみる。「いそぎ」とは、この些景でもある儚い春の光景への没入ととらえてみよう。つまり景と情が、詩において溶解し、一つになる方途を、伊東は望んでいたのではないか。「いそぎ」「消え」、これこそが、溶解への願望と私には読める。そして外の声を想像してみると、そこに、生と滅へ急(ルビせ)くことの運命的な受苦を感ずる。
*
同『春のいそぎ』より、同じ頃に書かれたであろう、もう一篇の春の詩を引く。
春淺き
あゝ暗(ルビくら)と まみひそめ
をさなきものの
室(ルビしつ)に入りくる
いつ暮れし
机のほとり
ひぢつきてわれ幾刻(ルビいくとき)をありけむ
ひとりして摘みけりと
ほこりがほ子が差しいだす
あはれ野の草の一握り
その花の名をいへといふなり
わが子よかの野の上は
なほひかりありしや
目とむれば
げに花ともいへぬ
花著(ルビつ)けり
春淺き雑草の
固くいとちさき
實(ルビみ)ににたる花の數(ルビかず)なり
名をいへと汝(ルビなれ)はせがめど
いかにせむ
ちちは知らざり
すべなしや
わが子よ さなりこは
しろ花 黄い花とぞいふ
そをききて点頭(ルビうなづ)ける
をさなきものの
あはれなるこころ足らひは
しろばな きいばな
こゑ高くうたになしつつ
走りさる ははのゐる厨の方(ルビかた)へ
(同詩集「春淺き」全篇)
伊東の詩の中でも、最も私が好んでいる一篇である。詩集『春のいそぎ』の中に詩人がひそませた、佳篇。ある日の家族の光景ととらえることができる。詩人が暗い書斎にいると、外から娘が帰ってくる。手には雑草を持っている。あどけない子は、光を帯びている。冒頭の「あゝ暗」という関西風のリアルな口語が、一気に光と闇のあざやかな対比を見せる。子は、光につつまれ、詩人は、闇につつまれている。闇は、そこにいる室内の闇だけではない。詩人の心中のすみずみにまで溶解している。
また、この対比は、花の名称というモチーフを接点とした、親子のつながりの内にも投影されている。子にとっては、その時、切実に知りたいと願っている花の名称が、詩人にとっては、朧な心中に混濁させてしまいたいと思うほどに、そのことは、些事にすぎない。
この一篇にも、些事や些景の内声が綿密な細工で描かれている。おそらく実際にここで描かれていることは事実であると思う。子は、「あゝ暗」とつぶやいてもいただろう。それは、全篇全行によって示された言葉で、確かに見えてくる。ただ、ここでも私は、伊東の外声の余情を聞いてしまう。作品の終行、末尾の言葉は、またしても描かれた些景から、「走りさる」という生と滅への急きが吐露される。
あるいは、大胆に、この一篇の詩行を読み終えた後の外声を想像してみる。光の場所と闇の場所、それが接している。私は闇の場所にいる。あるいは、闇の場所にいたいと欲している。そうしたことを意識したのは、ある時、子がふいに発した詰問であった。闇にいる私は、その時いっさいの煩わしい想を捨てて、いそぐように朧な闇を選択した。そして、闇の中に、光も色も、それから花の名辞もすべてが一束となって消えて行く。子の姿とともに。外声とは、これらが瞬く間に消えていく様子のことである。
些事や些景とともに、急くように消滅することを願う。これが伊東詩における、内外をひっくるめた詩の声である。虚無のあらわれなどといってしまうと、それで済むようなことだろうが、秀逸なのは、それらが実際の詩の構えにおいては、端正にそして淡彩にしかも薄情に仕立てられていることだ。詩人は、一篇の詩を書き終えた後、つまり最終行に至って、結ぶように、光景ともどもそれと溶解するための消滅を希求する。私は、この詩人の特質が、単に書かれた時代の気分などではないと思っている。
*
六月の夜(ルビよ)と晝のあはひに
萬象のこれは自(ルビみづか)ら光る明るさの時刻(ルビとき)。
遂(ルビつ)ひ逢はざりし人の面影
一莖(ルビいっけい)の葵(ルビあふひ)の花の前に立て。
堪へがたければわれ空に投げうつ水中花。
金魚の影もそこに閃きつ。
すべてのものは吾にむかひて
死ねといふ、
わが水無月のなどかくはうつくしき。
(詩集『夏花』「水中花」より後半)
些事や些景といっては、あまりにも鮮烈であるかもしれない。光彩に満ちた透明な時間。ガラス、水、夜の灯。結びの三行で、光景への消滅的な同化が希求されている。
詩人は、何になりたいか。こう問うてみた時、伊東ならばこう答えると思う。
私は、詩になりたい。詩の光景となって滅んでいきたいと。
「春の雪」で語られている些景の奥行は、浅い。詩人がその時住んでいた、堺市三国ヶ丘の御陵に、雪が降る。木にうっすら積もった雪が、光に透けている。「ながめゐしわれが想ひ」は、「下草のしめりもかすか」と体感し「春來むと」「ゆきふるあした」の今にいることを確かめている。
些景と言ったが、それは景物の描写に頼らないがための詩人の細い感性が選択した詩法であったろう。たとえば、俳諧における名辞や事物の象徴性に仮託させる方法に近しい。象徴性を高めるために、景物描写のまわりで修飾される雅語は、けっして浅くない。詩の内、つまり言葉の内声において、「些」であったとしても、一篇の数行を通して渡る時、そこに外なる声も響かせている。
では、外なる声とはなんだろう。
みささぎにふるはるの雪
枝透きてあかるき木々に
つもるともえせぬけはひは
なく聲のけさはきこえず
まなこ閉じ百(ルビもも)ゐむ鳥の
しづかなるはねにかつ消え
(詩集『春のいそぎ』「春の雪」全三連のうちの前二連)
詩とは、言葉によって書かれていることがすべてであるという考え方もあるだろう。伊東の場合その「すべて」が「些」にすぎない。それを内声といってしまい、書かれた詩の余情や、漏れ出る行間からの声を、外声といって、考えてみると見えてくるものがある。
もちろん伊東詩の本質を、内と外どちらに見るかといったことを考えることの方法的な正否は、別にしてである。
外の声といって、まず考えられるのが、詩人の存在を包む時代の気分があげられる。この詩が書かれたのは、戦中のまさにその最中であろう。住まいの近隣へ歩み出で、浅き春の雪に出会う。その雪は、積りもせずただ、朝の光を受けて解けはじめている。光景は、まばゆいばかりの光に満ちてはいるが、それだけにしだいに淡彩に均されて見える。圧倒的な光、そして淡く薄い眼前の様子。詩篇の行末の言葉は、「消え」である。詩人はもう、光景とともに、消滅への予感を察知している。
たとえば、この一冊の詩集の標題である『春のいそぎ』の「いそぎ」という言葉を取り出してみてもいい。詩集の標題とは、詩人の内と外を繋ぐ、特別な声なのである。仮に、この「春の雪」一篇との接点を考えてみる。「いそぎ」とは、この些景でもある儚い春の光景への没入ととらえてみよう。つまり景と情が、詩において溶解し、一つになる方途を、伊東は望んでいたのではないか。「いそぎ」「消え」、これこそが、溶解への願望と私には読める。そして外の声を想像してみると、そこに、生と滅へ急(ルビせ)くことの運命的な受苦を感ずる。
*
同『春のいそぎ』より、同じ頃に書かれたであろう、もう一篇の春の詩を引く。
春淺き
あゝ暗(ルビくら)と まみひそめ
をさなきものの
室(ルビしつ)に入りくる
いつ暮れし
机のほとり
ひぢつきてわれ幾刻(ルビいくとき)をありけむ
ひとりして摘みけりと
ほこりがほ子が差しいだす
あはれ野の草の一握り
その花の名をいへといふなり
わが子よかの野の上は
なほひかりありしや
目とむれば
げに花ともいへぬ
花著(ルビつ)けり
春淺き雑草の
固くいとちさき
實(ルビみ)ににたる花の數(ルビかず)なり
名をいへと汝(ルビなれ)はせがめど
いかにせむ
ちちは知らざり
すべなしや
わが子よ さなりこは
しろ花 黄い花とぞいふ
そをききて点頭(ルビうなづ)ける
をさなきものの
あはれなるこころ足らひは
しろばな きいばな
こゑ高くうたになしつつ
走りさる ははのゐる厨の方(ルビかた)へ
(同詩集「春淺き」全篇)
伊東の詩の中でも、最も私が好んでいる一篇である。詩集『春のいそぎ』の中に詩人がひそませた、佳篇。ある日の家族の光景ととらえることができる。詩人が暗い書斎にいると、外から娘が帰ってくる。手には雑草を持っている。あどけない子は、光を帯びている。冒頭の「あゝ暗」という関西風のリアルな口語が、一気に光と闇のあざやかな対比を見せる。子は、光につつまれ、詩人は、闇につつまれている。闇は、そこにいる室内の闇だけではない。詩人の心中のすみずみにまで溶解している。
また、この対比は、花の名称というモチーフを接点とした、親子のつながりの内にも投影されている。子にとっては、その時、切実に知りたいと願っている花の名称が、詩人にとっては、朧な心中に混濁させてしまいたいと思うほどに、そのことは、些事にすぎない。
この一篇にも、些事や些景の内声が綿密な細工で描かれている。おそらく実際にここで描かれていることは事実であると思う。子は、「あゝ暗」とつぶやいてもいただろう。それは、全篇全行によって示された言葉で、確かに見えてくる。ただ、ここでも私は、伊東の外声の余情を聞いてしまう。作品の終行、末尾の言葉は、またしても描かれた些景から、「走りさる」という生と滅への急きが吐露される。
あるいは、大胆に、この一篇の詩行を読み終えた後の外声を想像してみる。光の場所と闇の場所、それが接している。私は闇の場所にいる。あるいは、闇の場所にいたいと欲している。そうしたことを意識したのは、ある時、子がふいに発した詰問であった。闇にいる私は、その時いっさいの煩わしい想を捨てて、いそぐように朧な闇を選択した。そして、闇の中に、光も色も、それから花の名辞もすべてが一束となって消えて行く。子の姿とともに。外声とは、これらが瞬く間に消えていく様子のことである。
些事や些景とともに、急くように消滅することを願う。これが伊東詩における、内外をひっくるめた詩の声である。虚無のあらわれなどといってしまうと、それで済むようなことだろうが、秀逸なのは、それらが実際の詩の構えにおいては、端正にそして淡彩にしかも薄情に仕立てられていることだ。詩人は、一篇の詩を書き終えた後、つまり最終行に至って、結ぶように、光景ともどもそれと溶解するための消滅を希求する。私は、この詩人の特質が、単に書かれた時代の気分などではないと思っている。
*
六月の夜(ルビよ)と晝のあはひに
萬象のこれは自(ルビみづか)ら光る明るさの時刻(ルビとき)。
遂(ルビつ)ひ逢はざりし人の面影
一莖(ルビいっけい)の葵(ルビあふひ)の花の前に立て。
堪へがたければわれ空に投げうつ水中花。
金魚の影もそこに閃きつ。
すべてのものは吾にむかひて
死ねといふ、
わが水無月のなどかくはうつくしき。
(詩集『夏花』「水中花」より後半)
些事や些景といっては、あまりにも鮮烈であるかもしれない。光彩に満ちた透明な時間。ガラス、水、夜の灯。結びの三行で、光景への消滅的な同化が希求されている。
詩人は、何になりたいか。こう問うてみた時、伊東ならばこう答えると思う。
私は、詩になりたい。詩の光景となって滅んでいきたいと。










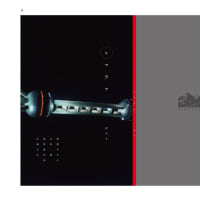



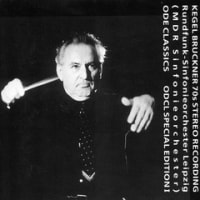




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます