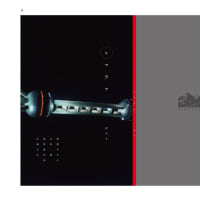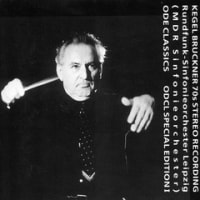夏の詩人13 花鳥と燈
詩集『夏花』は、『わがひとに与ふる哀歌』(昭和十年)と『春のいそぎ』(昭和十八年)の間、昭和十五年に刊行されている。全二十一篇から成る。この詩集について伊東は、次のように述べている。
『詩集夏花』は、一部を大阪市内の狭い露地の家で、大部分を、堺市北三国ヶ丘の斜面に立つてゐる家で書いた。ここに引越すとすぐ大陸の戦争が起こつた。坂下の大道路を幾日も大軍団が通るのを眺めた。――<中略>――私は毎日のやうに子供をつれて路傍に立ち、敬礼した。家にじつと坐つてゐても、胸がはあはあと息づき強く、我慢出来ず興奮したりした。そんななかで、わたしの書く詩は、依然として、花や鳥の詩になるのであつた。
(『コギト』昭和十五年五月 傍点筆者)
この「依然として」という言葉であるが、詩人のこれまでの作品傾向のモチーフを語っているのではないだろう。この四年半前に出版された『わがひとに与ふる哀歌』を見ても、「花や鳥」が材となっている作品はそれほど多くはない。むしろ詩人の想念に浮かぶ叙景をしるした作品を多く見受けられる。そうすれば、「依然として」と述べた意味合いは、むしろ「そんななかで」という時流の空気に反したひとつの釈明として語られているように感じられる。つまり「依然として」とは、『哀歌』刊行以後の昭和十年から、十四年までのより激化する戦中の空気に対応した言葉であろうと思われる。
それから、引用末尾の言葉「なるのであつた」も気になる。これは、詩人が意図して「花や鳥」を材として書いたというよりも、むしろ消極的な意味において、なぜだかそう「なるのであつた」と述懐しているようにも読める。
さて、詩集『夏花』であるが、全21編の作品をひと通り眺めていけば、ほとんどすべてといっていいくらいに、花、鳥、虫、魚などの生き物の気配があらわれる。
草むらに子供は踠(ルビもが)く小鳥を見つけた。
子供はのがしはしなかつた。
けれど何か瀕死に傷いた小鳥の方でも
はげしくその指に噛みついた。
子供はハツトその愛撫を裏切られて
小鳥を力まかせに投げつけた。
小鳥は奇妙につよく空(ルビくう)を蹴り
飜り 自然にかたへの枝をえらんだ。
自然に? 左様 充分自然に!
――やがて子供は見たのであつた、
礫(ルビこいし)のやうにそれが地上に落ちるのを。
そこに小鳥はらくらくと仰けにね転んだ。
(『自然に、充分自然に』全編)
伊東の代表作ともいえる『水中花』の次に配された作品。『水中花』においては描かれた材が、色彩的にも音楽的にもある種の象徴力をもって微細に描写されているのに比べて、本作は意図して淡彩に描写されているように思える。「小鳥」に対する視線としては、冷徹でもあり、薄情にも思える。
詩人が見た、情景が実際のものであったか、想像上のものであるかはわからない。ただ、この作品で描かれていることは、とても単純である。子供がいる。傷を負った小鳥を見つけ一度は手にとったが、小鳥はその手を逃れ、一旦は樹木の枝にとまったが、地に落ちて死んでしまった。これだけである。しかしよくよく詩篇を見てみると、4行ずつの3連、全12行から成る作品に「小鳥」という言葉が5回、「子供」が4回も記されている。これは、ある種の客観的記述に徹しようとする姿勢であろうか。それとも観察文や写生文に模して、極力、主観的な「思い入れ」を抑制したのだろう。これは、『水中花』に向かう
姿勢とまったく異なっている。
そしてこの姿勢とはどこに因があるかを見つめるとき、昭和4年に書かれた詩人の卒業論文『子規の俳論』に行き当たる。
しかして子規は芸術に於ける主観を知識的なものにまで堕せしめないもつともよき方
法として、先づ主観を没せよ、只ありの儘に自然を見、そのまま模倣せよと言ふ写生
主義を唱へたのである。――<中略>――次に「理想の弊害」として彼は知識的主観
のほかに今一つ陳腐なる「感情的主観」も指摘してゐる。
(『子規の俳論』)
「依然として」「なるのであつた」、「花や鳥」とは、主観を排した、それは、冷徹な目で向けられた、時代の状況、もしくは、その潮流に無言のまま流されて生きる民の喩えであろうか。そう私には読める。また、この詩篇の題『自然に、充分自然に』という言葉もまた、卒業論文の文中にある「先づ主観を没せよ、只ありの儘に自然を見、そのまま模倣せよ」に照応しているように読める。
ただ、いくら冷徹に淡々と小鳥と子供のいる光景を写生したとしても、否、淡々と描写しているからこそ、それを見つめる作者の位置と姿が、逆に反照されて浮かび上がってくる。
彼の写生といふことが単に在外物象の何等主観の裏づけなき写真術的模倣にとどまら
ず、それを通過して、その最も反極に立つ所の物象の内的真といふこと、客観を描く
ことによつて自己の態き主観を表現しようとする様な境地にまで飛躍しつつあること
を認め得るといふことである。
(同)
写生する客観的対象としてある、「花や鳥」にもはや、伊東静雄の思い入れ(「感情的主観」)はない。それは、時代の大局という背景をあらわす気配といってもよい。では、それらを透徹してさらに、あぶりだされる「自己の主観」とはどこにあるのだろうか。
詩集『夏花』の詩篇を見ていると、「花や鳥」のほかにもうひとつの重要な像が浮かびあがってくる。それは、「光や燈」のイメージだ。
万象のこれは自(ルビみづか)ら光る明るさの時刻(ルビとき)。 (『水中花』)
燈台の頂には、気附かれず緑の光が点(ルビとも)される。 (『夕の海』)
あゝわれら自(ルビみづか)ら弧寂(ルビこせき)なる発光体なり! (『八月の石にすがりて』)
燈台の緑のひかりが 彷徨(ルビさまよ)ふ (『燈台の光を見つつ』)
仔細に見ればさらに多く、この光の像が散見される。たとえば、燈台、光を発するものは、弧寂ではあるが、透明で繊細で鋭敏で強い意志も感じられる。角度を変えてみれば、ほとんど思い入れのない写生の対象である「花や鳥」の反極とも言えるこれこそが、伊東の喩的身体(内的真)なのではないか。
伊東静雄における「花や鳥」そして「光や燈」は、けっして彼の詩における“抒情の具”ではない。たとえば吉増剛造は、伊東の詩を読んだ印象として次のように述べている。
まず気づいたことは、全く予想に反して、伊東静雄の詩から季節感が感じられなかっ
たことだ。
(思潮社・現代詩文庫『伊東静雄詩集』)
そこに描かれた、「花や鳥」は主観的に託された喩えではない。ましてや、日本的な古雅の象徴でもなんでもない。ある種名を与えられた生き物であり、光景の中の事物に近いと言ってもいい。伊東はむしろ、そこを貫いたその先(奥)にある、鋭敏でこわれやすい発光する我を現出させたかったのだろう。
詩集『夏花』は、『わがひとに与ふる哀歌』(昭和十年)と『春のいそぎ』(昭和十八年)の間、昭和十五年に刊行されている。全二十一篇から成る。この詩集について伊東は、次のように述べている。
『詩集夏花』は、一部を大阪市内の狭い露地の家で、大部分を、堺市北三国ヶ丘の斜面に立つてゐる家で書いた。ここに引越すとすぐ大陸の戦争が起こつた。坂下の大道路を幾日も大軍団が通るのを眺めた。――<中略>――私は毎日のやうに子供をつれて路傍に立ち、敬礼した。家にじつと坐つてゐても、胸がはあはあと息づき強く、我慢出来ず興奮したりした。そんななかで、わたしの書く詩は、依然として、花や鳥の詩になるのであつた。
(『コギト』昭和十五年五月 傍点筆者)
この「依然として」という言葉であるが、詩人のこれまでの作品傾向のモチーフを語っているのではないだろう。この四年半前に出版された『わがひとに与ふる哀歌』を見ても、「花や鳥」が材となっている作品はそれほど多くはない。むしろ詩人の想念に浮かぶ叙景をしるした作品を多く見受けられる。そうすれば、「依然として」と述べた意味合いは、むしろ「そんななかで」という時流の空気に反したひとつの釈明として語られているように感じられる。つまり「依然として」とは、『哀歌』刊行以後の昭和十年から、十四年までのより激化する戦中の空気に対応した言葉であろうと思われる。
それから、引用末尾の言葉「なるのであつた」も気になる。これは、詩人が意図して「花や鳥」を材として書いたというよりも、むしろ消極的な意味において、なぜだかそう「なるのであつた」と述懐しているようにも読める。
さて、詩集『夏花』であるが、全21編の作品をひと通り眺めていけば、ほとんどすべてといっていいくらいに、花、鳥、虫、魚などの生き物の気配があらわれる。
草むらに子供は踠(ルビもが)く小鳥を見つけた。
子供はのがしはしなかつた。
けれど何か瀕死に傷いた小鳥の方でも
はげしくその指に噛みついた。
子供はハツトその愛撫を裏切られて
小鳥を力まかせに投げつけた。
小鳥は奇妙につよく空(ルビくう)を蹴り
飜り 自然にかたへの枝をえらんだ。
自然に? 左様 充分自然に!
――やがて子供は見たのであつた、
礫(ルビこいし)のやうにそれが地上に落ちるのを。
そこに小鳥はらくらくと仰けにね転んだ。
(『自然に、充分自然に』全編)
伊東の代表作ともいえる『水中花』の次に配された作品。『水中花』においては描かれた材が、色彩的にも音楽的にもある種の象徴力をもって微細に描写されているのに比べて、本作は意図して淡彩に描写されているように思える。「小鳥」に対する視線としては、冷徹でもあり、薄情にも思える。
詩人が見た、情景が実際のものであったか、想像上のものであるかはわからない。ただ、この作品で描かれていることは、とても単純である。子供がいる。傷を負った小鳥を見つけ一度は手にとったが、小鳥はその手を逃れ、一旦は樹木の枝にとまったが、地に落ちて死んでしまった。これだけである。しかしよくよく詩篇を見てみると、4行ずつの3連、全12行から成る作品に「小鳥」という言葉が5回、「子供」が4回も記されている。これは、ある種の客観的記述に徹しようとする姿勢であろうか。それとも観察文や写生文に模して、極力、主観的な「思い入れ」を抑制したのだろう。これは、『水中花』に向かう
姿勢とまったく異なっている。
そしてこの姿勢とはどこに因があるかを見つめるとき、昭和4年に書かれた詩人の卒業論文『子規の俳論』に行き当たる。
しかして子規は芸術に於ける主観を知識的なものにまで堕せしめないもつともよき方
法として、先づ主観を没せよ、只ありの儘に自然を見、そのまま模倣せよと言ふ写生
主義を唱へたのである。――<中略>――次に「理想の弊害」として彼は知識的主観
のほかに今一つ陳腐なる「感情的主観」も指摘してゐる。
(『子規の俳論』)
「依然として」「なるのであつた」、「花や鳥」とは、主観を排した、それは、冷徹な目で向けられた、時代の状況、もしくは、その潮流に無言のまま流されて生きる民の喩えであろうか。そう私には読める。また、この詩篇の題『自然に、充分自然に』という言葉もまた、卒業論文の文中にある「先づ主観を没せよ、只ありの儘に自然を見、そのまま模倣せよ」に照応しているように読める。
ただ、いくら冷徹に淡々と小鳥と子供のいる光景を写生したとしても、否、淡々と描写しているからこそ、それを見つめる作者の位置と姿が、逆に反照されて浮かび上がってくる。
彼の写生といふことが単に在外物象の何等主観の裏づけなき写真術的模倣にとどまら
ず、それを通過して、その最も反極に立つ所の物象の内的真といふこと、客観を描く
ことによつて自己の態き主観を表現しようとする様な境地にまで飛躍しつつあること
を認め得るといふことである。
(同)
写生する客観的対象としてある、「花や鳥」にもはや、伊東静雄の思い入れ(「感情的主観」)はない。それは、時代の大局という背景をあらわす気配といってもよい。では、それらを透徹してさらに、あぶりだされる「自己の主観」とはどこにあるのだろうか。
詩集『夏花』の詩篇を見ていると、「花や鳥」のほかにもうひとつの重要な像が浮かびあがってくる。それは、「光や燈」のイメージだ。
万象のこれは自(ルビみづか)ら光る明るさの時刻(ルビとき)。 (『水中花』)
燈台の頂には、気附かれず緑の光が点(ルビとも)される。 (『夕の海』)
あゝわれら自(ルビみづか)ら弧寂(ルビこせき)なる発光体なり! (『八月の石にすがりて』)
燈台の緑のひかりが 彷徨(ルビさまよ)ふ (『燈台の光を見つつ』)
仔細に見ればさらに多く、この光の像が散見される。たとえば、燈台、光を発するものは、弧寂ではあるが、透明で繊細で鋭敏で強い意志も感じられる。角度を変えてみれば、ほとんど思い入れのない写生の対象である「花や鳥」の反極とも言えるこれこそが、伊東の喩的身体(内的真)なのではないか。
伊東静雄における「花や鳥」そして「光や燈」は、けっして彼の詩における“抒情の具”ではない。たとえば吉増剛造は、伊東の詩を読んだ印象として次のように述べている。
まず気づいたことは、全く予想に反して、伊東静雄の詩から季節感が感じられなかっ
たことだ。
(思潮社・現代詩文庫『伊東静雄詩集』)
そこに描かれた、「花や鳥」は主観的に託された喩えではない。ましてや、日本的な古雅の象徴でもなんでもない。ある種名を与えられた生き物であり、光景の中の事物に近いと言ってもいい。伊東はむしろ、そこを貫いたその先(奥)にある、鋭敏でこわれやすい発光する我を現出させたかったのだろう。